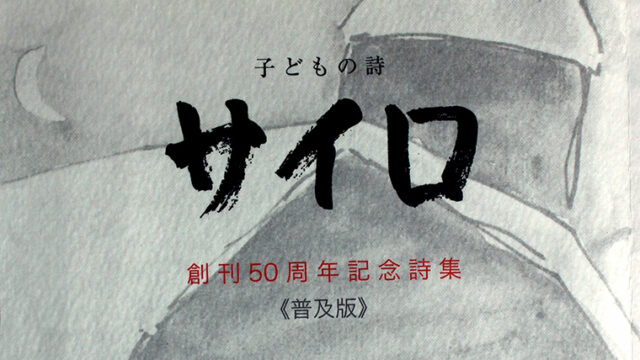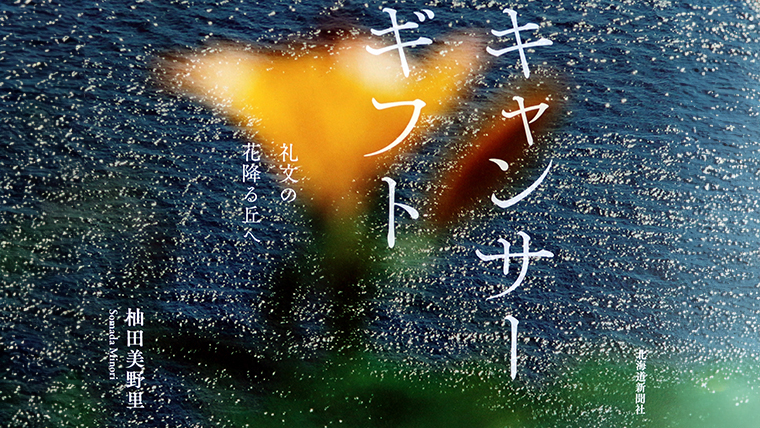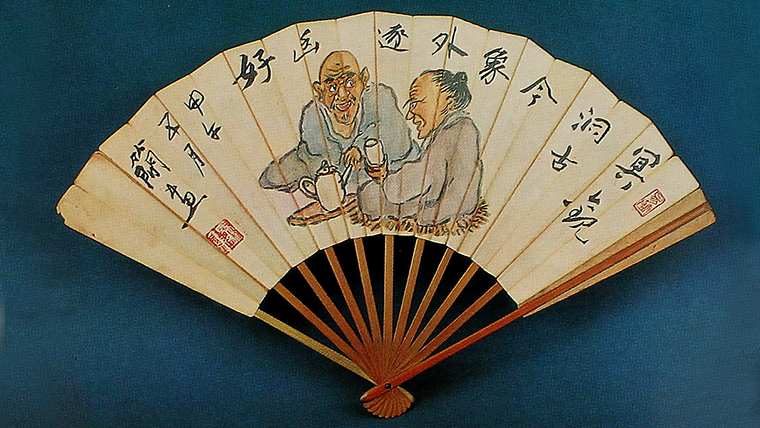本書のカバーには「紙と鉛筆をもぎ取られた私は、石に爪で書きつける思いでこの五年間の経緯を書いた」とある。あとがきにも「この記録の内容の性格をあらゆる客観情勢から考えて、私の鉛筆はもぎとられていると思う。……いつかは、石に爪ででも書き残しておかねばならぬ心情は常にあった」と書いている。よほどの覚悟で書いたであろうことが伝わってくる。
本書で、大森氏は一貫して新聞の編集権、権力から独立した新聞の権威ということを強く主張している。彼はその点で、アメリカ政府の圧力をはねのけ、「ペンタゴン ベトナム秘密報告書」の掲載に踏み切ったニューヨークタイムズを初めとするアメリカ各紙とそこに属する記者の勇気を高く評価し、それに刺激を受けたことを繰り返し強調し、それが本書執筆の動機の一つであったことを明かしている。「まえがき」を読むと、大森氏が本書の執筆を始めたのは、ニューヨークタイムズが「ベトナム秘密報告書」の掲載を始めて間もなくのことだ。大森氏も又毎日新聞社の外信部長の職にあってベトナム戦争の報道に情熱を傾けていた。
本書をコラムで取り上げるのは、この事件が日本のジャーナリズム史にとって看過できない内容を含んでいると思えるからだ。
ではライシャワー事件とは何だったのか。『石に書く』の記述に沿い概略を見ていこう。
問題の発端
1965年9月23日、西側の記者として初めて、米軍北爆下の北ベトナム入りした毎日新聞外信部長の大森実氏は、10月2日、アメリカ軍のライ(原文のママ、以下同じ)病院爆撃について送稿し、10月3日付の毎日新聞に掲載された。この記事で大森氏は、これより先、一連のハノイ報告の第二報として、未確認のままの情報として米国のライ病院爆撃についてレポートを送ったが、「ゲアン省クイン・ラップ・ライ・センターが激しい爆撃にあい、壊滅的な損害をうけたのは事実であることを知らされた」という前書きで爆撃の状況を詳しく書いている。
大森氏は「ベトナム外務省の案内で国立映画部を訪れ、同映画部が撮影したライ病院爆撃の実写フィルムを見せられ、このような鬼気迫る情景を活字によって再現するに忍びないが、やはりこれを報道せねばなるまい」と書き起こし、次のように具体的な状況を描写している。「低空で米軍機があるいは三機あるいは五機編隊で空中に描き出され、砲煙と爆弾の中を、松葉づえをついた患者が逃げまどい、看護婦が歩けない患者を背負って防空壕に逃げて行く目の前を爆弾が炸裂し、ナパーム弾が火を吹くのだ。……2300人の患者を収容できる病院が160の建物を破壊された、先に会った軍部の首脳は憤り、必ず証拠を見せましょうと語っていた……。」
大森氏は、もちろんこの記録映画は北ベトナム国民の反米意識高揚のための宣伝映画に違いないが、第三国人の我々は完全に頭をかかえてしまうとレポートを結んでいる。(この記録映画は大森氏から一週間後にハノイ入りした朝日新聞の秦正流外報部長も同席して見ていた。)大森氏はすでに、ハノイ入り三日目の9月25日に、後にパリ会談の北ベトナム次席代表となるハ・バン・ラウ大佐と会見した際、このライ・センターが6月12日から22日まで十日間にわたり連続爆撃を受け、甚大な被害を受けたことを記録した公式文書を受け取っていた。
ライシャワー大使の反撃
このレポートが掲載された2日後の10月5日、アメリカのライシャワー駐日大使は、大阪で開かれた大阪日米協会、関西アメリカ商工会議所共催の昼食会でスピーチし、その後記者会見をした。その日の朝、大使は通訳を介して毎日新聞に電話をいれ、これから大阪に行き、重大声明を発表すると予告していた。記者会見での一問一答でライシャワー大使は要旨次のような発言をした。発言の内容は速記録をもとにしていると大森氏は述べている。(質問をしたのは主として毎日新聞大阪社会部の大橋久利記者)
ライシャワー:皆さんは以前サイゴンから報道をした。ところが今はハノイから報道している方もいる。大森実さんとか秦正流さんのことを言っているのだが、サイゴンとハノイの報道の仕方の違いはどうだろう。日本の新聞記者はサイゴンに行くとかなりの先入観を持っていて、南ベトナム政府の言うことに耳をかさず、裏から物を見ようとする。ところがハノイに行けば、警察国家の宣伝文句を受け取り、それをそのまま鵜呑みにし、ニュースとして日本に流す。それでは公平ではない。何という報道だろう。
(ここで記者が反論する)
大橋記者:ベトナム戦争の報道が片寄っているとの話だったが、それは間違いだ。私の方の大森特派員も、北ベトナムに行っていろいろ報道しているが、向こうに行って一番先に北ベトナム当局に要請したのは、話しを聞くだけでは十分ではない、聞いた話だけだったら、いつも疑うという本性を日本人記者は持っている。だから現実を見せてほしいということで、大森はやっと小学校や病院がアメリカによって爆撃されている証拠を自分の目で見たわけだ。
ライシャワー:大森さんの名が出たところで、一言いいたいが、宣伝映画を見たことが現物を見たことになるのか。アメリカが十日間もライ病院を爆撃したというようなことを長文の記事にしているが、気がおかしくないかぎり十日間も続けて病院を爆撃する者がいるだろうか。そんなことは常識ではない。しかし大森さんは、自分は信じたくないのだが、映画で見せてもらったのだから信じないわけにはいかないと言っている。映画は純然たる宣伝であり、明らかな宣伝と自分の目で見たことの区別がつかないようでは、新聞記者の資格に欠けるといわなければならない。
大橋記者:映画を見て帰った話ではなく、朝日の秦記者も全く同じ事をいっている。小学校や……それに隣の病院もやはり大分ひどい被害を受けている。そういうことを、ちゃんと彼らの目で確かめ日本の新聞の朝刊で報道している。……日本の新聞というもの、あるいは報道全体というものを謙虚に理解してほしい。こういうことを大使が公の席でいわれることはわれわれの立場として面白くないことだ。もっと表現を考えてはどうか。
記者の言葉の中で新聞の朝刊というのは、10月3日ハノイ発の大森氏の戦線視察記のことで、大森氏は記者の指摘通り、爆撃された病院(記録映画で見たライセンターではない)や学校の目撃記を送稿していた。だがライシャワー大使は大橋記者の最後の質問に答えることはなかった。大森氏の戦線視察記は、ライシャワー大使の記者会見の前日の10月4日の夕刊に報道されていた。大森氏は、ライシャワー大使はこれを見落として日本の記者は現場を見ずに報道している、記者としての資格に欠けるという重大な発言を行ったのではないかと見ている。
ライシャワーは3日朝刊のライ病院爆撃のフィルム報道を見て、「とうとう大森をつかまえたぞ……アイ・ゴット・オオモリ!」と叫び、大使館の政治スタッフを非常招集し、対大森攻撃の声明を準備させたという。この叫びは前回のコラムで紹介した『泥と炎のインドシナ』などに見られる大森外信部長主導のベトナム報道に不満を鬱積させていたライシャワー大使の快哉の叫びだったのだろう。
大森と秦とは区別する
ここで朝日新聞の記者が質問する。前に指摘したように朝日新聞の秦外報部長も大森氏よりやや遅れてハノイ入りしていた。
朝日の記者:私の新聞社の秦特派員が書いた記事にライシャワー大使からいろいろ批判の声があったのだが……。
ライシャワー:私は秦さんの名前を口にした。しかし、私は秦さんを批判はしなかったし、また批判するつもりもない。私が言ったのは、取材源が違う、一方では政府の手渡す資料であり、他方では資料の裏側を眺めようとするということだ。私は秦さんの書いたものを全部読んだわけではないが、秦さんの報道の多くは、この人はああ言った、あの人はああ言ったというように引用されている。秦さんは、映画のフィルムが証拠であるかのように、それに基づいて記事を書くようなことはしていないと思う。この点、大森さんと区別しておきたい。
ところがこのライシャワー発言の二日後の朝日新聞に、秦氏のハノイ発の次のような記事が載った。「当局の宣伝もあるだろうが、北ベトナム国民の米国に対する敵愾心は北爆によってかえって熱せられたのではないか。特にタンホアのあのライ病院の被爆状況を映した映画を見せられたり、学校や幼稚園、合作社の農民に対する無差別爆撃の状況が知らされるにつれ、国民の抗米戦闘意識はますます高められて来ているようだ。」大森氏によると、この記事でタンホアのライ病院とあるのはクイン・ラップ・ライ・センターのことであり、秦氏のミステイクだという。大森氏はこの二日間の差は、ライシャワーにとって “毎日・朝日分断作戦” を決定的に立案する材料として役立ったであろうと指摘している。ライシャワー大使は更に「ベトナムの問題についてみなさんは何らかの誤った先入観を持っていて、そういうところから多くの点で不幸な誤解が出てくるのではないかと思う」と話した。
このライシャワー発言と時を同じくして、在日米大使館のスコット報道官は、大使館に日本人記者団を緊急招集し、「共産側は、北ベトナムのライ病院に対し米国が故意に無差別爆撃を行った旨非難していると、毎日新聞外信部長の大森実氏が同紙に報道しているが、これは全く事実に反している。こうした流言は、これまでにも北ベトナム政権が宣伝の事前工作として飛ばしてきたところだ……」という米大使館声明を発表した。
大森氏とライシャワー大使のもつれの始まり
本書では、大森氏とライシャワー大使のもつれが、1965年4月29日の天皇誕生日に始まったことを明らかにしている。詳細は省くが、この日アメリカの上院外交委員会で、前駐日大使のマッカーサー二世とポール国務次官補がこもごも日本の新聞のベトナム報道をめぐり、毎日新聞の編集者の中には多数の共産主義者がいる、朝日新聞の編集局には共産党員が200名もいた、などと証言したというのだ。
大森氏はこの件についてライシャワー大使に会見を求め抗議するとともに、アメリカ政府を代表する大使としての態度表明を夜の12時までに公式声明として出すように要求した。
その日の深夜ライシャワー大使の声明が毎日新聞に届けられた。そこでは「日本の新聞が米国の政策と意見を異にし、あるいは批判する場合においてさえ、我々は日本の新聞の職業的信念と進取の気性をたたえ、不偏不党の率直さを歓迎し、かつその政治的な誠実さに敬意を払うものである」と述べられていた。大森氏は、この声明に関する限り、米政府側の全面降伏であり、ライシャワー大使は良心的であったと思うし、日本の新聞の権威は保全されたと思うと述べている。
執筆停止処分
大森氏は、これより先の1965年4月14日付一面トップ扱いでベトナム戦争の現状を分析した長文の署名記事を書いた。ベトナム戦争は手詰まりの状態に陥っており、最悪事態と見るべきだというのがその主旨だった。所がその日、フランスのフォール元首相の講演会会場にいた大森氏は同紙の狩野編集局長に呼び止められ、執筆停止を告げられた。大森氏は社の内外で自分に対する目に見えない圧力が次第に強まりつつあることを感知していたという。執筆停止を告げられる一週間前、大森氏は狩野編集局長から、編集局員が署名原稿を書く場合、最高首脳部の事前了解をとるようにと指示されていた。14日の記事はこの指示を破ったということなのだった。大森氏はこの執筆停止の処分を「私刑的刑罰」と言っている。
大森氏は、社を辞することを考えたが、一週間後には辞意を翻し、書かざる外信部長となった。本書にはこの間の複雑な経緯やこれまでの取材の成果など多くの事が執筆停止事件の背景として記述されている。
ハノイ入り前後
大森氏がハノイ一番乗りを決意したのは1965年の6月ごろだったという。初めは外信部の副部長を行かせるつもりにしていたが、副部長から、あなたがやらぬと朝日に負けると言われ、やらねばならぬと思ったという。そんなある日、田中香苗編集主幹から「ハノイはどうだ、キミが負けたり、遅れを取ったりはしないだろうね」とけしかけられたという。書くな、と言いながらどういうことかと理解に苦しんだが、大森氏はどうしてもやれというならと否やはなかった。このあとインドネシアのスカルノ大統領を介したハノイ入りの工作などが詳しく書かれているが、省略する。
9月18日、中国の通過ビザ待ちのため香港入りした大森氏に、9月25日までにハノイに入り、第一報を送るようにという本社の指令が届いた。それは26日の朝刊に新聞の定価値上げの社告を出すので、大森氏のスクープで読者の不満を薄めようという狙いがあったのだという。大森氏は怒り狂ったが、奇跡的に23日にハノイ入りに成功した。
大森氏はそれから14日間にわたり、朝刊、夕刊に長大なハノイ報告を書きつづけるのだが、その間、冒頭にある通りライシャワー事件が起こっていたのである。
ハノイ報告を書き終えて香港に戻った大森氏にTBSラジオから電話がかかり、ライシャワー発言のあらましを告げられるとともにコメントを求められた。大森氏のコメントは「ここでいえることは、東京の赤坂の大使館にいるアメリカの大使などに、何を発言する資格があるかということだ。私は、いま爆撃下の北ベトナムから、泥まみれ汗まみれで香港に辿りついたところだと言えることです」というものだった。これより先、大森氏が宿泊する予定のホテルには毎日新聞の指令として「至急、帰国されたい」という電報が届いていた。大森氏は、インドネシアのスカルノ大統領から中国の毛沢東主席、周恩来総理への紹介状ももらっており、毛、周両氏と単独会見をすべく、すぐにも中国入りを模索するつもりだったが、社命とあっては帰国せざるを得なかった。
大森氏は香港から2本の原稿を打った。一本は、短いライシャワー大使への反撃電報、これは完全に押さえられたという。もう一本は、帰国後に掲載されたが、ハノイ報告の総括の原稿だった。これが、大森氏が毎日新聞紙上に書いた最後の原稿となった。執筆停止の解除はハノイに行き帰国するまでの束の間のことだった。
退社まで
大森氏は帰国の夜、外信部員たちから、社内の保守的思想の持ち主たちが、ハノイ報告を批判していることを聞かされた。批判の一つはライ病院爆撃を書いたことがライシャワー大使に嘘をつく材料を与えたというものだった。
一方ライシャワー大使の「朝日・毎日分断作戦」は現実となって表れ、朝日の秦外報部長は帰国後すぐワシントンに飛び、ラスク国務長官と会見、アメリカ側の言い分を報道した。朝日は公平だというわけだ。これに対抗し大森氏は、小西健吉ワシントン支局長に民主党のマンスフィールド院内総務と会見させた。
大森氏はライシャワー大使の批判に沈黙、動揺している毎日新聞首脳部に対し、社内の結束とベトナム戦争の深い理解をとりつけることの必要性を痛感、田中編集主幹宛に長文の建白書を書き、10月20日の朝に田中主幹のもとにとどけさせた。この建白書は、毎日新聞が姿勢を正し、ライシャワー大使の批判に対し社説をかかげ、堂々と対決すべきだという心情を切々と訴えたものだったという。
ところが10月20日、毎日新聞夕刊に一読者の問いに答えるという形式での記事が出た。大森氏はこの“釈明”の内容を事前に知っていたので、田中主幹宛に建白書を書いたのだという。釈明は次のような言葉で結ばれていた。
「ライシャワー大使が日本の新聞に対しあのような激しいことばを使って非難したのは、これを推測するに、おそらくはライシャワー大使の、日本及び日本の新聞に対する特別の親愛の情から出たものであろう。つまり職業的外交官としてではなく、日本に対し深い理解を持ち、真に日本の友人といわれるライシャワー大使が、その日本に対する親愛の情から、あのような新聞批判をしたものと我々は信じている。ただもしそうであるなら、親愛の情のあふれる批判としては、それにふさわしいことばの選択がなされてしかるべきだったと思われる。」
大森氏は、このような社の態度はまことに卑屈で、この腰の曲がった新聞社の姿勢を正すために居残って戦うべきか、社を辞めるかの選択に迷いだした、と述懐している。
外務省の曾野明情報文化局長が定例の外人記者会見で語った内容が、11月5日付の毎日新聞夕刊に、「ベトナム報道、日本の世論と無関係」「外務省曾野局長、日本の新聞批判」という見出しで掲載された。UPI通信の報道だった。
社説で世の新聞不信に答えるべきだとする大森氏と、これを拒否し「釈明」で十分とする社側の意見が対立しまままの中で、大森氏は持病のメニエル氏症候群を治療するため入院し、長期病欠に入った。
1966年1月8日、毎日新聞の朝刊に「ベトナムの断層」と題する新企画の連載が掲載された。「サイゴン発、本社編集顧問、林三郎」の署名記事だった。この署名記事の中には、「最近になって、ベトナムの新聞に日本の論調が時々出るようになった。それはベトコンに同情的であり、ベトコンと北ベトナムを民族解放の戦士、独立のにない手のように扱っている。……これほどまでに日本を信じ愛してくれている(南)ベトナムの人々に、日本がどうすることもできないのみか、彼らの足をひっぱるような論調が多いのは、彼らの友情を裏切るような思いがして唖然となった」というくだりがあった。この記事は大森氏に自分の「ハノイ報告」を打ち消す意図を持つものだという印象を与えた。
激怒した大森氏は外信部長として、以後の連載を止めるように部下に指示したが、ならなかった。そんな中、部下の一人が辞表を出した。「ベトナムの断層」の掲載に踏み切ったことへの抗議であったことは間違いないと大森氏は判断、それで大森氏の退社の意志がかたまった。田中編集主幹は強く慰留し、大森氏の辞表を受け付けなかったが、大宅壮一が辞表提出の斡旋をした。
大森氏が辞表を提出し、毎日新聞の編集局を去ったのは1966年1月13日のことだった。
あとがきで
「あとがき」には大森氏の新聞報道に対する信念が吐露されている。
「常に強者が勝つという権力の論理は矛盾を内蔵し、弱者の犠牲の上に成り立っている。強者には新聞の味方はいらないが、弱者に新聞の保護は必要だ。権力への挑戦は新聞に課せられた崇高な義務である。権力への挑戦を忘れた新聞は、弱者の大衆から敬遠されよう。新聞は常に瓦版でなければならず、新聞の権威は民衆のために存在する」
このコラムは『石に書く』の内容をごくごくかいつまんで紹介したに過ぎない。本書の中にはベトナム関連報道を巡る取材の裏話、毎日新聞社編集局の内部事情、大森氏と内外の多くの政界、財界人らとの交流、交渉をめぐる裏話なども書かれているが、このコラムではライシャワー事件の大まかな経緯を記述するにとどめた。
大森氏は、毎日新聞を退社後3年間、週刊新聞「東京オブザーバー」を主宰、70年3月に休刊後は国際問題を中心に執筆活動に専念、同年アメリカに移住、カリフォルニア大学アーバイン校で歴史文学部教授を勤めるなどした。