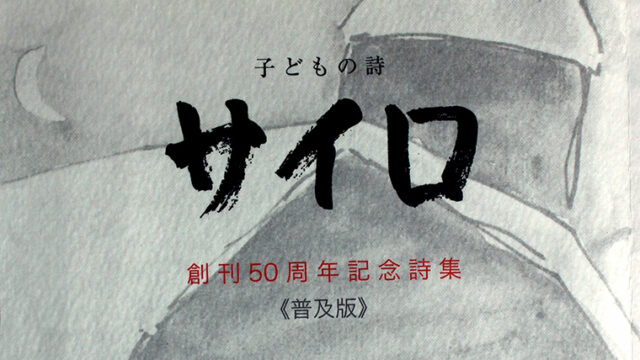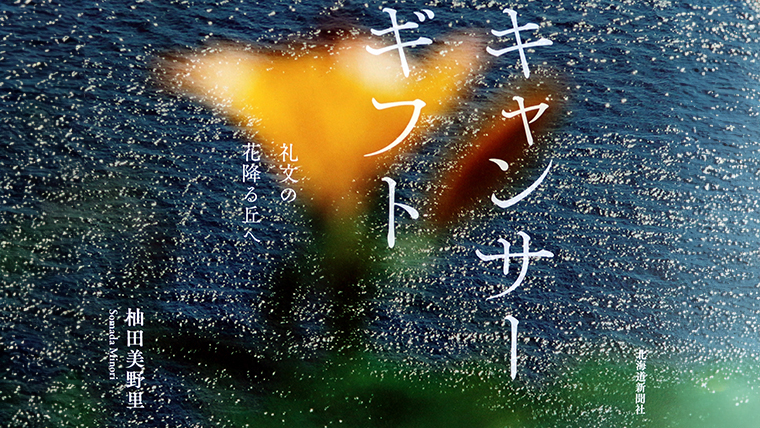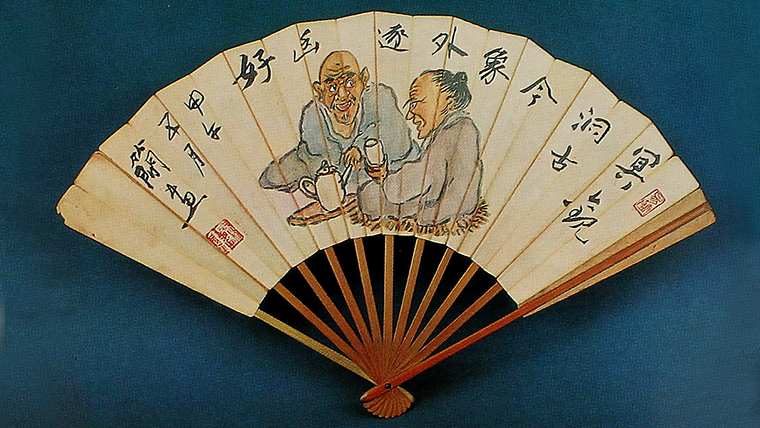本書の監修者・大森実氏の「新事態に直面するベトナム戦争―序にかえて」と題されたはしがきによると、彼がこの企画の構想を練ったのは1964年4月末にサイゴンを訪れた時だったという。彼は当時悪化の一途をたどる戦況の中で、いずれ遠からず米国は戦場を北ベトナムにエスカレート(拡大)するに違いないと考え、「その時機に間に合うように、この企画を実現に移さねばならぬ」と決意したという。大森氏は、南ベトナムの戦況はベトコンが圧倒的に優位にあり、やがて南ベトナムそして米軍を襲うであろう最悪事態を見越しての特派員団の全域調査である、と企画の意図を述べている。
実際にこの企画が実行に移されたのは1964年11月だった。1954年のジュネーブ協定でベトナムは北緯17度線で南北に分断され、1960年には南ベトナム解放民族戦線が成立し、南ベトナムでくすぶっていた反政府活動は内戦へと移行し始めていた。
大森氏の予測通り、アメリカが北ベトナムへの爆撃(北爆)を開始したのはベトコン(南ベトナム解放民族戦線)が南ベトナム・プレイクの米空軍基地を攻撃した1965年2月7日のことだった。この時期、南ベトナム駐留の米軍顧問団と称する米軍は2万3000人余りに達し、1965年8月には米軍の地上戦闘介入が決定された。ベトナム戦争は半ばアメリカの戦争と化しつつあった。一方ベトコン側も民兵、地方軍、正規軍の軍隊組織を次第に整備し、初期のテロ活動、ゲリラ戦から機動戦へと戦法を変えつつある時期だった。64年10月にはサイゴン郊外30キロのビエンホア空軍基地がベトコンの襲撃を受け、米空軍のB57爆撃機21機などが破壊され、64年末から翌年1月にかけてのビンシアの戦闘では1500人のベトコンが南ベトナム政府軍2個大隊を全滅させている。そして北爆のきっかけとなったプレイク米空軍基地への攻撃である。
本書のタイトルに「泥と炎」とあるが、「泥」はベトナム民族の底辺、「炎」はベトナム戦争の現場のことだと大森氏は説明している。取材は外信部副部長の小西健吉記者を団長格に6名以上の記者が担当した。この企画を編集会議で検討した時には、多くの編集幹部が記者の生命の危険と3ヶ月の時間を伴うこの企画に反対した、と大森氏は述懐している。
本書は13本のリポートから成る「燃えるベトナム」、15本のリポートから成る「南ベトナムの底辺」、5本のリポートから成る「揺らぐラオス、カンボジア」、総括に当たる「ベトナムの行方」、それに『17度線の北』など共産圏側から見た異色のルポで知られるオーストラリア人ジャーナリストのW.G.バーチェット氏の寄稿「ベトコンの側からみる」の5本の柱で構成されている。大森氏は「序にかえて」の中で、バーチェット氏の報告は、われわれがやろうとしてどうしても果たしえなかった地域を、彼の特異な筆の力を借りて補足したものだと述べている。
このコラムでは「燃えるベトナム」と「南ベトナムの底辺」にしぼって紹介する。
記者たちのリポートは、上記のように項目が多くそれぞれがまたいくつかの短い話題で構成されている。それらのリポートで共通しているのは、「泥」と「炎」のいずれの面でも絶望的な南ベトナムの情況である。それぞれの短いリポートを各個に紹介するのは難しいので、断片的にはなるがリポートの中で私の目を惹いた特徴的な場面や談話などを拾い概略紹介することにする。
なおリポートの中の細かな地名、人名などは省いている。
「燃えるベトナム」の最初のリポートは「南ベトナムの戦闘」で、石塚俊二郎記者の取材だ。石塚記者は赤い海といわれ、ベトコンが圧倒的に支配するメコンデルタでどうにか持ちこたえている村の一つ、タンジン村への緊急補給作戦に同行した。三個分隊ほどの兵員が三隻の舟艇に分乗し、約30キロ下流の村に向かった。セメント、弾薬、食料を届け、あわせてトーチカの強化、稲作指導、肥料小屋の設営などを行うのが任務だ。
単調な船旅に昼寝を決め込んでいた石塚記者は「ダーン……」という音に目を覚ました。2隻の内火艇が川岸へ突進して行く。「ベトコンのスナイパー(狙撃兵)だ」と米軍顧問のキング大尉がつぶやいた。水中にまで生い茂ったマングローブの林の中につっこんだ舟艇はやがて一人の男を捕らえ引き返してきた。
捕らえられた男は米特殊部隊発行の偽の証明書を持ち、CIAの密偵だと言い張った。紳士的に扱われて安心、観念したのか、彼は自供を始めた。紛れもないベトコンで、反政府活動で6ヶ月投獄されたことがあるとも話した。彼は「仲間の分隊の居場所を教えるから命だけは助けほしい」と言いだし、差し出されたメコン流域の拡大地図に×印をつけた。これをもとに政府軍の兵士らはベトコン部隊を急襲、戦闘は40分ほどで終わり、捕虜一人、弾薬、書類多数を捕獲した。ベトコンは負傷者や死者をかかえて水田の奧の茂みに逃げ去った。この間4人いた米軍顧問は一言も発せず、ライフルや短銃を握りしめているだけだった。石塚記者のリポートは、最初の捕虜はユダとなり、今頃は銃口の前で25年の生涯を閉じているかもしれないと結ばれている。
次は密林で部隊にはぐれ、命を落としかねなかった「荒わし作戦」の取材記だ。石塚記者はある日、ラオス国境から東へ20キロの地点で、南ベトナム正規軍2個大隊と戦闘中のベトコンの正規1個大隊の背後に政府軍を降下させ、ベトコンを挟撃しようという「荒わし作戦」の取材に挑戦した。傾斜が急で、竹藪が深く、ヘリコプターは着地できないため、ヘリコにすしづめに乗っていた南ベトナム政府軍の兵士は、地上5メートルに静止したヘリコから次々に跳び下りる。50キロそこそこの体に30キロの背嚢やナベ、カマを背負ってである。石塚記者も飛び下りたが足を少しねじったようだった。兵士は身軽にササをわけ、竹藪に吸い込まれていった。
飛び降りた兵士やヘリコを見ていて気がつくと、あたりには人影が消えていた。ササをかき分けながら20分も歩いたろうか、完全に部隊を見失った。1メートル先が全く見えない竹やぶ。あとで聞いた話しとして石塚記者は、部隊からはぐれた者は、ベトコンかトラのえじきになって永久に密林に消えてしまうのだと書いている。まさに命の危機に直面していたのだ。行けるところまで行くほかはないと、地雷を避けるため、しっかり生えたササの根元をえらんで歩く。時計を見ると引き上げ予定時刻まであと10分しかない。
その時何かしら人声らしい声が聞こえ、と同時に第二波らしいヘリコの複数の爆音が遠くに聞こえ始めた。クマザサに傷だらけになりながらやみくもに進むと荒わし部隊の赤いネッカチーフ、そして緑のユニホームが目に飛びこんできた。ころぶように竹やぶを突進し、飛び下りてくる第二陣の兵士がとつきあたりながらヘリコの脚にしがみついてよじのぼった。射手が機銃を片手に引き上げてくれた。ねんざした脚が急に痛み出した。
戦線取材はまさに命がけというリポートである。
小西健吉記者のベトコン遭遇記
1964年12月19日、午後3時半かっきり。サイゴンから118キロの路上。ギーとブレーキの激しい音がして車が急にスピードを落とした。三人の兵士が小銃をかまえ、道ばたの一人が手を上下に振って「止まれ」と合図をしている。それを見たとたんなぜか表現できない悪寒のようなものがおおいかぶさってくる感じがした。職業意識から思わずカメラを構えると、横にいた同行のK氏が、「とらないで」と小さいが力のこもった声で叱るようにいいながらカメラを押し下げた。車から降ろされ、銃口をつきつけられ、本能的に両手をあげた。
兵士は素早く小西記者の首からカメラをはずし、武器を所有していないかどうか入念にチェックした。一人の兵士はベトナム人がよく着る黒いシャツとズボン、素足に黒いホー・チ・ミン・サンダル(主に米軍車両の厚いゴムの廃タイヤを材料にして作られたサンダル。ベトコンのトレードマーク)を履いている。このサンダルに小西記者ははじめてベトコンにおそわれたのだとはっきりわかった。
じつはそれまでは半信半疑だったのだ。なぜなら小西記者の車をとめた三人の兵士は南ベトナム政府軍と同じ濃い軍服を着ていたし、なかの一人は政府軍と同じ緑色の鉄帽までかぶっていたからだ。
小西記者は「落ち着け、落ち着け、ベトコンと遭遇したいとさえ思ってきたのではないか」と心の中で繰り返したが、胸の鼓動がこめかみまでつきあげてくるのを止めようもなかった。
いつの間にか7人のベトコンに囲まれていた。K氏の通訳で尋問がつづいた。ベトナムに来てどれくらいになるか、目的はなにか、新聞社はベトナムの政府と関係があるのか、日本で給料はどれくらいか、このカメラは会社のものか……。財布から米ドルを引き出し、「この金はここでは通用しない」という。指揮官が「われわれはベトナム革命軍だ、グエン・カーン(南ベトナム3軍総司令官)の部下ではない」といい、「この三台のカメラのうち一台を明日まで預かる。われわれは盗賊ではないから明後日正午ここへくれば必ず返す。そしてわれわれの上級指揮官があなたがたと話すだろう」といった。彼らと話しをしたかったが、K氏からきびしく制止された。
40分間の尋問だった。小西記者は笑いながら指揮官と肩を抱き合い握手をして別れた。小西記者が後日カメラを取りに現場に戻ったかどうかの記述はない。
語録
ここで「燃えるベトナム」のリポートの中に出てくるさまざまな声を紹介する。
- ベトコンの捕虜を捕らえた南ベトナム政府軍将校:「ベトコンも同胞だ。一度で殺すわけにはいかない。しかし二度以上は敵だ」
- 南ベトナム出身で政府軍に寝返った35歳の元北ベトナム軍大尉:「前から考えていたことです。ゴ・ジン・ジェムさえいなければ南ベトナムはいい国です。この戦争は共産主義と帝国主義の戦いです。私は帝国主義はごめんだ、だが共産主義とつきあうのもくたびれた。南ベトナムの政府も人民もかわいそうです。私もこの年まで独身、ガール・フレンドもいません」
- 米軍特殊部隊の大尉:「ホー・チ・ミン・ルートというのは誤解を招きますね。ルートといったものはありません。山道のネット・ワークが実情です。われわれはトレイル(小道)と呼びます。実際にベトコンに補給が行われているかって……?疑う余地はありません。われわれにとってそれを妨害するのが主な仕事なのですから……」
- 石塚記者のメモから:最近押収されたベトコンの農民に対する宣伝文と政府軍側のリーフレットを比較したところ、互いの10項目の公約のうち、違うのは2項目しかなかった。それはサイゴン政府打倒と米人追放だった。つまり農地解放からかんがい工事、小学校の建設まで全く同じことを呼びかけていた。それは、メコンデルタの農民がいったい何を欲しているのかを双方が必死に追いかけた結果であり、偶然でも何でもない。
- ある省で、米国の農業指導員が水田の中でむかっ腹を立てているのを見て、ベトナムの青年が小声のフランス語で:「あれだからね、戦争に勝つはずがないよ。ここは場所違いだ」
- あるベトナム人の郡長:「恐らくいまデルタの農民は20%が政府側、30%がベトコン側、あとの50%は、多少の濃淡があっても生活がよくなればどちらでもいいのじゃないですか。これは手前ミソすぎるかもしれないけれど」
- 米援助軍司令部心理作戦部長・ボーエン大佐:「米国は心理戦争できわめて不利な立場にある。ベトコンはわれわれ外国人、しかも白人を追い出そうとよびかける。ベトナムの歴史は恰好な教材だ。今までの南ベトナム政府と地方官吏の腐敗、それに貧富の差はますますベトコンを有利にさせた。民主主義も自由も遠い先の説教だ」
- 一米軍大尉:「ベトコンはどこにもいない。そしてどこにでもいる」
- ベトコンの1小隊を袋のネズミにした政府軍の隊長が、部下に深追いをやめさせ、ベトコンを逃した後でのある政府軍兵士の感想:「僕には隊長の気持ちがよくわかる。僕らは戦うために兵隊になった。だから戦闘に勝つこと、一人でも多くのベトコンを殺すことが僕の任務だと思う。だけどね、大部分の南ベトナム兵は、軍隊とはつまり生活の道なんだ。アメリカ兵は1年たったら故郷へ帰れる。僕らはそのあとでも、いつまでも戦い続けなけりゃならないんだ。あすに生きのびても、2年後まで棺おけに入らないですむかどうか。月給をもらって家族を養って、死ぬまで戦いつづける。なるべく生きていたいし、隊長が部下を生かしておきたいと思ってもおかしくないだろう」
- 米軍の1中尉:「われわれは一体だれに頼まれて生死をかけにここに来ているのだろうか。デモはアメ公帰れ、だ。政府軍まで帝国主義反対とくる。道を通れば寄ってくるのは子供とポン引きだけた。だれにたのまれて僕はいるのか」
- ある米軍軍曹:「われわれがベトコンの十字砲火の中に立っているとき、サイゴンでは果てしない権力の奪い合いが続いている。苦楽をともにしているベトナム兵はつかれ果てている」
- 若い米軍中尉:「ベトナムの米国人は米国のためにここにいるのです。だれが他国のために死んでゆくでしょうか。恐らくベトナムが共産化したら、米国にいる私の家族や友人たちが苦しむ日がくるから、私はベトナムを志願したのです。そう考えなければ自分の命をかけるわけにはいかない」
「南ベトナムの底辺」では南ベトナムの農民(地主を含む)、漁民、北からの難民などの苦しい生活を政府の施策、具体的な数字、それに生活の実態などを数字をあげながら繰り返しリポートしている。ここでは北ベトナムからの難民、北部ダナンからドンハへの危険な鈍行列車の旅の二つのリポートにしぼって紹介したい。
「北からの難民」 1964年10月31日深夜、ベトコンの奇襲で米軍のB57爆撃機21機が一夜のうちに撃破されたことで有名になったビエンホア空軍基地から約5キロにあるタンヒエップ村には、北ベトナムからの難民約3000人が住んでいる。もとはジャングルだった荒れ地を切り開いて作られた村だ。小西健吉記者がこの村を訪ねた。
粗末なかやぶきの貧しい家の間にやたらと教会だけが目立つ。1954年のジュネーブ協定後、北ベトナムのカトリック教徒90万人は信仰の自由が保障されている南ベトナムに移住したのだ。
小西記者は誘われてパックさんの家を訪ねた。彼の家は粗末だがまわりの家よりましな方だ。彼には妻との間に8歳の娘、5歳の息子、生後1年あまりの女の子がいた。家の中を見回すと、むしろをしいただけのベッドが二つ、粗末なテーブルが一つに椅子が四つ、ホヤのないランプが一つ。壁にはマリアとキリストの色刷りの額が二つかかっていた。パンクして使えない自転車と壊れた目覚まし時計が一つ。かやのつり手のひもに着物もはだ着も一緒に20枚くらいがぶらさがっていた。おそらくこれが彼の全財産のようだった。農具はないのかと聞けば、質の悪い鉄で作られたクワの頭とスキが一つ、それに半分こわれかけたシャベルが一つ、農具はそれだけで収穫は手でするという。
パックさんは北ベトナムの首都ハノイの近郊で農夫をしていたが、55年に南ベトナムにやってきた。24歳だった。彼はてっとり早い道を選んで4年間兵隊に入り、必死なって金をため、この地に妻と二人で家を建てた。パックさんはここで野菜作りを始め、それを妻がビエンホアまで売りに行く。しかし、米、肉、魚などの食費、小学校へ行っている娘の授業料、カトリックの幼稚園へ通う長男の費用など出費が多く、毎年正月前に一人に1枚着物を買ってやるのが精一杯だという。
話しをしているうちに雨が降ってきた。たちまち雨漏りが始まり、ハンモックに寝かしてあった末娘の上に母親が菅笠を二つのせてやった。
政府は何もしてくれないのかと問うと、パックさんは「家も土地もおれが買った。お役人のしてくれたのはこれだけだ」といい、ベッドのかやの上から紙切れを一枚出した。彼の身分証明書だった。
小西記者はもっと難民のことを知りたいと、難民と一夜をともにする決意をし、サイゴン近郊コンタンの難民センターを訪れた。センターの正門をはいったところにマリア像が建てられていた。政府の建てた彼らの住居は、アンペラ張りの粗末なもので、まさにスラムそのものだった。ここには約200家族、千人の難民が住みついている。小西記者の宿の主はグエン・バンビーさん。彼の家は通りに面した12畳くらいの土間と6畳くらいの二間長屋だが、隣の家との壁は上半分が落ちていた。バンビーさんは妻との間に5人の子供をかかえ、57歳の母親との8人ぐらしだ。ベッドは井戸のわきに屋根だけふいた吹きさらしの場所にある一つを含め全部で四つだ。小西記者が寝るはずのベッドに腰掛け、リュックサックを置くと、その下で「ワーン」と蚊がなき、サンダルをはいた足がたちまちかゆくなった。汚水が流れ異様な臭気のする細い道に足を踏み入れたとたんに、正直「えらいことになった」と後悔していた。
バンビーさんは55年にサイゴンにきた。故郷では農夫だったが、軍隊にいたころ覚えた自動車の運転技術をいかし、今はサイゴンで政府の運転手をしている。わずかばかりだがたくわえもできるといった。
北ベトナムの故郷では1ヘクタールの土地を持ち、食うことの心配はなかった、サイゴンでの生活は故郷の生活よりつらく苦しいという。それでも北の生活を棄てて南に来たことはよかったという。北ベトナムの親類が検閲の目をくぐって書いてくる手紙で、住民が強制移住させられ、教会へ行くといっては政府からいやがらせをされていることを知れば、日曜ごとに気兼ねなく教会へ行けるこちらの方がましだと思うのだ。
小西記者は帰り道、ビエンホア=サイゴン間を結ぶすばらしい軍用道路を走りながら、国府(台湾)の農業技術指導員の徐さんが「道路ばかり、分にすぎてよすぎる」といったのを思い出した。南ベトナム政府の金の使い方は、わたしにはどうにも納得できない、小西記者のしめの言葉だ。
最後に南北ベトナム境界線まで危険な汽車の旅をした山本潔記者のリポートを紹介する。
昔はサイゴン中央駅から南シナ海に沿い快適な鉄道の旅が楽しめたそうだが、1954年のジュネーブ協定以後は北緯17度線で分断されたままだ。朝鮮半島の南北を結ぶ鉄道が朝鮮戦争の結果北緯38度線で途切れているのと軌を一にしている。しかもベトコンの激しい攻撃で、この時点ではサイゴンから中部のニャチャンまでと北部のダナンから国境に近いドンハまで以外は運行されていなかった。南ベトナム鉄道当局によれば63年1年間でこの線に対するベトコンの地雷攻撃は103回に達し、旅客、鉄道員合計308人が死傷しているという。
山本記者は何度もサイゴンからの乗車をトライしたが、外国人は乗せないと拒否され、北部のダナンからの列車に乗ることにしたという。列車はダナン発午前6時20分の一番列車、乗車前駅長から、「米国の鉄道施設を破壊するのがわれわれの目標だというベトコンからの果たし状が、これまで何十回となく爆破現場から発見されている。乗車を止めはしないが、私のいうことを聞け。もし、ベトコンが発砲してきたら、絶対に車外に飛び出してはならない。列車が地雷を踏んだら、できるだけ堅い物にしがみついていることですね」と注意された。
途中の情景描写や車内の様子は省き……さし向かいの客は50がらみの農婦とその息子らしい24、5歳の青年だった。青年がフランス語を話すことがわかり、山本記者は率直に自分の仕事の目的を話し、青年の答えを期待した。青年は、青年の家は南ベトナムのありふれた家庭だったが、戦火の犠牲者であることに変わりはないこと、姉と長男の彼の下にまだ5人の弟妹がおり、1ヘクタールほどの田があるが、生活は苦しいことなどを話し、更に急に声を落とすと次のような打ち明け話をした。
「わたしの23歳の弟は、実は約1年前から解放戦線(ベトコン)に投じているのです。豪雨があった2ヶ月前のある晩、ふと目をさますと、台所で母が若い二人の兵士に夜食をふるまっていました。その一人はまぎれもなく1年も姿を見せなかった弟でした。母も兵士もことばはまじえず、片方が黙々として飯を差し出し、片方は食べていました。やがて兵士たちはまた雨のヤミに消えていきました。」フランス語の分からない母親は、ただ黙然としていた。青年はこう付け加えた、「わたしも、村ではベトコンと戦う民兵の一人です。だが兄弟で殺し合えというのですか……」。
この危険な鈍行列車──それはまるでこの国のシンボルのようだ。
山本記者の乗ったその列車が、ベトコンの地雷で吹き飛んだのはそれから三日後のことだった。
これで「ベトナムの底辺」のリポート紹介は終える。最初に書いたように『泥と炎のインドシナ』は更に「揺らぐラオス、カンボジア」、「ベトナムのゆくえ」、「ベトコン側からみる-W・バーチエット」と続くが、それらは割愛する。
私の断片的なリポートの紹介からも当時の南ベトナム政府側、米軍側の絶望的な状況が見て取れると思う。実際にパリで和平協定が調印され、米軍が南ベトナムから撤退、南北ベトナムが統一されたのは、毎日新聞の取材団派遣からほぼ9年後の1973年7月のことだった。
大森氏は、本書を日本人ジャーナリストの目でインドシナ情勢をとことん見極めようとしたもので、できるだけのことはやれたとしている。
しかし、ベトコンや北ベトナムに対する直接取材はこの時点ではかなえられていなかった。大森氏はそれから間もなく、1965年9月、西側記者として初めて北ベトナム入りを果たし、「ハノイ報告」を毎日新聞に連載した。この「ハノイ報告」がいわゆるライシャワー事件へとつながり、大森氏は毎日新聞社を退社することになる。
その経緯は、次回の『石に書く』で……。