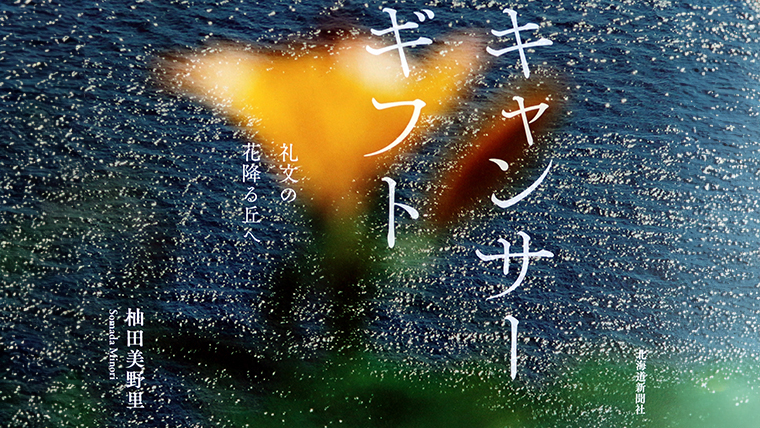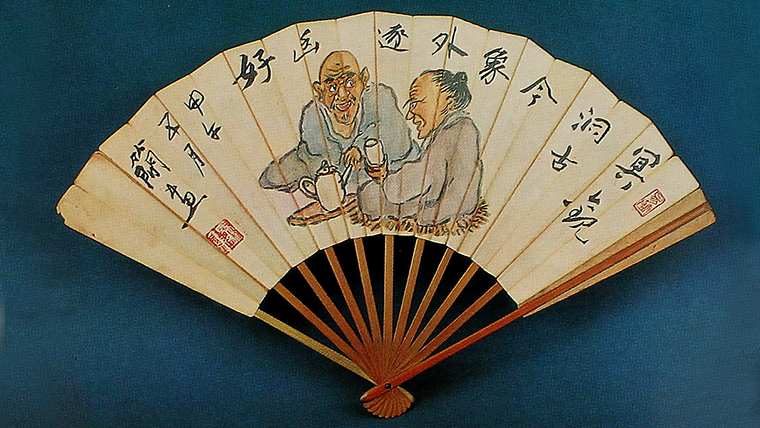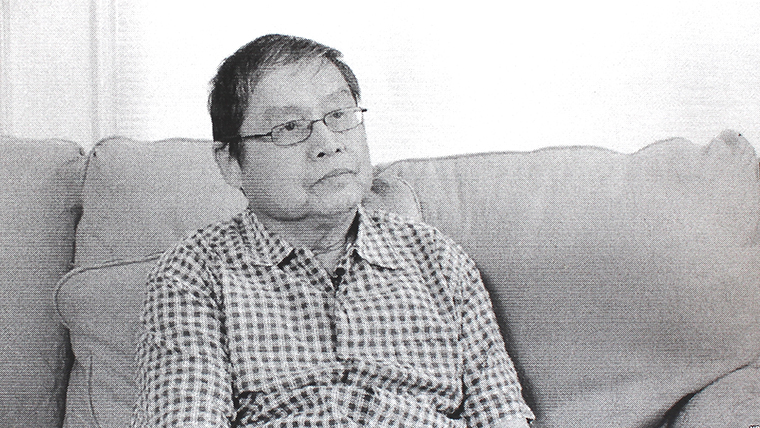書名:暁を見ずに
著者:ステヴァン・ハヴェリャーナ
訳者:阪谷芳直
版元:井村文化事業社
発行:1976年
原著は第二次世界大戦の終結間もない1947年に、米国ボストンの出版社から刊行されたフィリピン人作家ステヴァン・ハヴェリャーナ(Stevan Javellana)の英文の小説『Without Seeing The Dawn』。占領日本軍に蹂躙されたフィリピンの農民の苦難と悲しみ、そして怒りに満ちた物語だ。日本人にとって、自身の大戦中の東南アジアにおける加害行為を振り返る上での重要な一書と言えよう。
井村文化事業社は1976年~1980年にかけて12冊のフィリピン双書を発行した。筆者の手元には双書のうち第一期に発行された3冊があり、本書はその2冊目にあたる。ほかの2冊はフィリピン独立運動の指導者ホセ・リサールの著作だ。
本書の巻頭には、そのホセ・リサールの「私は、わが故国の上に輝き出づる暁を見ずに、死ぬ。暁を見ることの出来る諸君よ、君たちはそれを歓び迎えよ。そして、夜の間に斃れた人びとのことを、決して忘れるな!」という言葉が掲げられている。
本書の書名がこのホセ・リサールの言葉から取られたことは明らかだ。
本書の舞台は、フィリピンの首都マニラがあるルソン島の南に位置するパナイ島の中心都市イロイロ市に近いサンタ・バーバラの農村マンハーヤン。著者ハヴェリャーナはイロイロ市の出身で、彼自身、パナイ島の抗日ゲリラ部隊に加わり、日本の降伏まで抵抗運動に従事したという経歴を持つ。それだけに本書には、著者の農民に対する深い共感が込められている。
日本軍がフィリピンに侵攻したのは1941年12月中旬で、パナイ島に上陸したのは翌1942年4月のことだった。
小説はこの時期、マンハーヤンとそこに住む農民が見舞われた災厄を詳細に描写している。ドキュメンタリーかと思えるような内容だ。
本書は二段組みで310ページあまりの大部なもので、「第一部 昼」と「第二部 夜」の二部から成っている。「第一部 昼」では戦争前の素朴でのどかな農村生活と農民の哀歓が語られ、「第二部 夜」では日本軍に蹂躙され、荒廃して行く農村と悲惨な運命に弄ばれる農民の姿が活写される。この小説に登場する農民はすべて小作人で、彼らを支配する地主の横暴も小説の一要素として語られている。
物語の主人公は村の娘たちがみな秘かに恋する逞しく働き者の青年カルディンとその妻となる美しい娘ルーシンである。
それでは第一部からごく簡単に物語の筋を追って行くことにする。
なおコラムの小見出しは筆者がコラムの内容によりつけたもので、小説の中の見出しとは関係がない。
第一部 昼
結婚
物語は18歳のカルディンと16歳のルーシンの結婚で幕を開ける。カルディンは結婚を前にして5月に家を建てるのだが、迷信深い村の年上の連中からは、5月に家を建てるというカルディンの決定は特別不吉なことと考えられた。彼らは「5月に家を建てることは、その家の持ち主に不幸を負わせることになる。災難はその踵を追っかけ、そして彼は悲惨のコップから腹一ぱい飲むことになる」と言うのだった。物語の不幸な展開を予測させる言葉だ。
村の若者たちは何時もいっしょに川で游いだり、騒いだり楽しく過ごしているのだが、そんな中でも戦争の噂が広まるようになって来る。一人の若者は、こうした語らいの場で、唾を吐き軽蔑したように、戦争なんか俺たちの海岸まで来るものかと言うのだが、この予言はやがて外れることになる。
カルディンとルーシンは幸せな結婚生活を送り始めるが、待ち望んだ最初の子供は死産だった。その後、ルーシンは客人として現れた地主の息子の誘惑に危うく負けそうになり、カルディンとの間に亀裂が生じる。カルディンが地主の息子をひどく殴打したことで、カルディン親子は小作地を取り上げられ、カルディンの家も壊された。
カルディン夫婦は生活の糧を求めて島の中心都市イロイロに出て行くが、ここではカルディンが町の夜の女ローシンと浮気をし、傷心のルーシンは一人村に戻る。
しばらくしてローシンとの関係を断ち切って村に帰ったカルディンは、有力議員から村の北の地方にある小作地を与えられ、夫婦で新天地を求めて移住を決める。
そこでは、夫婦の間に待望の男の子が生まれた。カルディンは土地の者から、あのサンタ・バーバラから来た新しい小作人を見ろ。あれじゃ、そのうちに、水牛を使い殺しちゃうぞ。だが、あれは金持ちになるだろうよ。
と言われるほどよく働き、作物は順調に育ち、新生活は順調に進むかに見えた。
しかし、ここでも地主の都合で収穫後には小作地を取り上げられることになった。著者はその時のカルディンの心境を次のように描写している。
都会で仕事をするのを断念することも、そう辛くはなかった。なるほど、金は容易に手に入って来るのだが、何も自分を仕事に結びつけるものはなかったからだ。野良仕事は違う。そこでは、自分と土地との間に絆がある。ほんの短い間ではあったが自分のものであった。起伏している丘と真っ黒い田畑を振り返って見る時、彼の胸は痛んだ。
更に不運が見舞った。山の上のダムが山崩れの影響で決壊し、洪水となってカルディンらの村を襲ったのだ。収穫前の田畑はすべて泥土に埋まり、無に帰した。
カルディン戦場へ
ふるさとマンハーヤンに戻ると、そこには日米戦争の噂が流れていた。カルディンは、不運がこれまで何時も忠実な影のようにつきまとってきたが、戦争はひょっとして自分に幸運をもたらしはしまいか、と思う。
カルディンは兵士の募集に応じ、従兄弟の一人と共に戦場に赴くことにした。カルディンの父のホアンは言う。
背が高く、若々しく、素晴らしい若者たちは、朝陽を浴びて、顔にのんきな微笑を浮かべて戦いに出て行くだろう。全部は帰って来ないだろう。彼らのうち非常に多数の者が、立ち、戦い、そして倒れたその場所にうち捨てられ、その大きな死体は暑い太陽のもとで腐りただれ……。
ルーシンは「止めて!止めて!」と苦悩に顔を歪めて叫んだ。
第二部 夜
ゲリラへの参加を拒否するカルディン
カルディンはバタアン死の行進で知られるルソン島バタアン半島での日本軍との戦いに参加し、九死に一生を得て村に戻った。共に戦場に行った従兄弟のイスコは戦死した。
妻のルーシンはカルディンに子供は悪寒で死に、カルディンの父親は赤痢で死んだと告げるのだった。ルーシンは妊娠していた。
カルディンと親しかった村の若者の多くは地下にもぐり、ジャップ(日本軍)がインディアンと呼ぶ抗日の組織を作り、抗日のゲリラ部隊の到着を待っていた。
岳父のポール村長がカルディンに「ゲリラ部隊の募集の話しがあるのだが」と水を向けると、カルディンはこう答えた。
お父さん、あなたはこれが何を意味するのか分からないんですか?いいですか、われわれの取るに足らぬ弱い力を、日本帝国の部隊の強力な実力と取組ませようというんですよ。その結果を甘受する覚悟がありますか?あなた方が払う代償は、村は焼かれて略奪され、女は強姦されるということなんだ。あいつ等は山で、われわれはちっぽけなねずみみたいなもんさ。俺には何時成功の望みが絶たれるか分かっているんだ。俺は、休息のために、もう戦いはすまいと、家に戻って来た。俺は俺のやるべき戦闘の義務はもう果たしたよ。断じて!私は決して2度と銃には手をふれません。
このやり取りを聞いていたルーシンは、私たちは、あなたがそんな風に考えようとは思わなかった、私たちは、あなたがきっとゲリラに加わるだろうと思い込んでいたのにと落胆するのだった。
ゴンドイの予言
インディアンに加わっているカルディンの最も親しい従兄弟のゴンドイも日本軍がパナイ島に侵攻してきた時の侵入者の残酷さをカルディンに語り、彼にインディアンの仲間に加わることを勧めた。
もしお前が兵士であったら、そして、帰って来て、兄弟や親は日本軍に射殺され、女房や姉妹は強姦され、子供らは銃剣や軍刀で突き刺されたと知ったら、それだけで再び闘うという大きな理由にならないだろうか―たとえ、その正義の闘いが絶望的だと思われようとも。と言い、インディアンに加わるように説得した。カルディンが、そういうことが自分の身に起こらなかったことを神さまに感謝していると答えると、ゴンドイは目を伏せ、たくさんの他の人間は、お前ほど幸運じゃなかった。だが、カルディン。俺は確信している、何時かお前も俺たちのように感じるだろうということを。恐らく、お前が俺たちの誰よりも残酷に、執念深くなる日が来るだろうよと言った。
ルーシンとゴンドイの言葉の真の意味、深刻な意味をカルディンが知るのはまだ少し先のことになる。
日本軍の襲撃とルーシンの告白
小さな村は、襲来した匪賊を撃退した後、しばらくは平和だった。しかし、ある夜のこと日本兵がやって来た。彼らは抵抗する村人を殺し、少年をインディアンだと言って拷問し、殺害し、若い女性を強姦し、乳房を切り取り、或いは連れ去って売春婦にし、村を火の海にした。ゴンドイの話した情況がそのまま村で起こったのだ。村人の中には村を出るものもあった。その人たちは村には呪いがかっていると感じ、虐殺された人間が暗い夜に焼け跡を徘徊するだろうと怖れたのだ。林の中にある竹やぶの裏に小さな小屋を建て、水を汲んだり畠を耕したりするためにのみ出て来る人たちもいた。
ある夜、ルーシンがカルディンに衝撃的な事実を告白する。カルディンが戦場に出て行くまで、二人はむつみ合っていたから、あなたは私のお腹の中の子が自分の子だと信じているかもしれないが、カルディンが留守の間に私は部落を襲って来た日本兵に強姦され、お腹の子が誰の子かわからない、そして二人の最愛の子とカルディンの父も実際には日本兵に殺された、というのだった。カルディンは何も言わなかった。彼は、地震のような何か恐ろしい破局が起こればいい、大地が割れて自分たちを呑み込んでしまえばいいと願った。実は村では誰でもこの事実を知っており、知らなかったのはカルディンだけだった。
この告白の後、でルーシンはカルディンが死ぬまで決して忘れることのできないだろう言葉を口にしたのだった。
あたしは何時も自分が死ねばいいと思いつづけて来たわ。自殺することも考えたけれど、あたしは卑怯者なのよ。そして、こうお祈りしたの――神さま、どうかお許し下さい――あなたが戻って来てあたしの恥を分担しないでもすむように、敵の弾丸があなたの心臓を貫きますようにって。あなたがバタアンで闘っている最中でさえも。
ルーシンのこの言葉を聞きカルディンは泣いた。彼の家が洪水で流れてしまった時以来、彼が泣いたのは、これが最初だった。
この時、カルディンは、ゴンドイが「君が俺たちの誰よりももっと残酷に、もっと執念深くなる日が恐らく来るよ」といった時、彼が何を言おうとしていたのかを初めて理解した。
カルディンは悪鬼か
そうしたある日、カルディンはおばさんの家に預けてあった銃を取り、ゴンドイに会いに行き、俺にはもう銃が出来た、お前と一緒に行くぞと言った。
抗日ゲリラに加わったカルディンは、ゴンドイの言葉通り、残酷で執念深い行動をとるようになった。村に久しぶりに現れ、日本への帰順を説く洋行帰りのルーシンの叔父を殺害したり、日本軍を待ち伏せ攻撃した際、日本側についていた従兄弟を殺したりした。村人からは、カルディンは悪鬼だ、悪魔に魂を売り渡した、あいつが多くのほかの人間にしでかしたと同じような残酷な死に方をすればよい、とまで言われるまでになった。一方で、ゲリラ部隊の中で彼は急速に頭角を現し、昇進して行く。
ルーシンとの別れ
ルーシンの出産がいよいよとなったある夜、カルディンはゲリラの宿所を離れ、村に帰る。彼の目的は生まれて来る赤児を自らの手で殺害することだった。子供は死産だった。カルディンと顔を合わせたルーシンの眼には激しい憎悪の火が燃えていた。ルーシンは金切り声を上げた。
あんたが殺したのよ。赤ん坊はあたしの子よ。たとえ、それがあんたの子でなくても。……あんたが人殺しをはじめ、みんながあんたはきっと刀で破滅するだろうって言ったその時でさえ、あたしはあんたのためにお祈りしたのよ。あんたがあたしのことを憎みはじめていた時もあんたのために祈ったわ。あんたがあたしの叔父さんを殺し、あんた自身の従兄弟を殺した時、みんなは、あんたは悪魔だといったけど、あたしは、あのひとはそんな悪い人間である筈はないって言ったのよ。
そしてカルディンがルーシンをきちがい女と呼び、子供を殺しはしなかった、死産だったと抗弁したのに対し、ルーシンは、たとえ、それが死んで産まれて来たにしても、あなたは赤ん坊がオギャといったら殺そうと計画していたのだと言いつのり、更に
あたしはあんたを憎むわよ! あんたなんか殺されるがいいわ。ここからいなくなって。そして、もう決して帰って来ないで!
と叫んだ。
ゲリラの宿舎ではカルディンと、日本軍との戦闘で片足を失い、結婚相手に心ならずも別れを告げたゴンドイの二人が黙々と夕食を食べる姿があった。カルディンは死産の子の埋葬にも村に帰らなかった。彼は心の中で、自分を村八分にしている村などに決して戻るまいと誓った。ルーシンとの数々の思い出も、彼女の「ここからいなくなって、もう決して帰って来ないで!」と叫んだ恐ろしい瞬間のギラギラするような凄まじさによって、おぼろげなものになってしまっていた。
カルディンはこの後もイロイロ市にある日本軍の弾薬倉庫の爆破に出かけ、日本軍に逮捕されひどい拷問を受けた。しかし、実際に爆破を実行したのが、カルディンの目的を察知したかつて彼と情を通じたローシンだったことが分かり、カルディンは奇跡的に生還する。
死地に赴くカルディン
その後ゲリラ部隊の少尉になったカルディンは、ボロ(山刀)だけが武器のボロ部隊の指揮官となり、町に駐屯する日本軍の兵営に無謀な自殺行為の襲撃に向かうことになった。
村には日本軍の華僑大虐殺や村々での皆殺しの惨状などがしきりに伝えられた。サンタ・バーバラの町には日本軍から、住民一人残らず日本軍の作った集団部落に入れという命令が届いた。30日の期限が過ぎても集団部落に入らなかった者はすべてゲリラの同調者と見なし、射殺するという。これに対しゲリラ側は、集団部落に入る者はすべて日本軍の同調者と考える、日本軍駐屯地区に含まれていない町や村へ疎開すべきだというのだった。
マンハーヤンの人びとはまだ直接の危険に曝されていない遠く離れた村々へ逃れることになった。
暁を見ずに
しかし、ルーシンは最後の瞬間まで村を離れようとはしなかった。カルディンたちが町を襲撃に出て行く前にもう一度カルディンに会いたかったからだった。ついにボロ部隊が村を通りかかり、カルディンは一人部隊から離れてルーシンのいる竹やぶのわきの小さな小屋にやって来た。ルーシンはちらりと彼を見たが、ニコリともしなかった。カルディンは言った。
俺が君に対してやった悪いことをすべて許してくれ。これが俺の頼むすべてだ。俺のために祈ってくれとは頼まない。君は憎んでいる誰かのために祈ることは出来ないものな。
ルーシンには彼を見上げる勇気がなかった。もしそうしたら、彼の胸にとびつき、か弱い女のように泣くのは確かだと分かっていたからだ。
彼女がものも言えないでいるうちに、カルディンは行ってしまった。
戻って来て!戻って来て!ルーシンの心は狂気のように叫んでいた。そうしたら、あたしはあなたを許すというわ。あたしを許してとあなたに頼むわ。
だがカルディンは振り返って見ることさえしなかった。ルーシンの母のピアおばさんが言った、あの人たちのうち何人が帰ってくるだろうか?
外ではルーシンの弟たちが「戦いに行くフィリピン兵士の歌」を唱いはじめた。
われはフィリピノ、ここにあり。
いざ、戦いに出で征かん。
誰か嘆かん、今にして、
如何なる運命をわれ待つと。
われの運命の、死にあらば、
地上にわれは倒れなん。
誰ぞや、その時涙して、
眠れるわれを抱かんは。
ルーシンは両手で耳をふさぎ、「止めて!止めて!」と叫んだ。
やがて、ルーシンの耳に、彼女の家族が彼女を残し、竹そりに家財を積み、泥濘の中を出発して行く様子が聞こえて来た。
一人残ったルーシンは震える指で聖像の前のローソクに火を点してひざまずき、それから、沢山のお祈りの文句の一節や一句を唱え続けた。
彼女がまだ祈りつづけている時に、最初の銃声が町の方角から聞こえて来た。
物語はここで終わっている。「夜」のまま、「暁を見ずに」。
コラムではカルディン、ルーシン夫婦にしぼって小説の内容を紹介した。確かにこの小説の主人公はカルディン、ルーシン夫婦だが、この長編小説ではそのほかにも、マンハーヤンに住むほとんど全ての農民が日本軍の蹂躙によっていかに悲惨、残酷な境遇に追い詰められていったかが個別にも詳細に語られている。その意味で、マンハーヤンの村と村民全てがこの小説の主人公と言ってもいいかもしれない。
小説では意外にも、日本軍を直接罵ったり攻撃したりする言葉はほとんど書かれていない。それだけに、農民たちの怒りと憎しみの感情に寄せる著者の思いが強く伝わる内容となっている。
筆者は1973年と1974年にパナイ島を訪れる機会があった。
親日のフィリピン人は反日感情が強く何をされるか分からない、イロイロ市の中心部には行くなと忠告してくれた。しかし、実際には何も起こらず、むしろ歓迎さえ受けた。
だがイロイロ市の博物館へ行けば、館内に足を踏み入れたすぐその場から、パナイ島に侵攻した日本軍に関する資料が展示されていた。50年以上前のことで記憶はおぼろだが、たしか軍刀や日本軍の軍装その他武器などが多数陳列されていた。
またある時、筆者を案内してくれた若者は広い草原に筆者を連れて行き、ここは日本軍の飛行場で、この場所には飛行機の滑走路があったと言った。更に近くのくぼ地を指さし、あそこには以前井戸があった、日本軍は殺害したフィリピン人をその井戸に投げ込んだと話した。淡淡とした口調だった。
このように、表面的には何気ない様子を見せていても、この島では日本軍の蛮行が忘れられていないことは明らかだった。
パナイ島には戦争終結まで数百人の日本人が住んでいた。ある時、小高い丘の上にある日本敗戦時の日本人集団自決の場所を訪れる機会があった。同行したフィリピン人たちは非業の死を遂げた日本人のために手を合わせてくれた。島に取り残された日本人孤児、いわゆる残留孤児の何人かにも会った。スラムに住んでいたり、農奴のような生活を送っている人もいた。このように、戦前、現地のフィリピン人たちに交じって暮らしていた一部の日本人も戦争の被害者だったと言えるだろう。それだからと言ってフィィリピン人に対する日本軍の加害が忘れ去られ、許されていいというわけでは勿論ない。