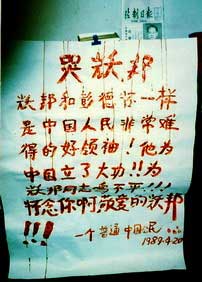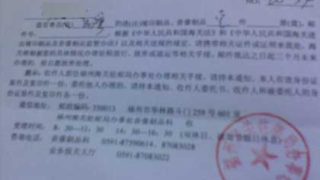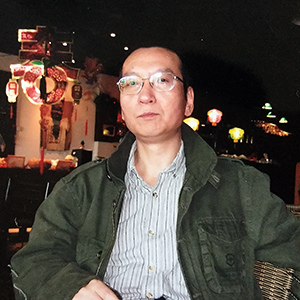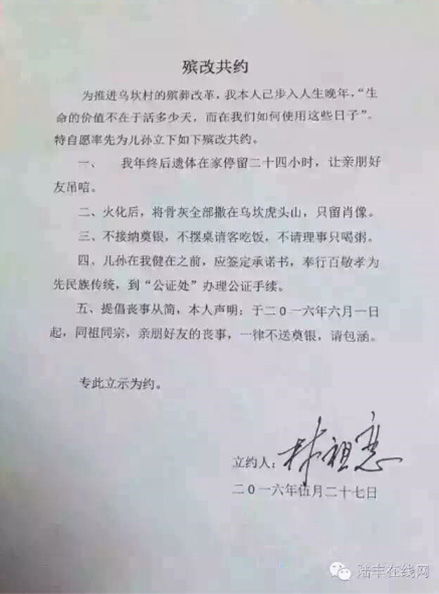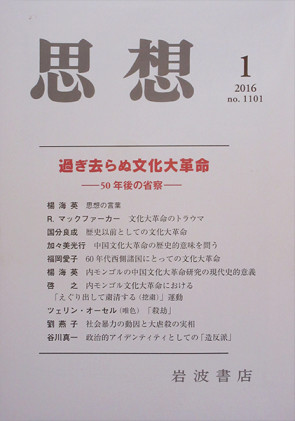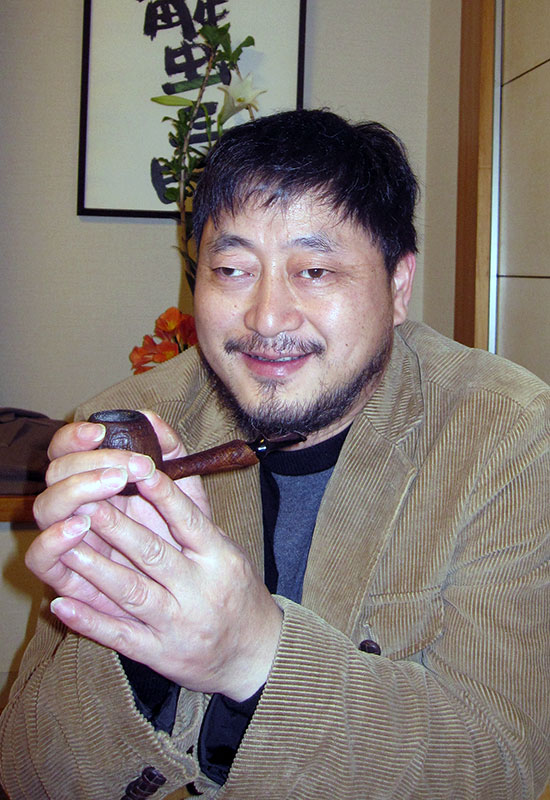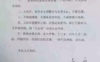1.
北京オリンピック開会式の日、廖亦武の新著『最後的地主・中国冤案録第3巻』(上下、労改基金会、2008年)が私のところに届けられた。
この日、開会式は昼ではなく、夜に行われた。選手よりも、夜の闇と人工的な光の演出が主役のような、機械仕掛けの前夜祭のようであった。他方、この上下2巻、全985頁の『最後的地主』は、生々しい肉声による貴重な証言を綿密に考証した雕心鏤骨(ちょうしんるこつ)の労作であった。 これは「土地改革」というテーマに即して、地主や富農だけでなく、キリスト教の伝道師、風水師、陰陽師、旧体制の保長、長老、国民党遠征軍の通信兵など「階級の敵」と呼ばれた様々な被害者、また、土地改革工作隊の隊長、組長、民兵、貧農とされたごろつき、与太者などの加害者、そして、それぞれの子孫を合わせて、30数名にインタビューし、文学の角度からまとめたオーラル・ヒストリー、ナラティブ・ヒストリーである。それは史実の検証もなされていて貴重な資料となっているが、それだけではない。資料だけであれば広く読まれるのが難しいが、しかし、廖亦武は文学者として読者を引きつける力量を備えている。彼の文学世界の魅力は、その独特の「闇」の位置から、「闇に埋もれた人々の声なき声」を緻密な筆致で描き出すところにある。一言にまとめると、このノンフィクション小説には、まさに資料としての価値だけでなく(廖亦武は後述するヒントンの研究を踏まえている)、廖亦武文学の魅力が凝縮されている。
そして、海外亡命文学者である胡平が「失敗者にも歴史が書ける」、また蘇暁康が「我々は物語を話そう:証言と文献について」という序文を寄稿している。いずれも共産主義の理想という装置が生み出した革命の大義の下でなされた「殺人」を非難し、混乱した苛酷な状況から発せられる呪詛に注目し、他者を殺害する根拠はどこにあるのかと問題を提起している。
2.
中国の土地改革と聞くとき、何を思い浮かべるだろうか? 社会主義の誕生?
少数の地主が集中的に所有していた土地を農民に均等に分配する。だが、ウィリアム・ヒントンの『翻身:ある中国農村の革命の記録』(加藤祐三他訳、平凡社、1972年)はもう記憶から薄れているのだろうか?。その扉では「翻身」について、次のように説明している。
「革命は新しい言葉を創りだす。中国革命も全く新しい言葉を生み出した。一番重要なのは翻身(ファンシェン)である。中国数億の貧農・雇農にとっては、この言葉は、立ちあがること、地主の圧迫をはねのけること、土地や食糧、農具、家屋などを手に入れることを意味していた。それだけではない。迷信を捨て、科学を学び、『文盲』をなくし、読み書きを習い、代わりに選挙による村政府を作る—つまり、新しい世界へ入ることを意味していた。『翻身』と題したのは、このためである。本書は山西省張荘村の農民がどのようにして新しい世界を創りあげたかの叙事詩である」(文中、現代では差別的とされる表現があるが、引用文であり、また文脈から決して差別を肯定するものではないことが明らかなためそのまま引用する)
しかし、このすばらしき世界を謳歌する叙事詩でも、「激情と大義」、「階級と革命」、「暴力と権力の濫用」が合体すれば、人はいくらでも他者(地主だけでなく聖職者や地主とされる者)を殺害できた状況が述べられている。しかも、その方法は野蛮で、混乱した時代でねじ曲げられた人間性がもたらした残酷な「悪」の極みであった。そして、殺された死体は、昔も今も、やはり死体である。死者は声を発することができず、歴史の闇に葬られてきた。
3.
言語の能力は人類の平等と深く関わる。言語学者のチョムスキーがこの問題に迫っているのと同様に、廖亦武は別の角度からこの問題に取り組んでいる。しかし、廖亦武はチョムスキーのように国際的に著名な学者ではなく、パスポートの申請すらできず、国内で亡命同様の流浪を強いられている。その廖亦武が、中国大陸西南の雲南省、貴州省、四川省の僻地を巡り、漢族だけでなく、イ族、ミャオ族、リス族、アニ族、ナシ族などの少数民族を含め、「土地改革」の被害者、加害者、それぞれの子孫の証言を収集し、検証し、オーラル・ヒストリーをまとめた。そこで彼は生存者の証言を通して死者の人生の明暗が生き生きと具体的に細部に渡って述べるだけでなく、それが時とともに風化していく過程も細やかに考察し、その上で、何故人は他者を殺すのかを解明しようとしている。このようにして、死者に言語能力が与えられる。そして、より多面的に歴史を理解できるようになる。
4.
近年、中国の研究者によると、「土地改革」の犠牲者は200〜300万であるという。膨大な血にまみれた数字である。この時期、台湾の蒋介石政権、朝鮮戦争の勃発、チベット進軍(「平和解放」)など、複雑な国際・国内情勢により、中共政権は国内の階級の敵が国外の敵と呼応することを恐れ、「革命は暴動であり、一つの階級が他の階級をうちたおす激烈な行動である」(毛沢東「湖南省農民運動の視察報告」(1927年3月)『毛沢東選集』第1巻、中国共産党中央委員会毛沢東選集出版委員会、外文出版社(北京)1968年、26頁)と対応して、性急な暴力的手段に訴えた。「翻身」の側面だけでなく、この「闇」の側面も踏まえ、多角的に「土地改革」について研究する必要がある。そして、学者の葉匡政は「土改学(土地改革学)」を提唱している。
この点で、廖亦武は文献資料による歴史をより多面的に考察する口述資料を提供したと言える。
5.
著書の行間から、もう一つのきらりと輝くメッセージが読みとれる。廖亦武の友人で、キリスト者の行脚医(『中国低層訪談録:インタビューどん底の世界』でも登場)の孫氏が、この書の鍵となる人物である。孫医師の案内を通して、雲南省の少数民族が暮らしている山村にキリスト教が静かに息づいていることが分かる。いわば「隠れキリシタン」として信仰を守り続けた貧しい村人たちにとって、キリスト教は心のより所であり続けている。これにより、苦難に満ちた一つの時代を乗り越えられたと言える。
6.
廖亦武の独特の文体に対して、瑣末主義で、文学的な潤いがないという批判がある。しかし、文学とは、文学性とは一体何であろうか? この点について抽象的な一般論をいつまで続けていても益はない。そのような議論などに拘らず、半世紀以上経て生存者の証言を掬いあげ、闇に隠され続けた歴史をオーラル・ヒストリーとして復活させることこそ、文学者の重要な責務ではないだろうか? 文学エリート、学者エリート、芸術エリートなどが歴史の真実から目を背け日々荒んでいく世情に対して何ら批判せず、唯々諾々とその流れに身を任せ、あるいは恥知らずに迎合するのは、まさに文学の崩壊と言わなければならない。
確かに、廖亦武は世の流れに逆らい、とても不器用である。一見して負け戦をしているようにも感じる。しかし、彼の文学はしっかりと歴史に屹立している。