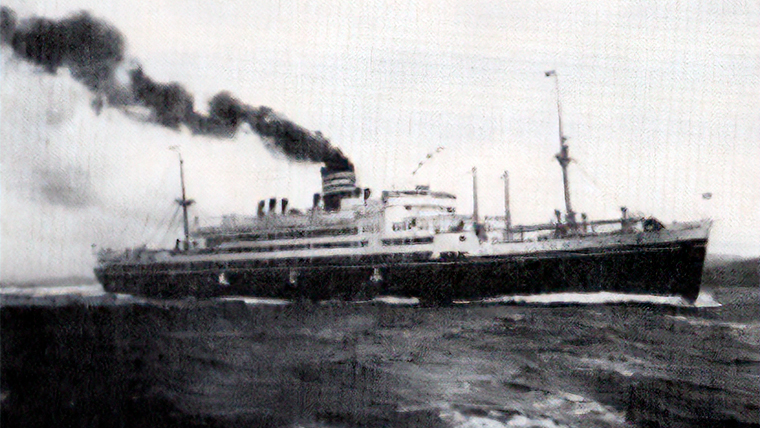阿里山・達邦で警察官兼蕃童教育所の教師を務めながら、青年団の指導者として活躍していた矢多一生は1940年(昭和15)11月、高砂族代表の一人として天皇・皇后が出席した内閣主催の「紀元二千六百年式典」に派遣された。この式典は日本の軍国主義への歩みを象徴する出来事であり、駐日米大使ジョセフ・グルーは式典に参列したが、国際社会は警戒のまなざしで見つめていた。
1937年(昭和12)7月、北京郊外で起きた盧溝橋事件をきっかけに、日本は中国国民党軍との本格的な戦いに入った。軍部の横暴な力は日に日に増大し、国家総動員体制へと突き進んで行くことになる。
当時、国民の暮らしはどう統制され、植民地・台湾の先住民、さらには台湾人(本島人)がなぜ戦争に駆り出されて行ったのか。それを知る手がかりとして、再び文豪・永井荷風に登場してもらおう。明治から昭和にかけて活躍し、後に文化勲章を受章した永井は、毎日のように銀座・浅草界隈や私娼街・玉の井などに出歩き、オペラ歌手、女優、カフェーの女給、娼妓などとの出会いや市井の出来事を赤裸々に記して、当時の世情を庶民の目線で活写しているからだ。
盧溝橋事件が起きた7月、日記17日の条には「街頭には男女の学生白布を持ち行人に請ふて赤糸にて日の丸を縫はしむ。燕京(北京の雅名)出征軍に贈るなりといふ。いづこの国の風習を学ぶにや滑稽といふべし」との記述があるが、戦時色というほどでもない。10月27日の条には「燈刻夕餉を喫せむとて銀座に往くに上海戦勝祝賀の提灯行列あり・喧噪甚しきを以て地下鉄道にて雷門に至る」とある。さらに11月19日の条には売店の女性や女子事務員などの通勤姿に新調の衣服を身に着ける人が多いとの観察から「東京の生活はいまだ甚だしく窮迫するに至らざるものと思はるるなり。戦争もお祭さわぎの賑やかさにて、さして悲惨の感を催さしめず。要するに目下の日本人は甚幸福なるものの如し」と、平和な暮らしを描いている。
とは言え、世の中を取り締まる権力の手綱は徐々に締まり始めていた。年も押し詰まった12月29日の条には「この日夕刊紙上に全国ダンシングホール明春四月限閉止の令出づ。目下踊子全国にて弐千余人ありといふ。この次はカフェー禁止そのまた次は小説禁止の令出づるなるべし。可恐ゝゝ」とあり、60歳の荷風はこの国の暗い運命を予感している。
翌1938年(昭和13年)に入ると「今春丸善書店に注文したる洋書悉く輸入不許可」(4月3日)、「ネオンサインの禁止」(8月9日)、「虎の門その他の辻ゝに愛国心扇動の貼札また更に加はりたり」(10月8日)、さらに1939年(昭和14)に入ると「世の噂によれば軍部政府は婦女のちぢらし髪(パーマ)を禁じ男子学生の頭髪を五分刈のいが栗にせしむる法令を発したりといふ」(6月21日)、「銀座食堂にて晩飯を命ずるに半搗米の飯を出したり。あたりの客の様子を見るに、皆黙々としてこれを食ひ毫も不平不満の色をなさず。国民の従順にして無気力なることむしろ驚くべし。畢竟二月甘六日軍人暴動の効果なるべし」(12月2日)と、坂を転がるように世の中は窮屈の度を増していったのである。
そして「紀元二千六百年式典」が行われた1940年(昭和15)。年明け早々、荷風は旅順要塞司令部から旅順占領三十年祭のための詩歌を揮毫し郵送せよとの命令を受ける。「軍人間に余が名を知られたるは恐るべく厭ふべきの限りなり。いよいよ筆を焚くべき時は来たれり」と嘆いてはみたが、歌を二首寄せている。
つくね髪たかきとりでの名にちなむ妹がひたへのをかしかりけり
浪まくら稲佐の里のにぎはひをしのぶよすがも絶へ果てにけり
自分のような遊び人への詩歌の依頼とはと、呆れた荷風が茶目っ気たっぷりに詠んだのだろう。「つくね髪」とは結わずに手軽にこねるように仕立てた髪型との説もあるが、その後に「たかきとりでの名にちなむ」と続くから、難攻不落の203高地にちなみ、芯を入れて前髪を高く結い上げる髪型「203高地髷」のことと解すべきだろう。ただ「203高地」では和歌に詠めないから「つくね髪」とやや優雅な表現を使ったのだろう。この髪型は洋装にも和装にも合うことから明治35年ごろから大流行し女学生もこぞってこの髪型を結ったという。
「稲佐の里」とは長崎市の稲佐岳(標高333メートル)の東麓あたりで、長崎港の対岸に位置する。この地は幕末の開港によりロシア軍艦の寄港地となり、ロシア兵向けの遊郭も誕生。冬場に凍結するウラジオストックを母港とするロシア極東艦隊が、越冬地として利用したことにより街は栄えた。しかし、日露戦争が起きると、ロシア人の人影はすっかり絶えてしまう。街の盛衰とロシアの運命の変転を重ね合わせて感慨を詠んだものだろう。旅順要塞司令部にはユーモアを解する司令官がいたのか、荷風の歌が問題になったとの資料はないようだ。
さて、この年は、世情は詩歌の世界とは相いれない息苦しい展開を見せる。「学生の飲酒禁止」(1月14日)、「電力不足による灯火規制」(2月13日)、「芸者の遠出禁止」(5月31日)、「奢侈品制造および売買禁止」(7月6日)、「街頭にぜいたくは敵だと書いた立て札を出し、愛国婦人連が通行人に触書を渡すとのうわさ」(8月1日)…という具合だ。そして注目すべき記述が11月に登場する。西銀座のある商店の主人から聞いた話として「銀座西側だけで今年徴兵に出る者170人あり。ほどなく南京あたりへ送らるる由。丁年者の体格今年は著しく悪しくなりたりとて検査の軍人ども眉をひそめゐたりと」(11月20日)と徴兵検査の軍人の嘆きを記している。北支戦争による兵力不足も手伝い、南方戦線の立案では投入できる軍人・軍属の数はしわ寄せを受けていた。これが台湾先住民による「高砂義勇隊」へとつながっていくのだ。
陸軍は、台湾山地先住民のなかでも取り分け勇猛果敢さで知られる北部のタイヤル族に早くから目をつけていた。タイヤル族一派の反乱である霧社事件での戦いぶりが、日本側に鮮烈な記憶として焼き付いていたからだ。阿里山ツォウ族である矢多一生も、内地観光旅行で訪日した際に「そんなに体格がいいのになぜ兵隊に志願しないのか」と問われて、返答に窮したと『神国日本の感銘』に書いている。当時は一般の台湾人だけでなく、先住民も徴兵の義務がなかったからだ。しかし、やっと統治の安定を保っている時に、先住民を訓練して軍人として軍隊に組み込むことには、将来反抗の事態を招くかもしれないと、総督府にためらいがあったのも確かだ。
それでも中国大陸で戦線が拡大し続ける中で日本が南進政策をとると、熱帯のジャングルでたくましく動けるであろう先住民を、軍役要員として組織化することが課題となった。そして日本が太平洋戦争に突入した1941年12月、500人からなる「高砂挺身報国隊(第一回高砂義勇隊)」が誕生した。建前上では志願制であったが、山地をコントロールする日本人警察官が主導して参加を強く働きかけ、警察官は指揮官として戦地に赴いた。「やっと同じ日本人として認めてもらえる」と奮い立つ若者や、若い女性には「結婚するなら軍で働く勇敢な男でないと」という受け止めもあったようだが、若者が志願すると零細な農業を支える家族は疲弊する。息子を出征させたくないのは、親たちの本音でもあったであろう。
「高砂挺身報国隊(第一回高砂義勇隊)」はフィリピン・ルソン島中西部にあるバターン半島攻撃に際し、後方の物資搬送のため送り込まれたが、続くコレヒドール要塞攻撃作戦では戦闘要員として投入された。第一回の義勇隊にしてこれだ。戦地に送り込まれればそこは戦場であり、戦闘員として戦うよう宿命づけられていたのである。
「高砂義勇隊」は第七次まで編成され、合計約3800人がフィリピンのルソン島、ニューギニア、パラオなどに派遣された。戦闘が激しくない時には弾薬や食料などの荷物運び,道路開削などの労働に従事したが、戦場のど真ん中に送られた彼らが戦わずに済むわけがなかった。高砂義勇隊については公的な資料がほとんど残っておらず、生還者の正確なデータがないが、300人に満たないと推測されている。つまり戦地に赴いた9割が帰ってこなかったということだ。
これとは別に1942年(昭和17)4月から陸軍特別志願兵制度が始まった。志願者を選抜して軍人として訓練する仕組みで、一般の台湾人(本島人)が対象となった。翌1943年(昭和18)には先住民だけを対象とする陸軍特別志願兵制度が誕生、双方あわせて約5000人の兵員を養成した。一方、1943年8月には海軍特別志願兵制度も発足、海軍兵籍に編入された者は約1万1000人とされている。さらに1945年(昭和20)1月には台湾全島で徴兵検査実施し、2万2680人が合格、大部分が現役兵として入営した。
ツォウ族の若者の遺骨が戻ると、矢多一生は、高雄港まで引き取りに出かけなければならなかった。ただでさえ人口が少ない弱小部族の若者が戦死することは、矢多にとっては耐えがたくつらいことだった。若者を高砂義勇隊へと勧誘・指導することは、警察官としての矢多の職務だったが、上司に、もうツォウの若者を送り出さないでほしいと訴えてきつく叱られ、壁に向かって一晩中座らされることもあったという。
高砂義勇隊の活動についての公式資料は無きに等しく、ジャーナリストによる生存者へのインタビュー記録に頼るしかない。林えいだい編著『証言台湾高砂義勇隊』から、象徴的なエピソードを一つだけ紹介しよう。陸軍中野学校出身で、パプア・ニューギニア島の北部海岸に位置するマダンで、500人の「義勇隊」から選抜した110人の「遊撃隊」を編成した小俣洋三中尉の話だ。1943年2月、ガダルカナル島が連合軍の手に落ち日本軍は撤収、ニューギニアで連合軍と戦う作戦に移った。ニューギニアのジャングルや山岳地帯で戦うには体格強健で、闇の中で数十メートル先が識別できるほど夜目がきき、方向感覚、臭覚、敵機のエンジン音や投下された爆弾の種類を聞き分ける聴覚など、五感が圧倒的に優れた台湾先住民はうってつけの戦闘要員だった。遊撃隊は物音をたてず100メートル進むのに1時間かけて匍匐前進し、夜襲をかける。義勇隊員の武器は使い慣れたバナライ(先住民の短刀)と手榴弾だった。
1943年(昭和18)12月8日、敵陣地への攻撃命令を受け決死的な総攻撃をかけた際、小俣中尉は負傷し気を失う。戦場から野戦病院に運ばれたが銃弾や手りゅう弾の破片で10数か所の傷を負い、軍医は手の施しようがないと診断。マダンの野戦病院なら助かるかもしれないと聞いた高砂義勇隊員6人がツタを編んで担架を作り、気を失ったままの小俣中尉を載せて60キロメートルの道を4昼夜眠らず走り続け、マダンの野戦病院に送り届けたのである。軍医は傷口に沸いたウジを水で流すよう指示し、意識が戻った。数日すると貨物船の入港予定が告げられ、小俣中尉は乗船を決意し、6人に部隊へ戻るよう命令。制空権も制海権も失っている状況では、貨物船が出向すれば撃沈されるのは確実だった。中尉の決意のほどを知った6人は、今度はツタで筏を作り、周りに救命具をいくつもくくりつけ、中尉の体を筏に括りつけて涙ながらに貨物船の甲板まで運び上げ、中尉に敬礼して去った。
出港後3時間、貨物船は撃沈され、筏に括りつけられたまま波間を漂っていた中尉は日本軍の潜水艦に救助されマニラ港に入港。さらに1944年1月末、最後の病院船に乗せられたが、夕刻マニラ港を出港した病院船はバシー海峡で敵潜水艦の魚雷攻撃を受け沈没。担架に括りつけられ真冬の海を漂流していた小俣中尉は、日本軍の駆逐艦に助けられ、終戦を台湾で迎えたのだ。
実に壮絶で数奇な体験である。小俣元中尉が林えいだい氏のインタビューを受けたのは1994年(平成6)7月。銃弾が貫通して体は穴だらけ、破片を含め12個が体内に残り、1発は心臓の近くにとどまっているという状態だった。戦後、小俣さんの念頭を去らなかったのは、自分の命を助けてくれた高砂義勇兵のことだ。彼が覚えているのは、訓練の時隊長格だった「角田」と担架を貨物船デッキまで上げてくれた「青野」と「西川」だった。東海岸の花蓮出身とだけしか聞いていない。
「私は元日には、真っ先に南の台湾に向かって、貴方たち高砂義勇兵のお蔭でこんにちの私がありますと、心を込め手を合わせて拝みます」と語ったのである。
戦後、大陸から台湾に逃げ込んできた蒋介石・中国国民党政権は、長らく日本人と先住民との交流を禁じた。日本に親しみを持つ先住民は、政権にとっては潜在的な脅威だった。ましてや、戦場に赴いた高砂義勇隊員は、装備の操作に習熟している可能性もある強い兵だ。政権のこの疑心暗鬼がやがて新たな悲劇を生むことになる。そして大方の日本人は、歳月の流れとともに高砂義勇隊のことを忘れて行ったのである。
〔主要参考文献〕
◎『摘録 断腸亭日乗』永井荷風著、磯田光一編(岩波文庫)
◎『高砂族に捧げる』鈴木昭(中公文庫)
◎『証言 高砂義勇隊』林えいだい編著(草風館)
◎『台湾北部タイヤル族から見た近現代史』菊池一隆(集広舎)