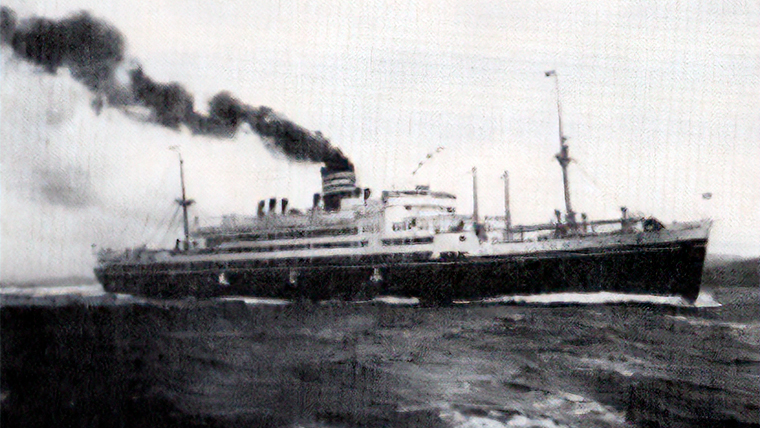高一生の生涯を理解するためには、ほぼ400年にわたって外来勢力の支配下に置かれたこの島の歴史をたどらなければならない。大航海時代、いち早くアジアに進出したポルトガルは16世紀半ば、洋上から見た緑豊かなこの島を「イーラ・フォルモサ(美しい島)」と呼び記録した。この時から、台湾は世界史の舞台に登場することになり、「フォルモサ」は台湾の美称となった。
台湾中部。脊梁山脈に源を発し、西に流れて台湾海峡に注ぐ台湾最長の大河・濁水渓は、台湾西部を南北に二分し、河を境に景観も変わる。普段は流量が少なく荒漠とした河原の広さばかりが目立つのだが、一度雨が降ると土石流が渦巻き暴れ川の本性を現す。源流部で黒い粘板岩の細かい粒子が大量に水に溶けだすことから、濁水渓の名前がある。
外国人として初めて直木賞を受賞した作家邱永漢は、日本統治下の台湾で生まれ育ち日本に留学した。戦後台湾に戻ると、日本のサンフランシスコ講和条約締結前の台湾独立に言及したことなどで治安当局に睨まれ、身の危険を感じて香港に亡命した。彼は1954年に世に出した自伝的小説「濁水渓」で、台湾人として生きる意味を模索し煩悶する主人公の「私」に、濁水渓のほとりでこう叫ばせている。「そうだ。俺の体内には開拓者の血が流れているのだ」と。台南市出身の邱永漢がなぜ小説で「私」を台中市出身と設定し、この独白の舞台に濁水渓を選んだのだろうか。それは、大地を開拓した者たちの末裔である自分に、台湾人としての誇りを自覚したからだろう。
濁水渓から南には総面積約4550キロメートルにも及ぶ台湾最大の嘉南平原が広がる。平原とは言っても、平地は西側半分で、東側は丘陵地となっており、東へと傾斜を増して台湾の背骨の山々の山裾に連なる。降水量が少なくて地味に乏しく、作物が十分に育たなかったこの大地は、後に台湾総督府内務局の技官・八田輿一が率いたアジア最大の烏山頭ダム建設と、総延長1万6千キロメートルに及ぶ一大灌漑用水路の建設によって、今では台湾の穀倉地帯に生まれ変わっている。
嘉南平原の北部に中核都市・嘉義がある。高一生の故郷、阿里山郷への入口の街だ。嘉義には、福建省出身で長崎県・平戸に居を構えた密貿易商で海賊でもある顔思斉が、今からほぼ四百年前の1621年、濁水渓を遡って嘉義市北西の笨港(現在の雲林北港から嘉義新港一帯)から上陸し開墾を手掛けた、という民間伝承が伝わる。彼は38歳の若さでこの地に没しており、ここに墓もあるのだ。また、現在の嘉義市の中心部には史跡「紅毛井(オランダ人井戸)」があり、これを中心に東西に伸びる「蘭井街(オランダ井戸通り)」、さらに今は上水道源となっている人口池「蘭堤」もある。嘉義とはどんな街だったのだろうか。
オランダは1624年に台湾統治に乗り出し、台南・安平に「ゼーランディア城(漢語表記は熱蘭遮)」を築いた。その活動記録である「ゼーランディア城日誌」には、商取引の話を中心に先住民の居住地や長老名、海賊の動向、日本との貿易などを記録している。台南の海岸は遠浅で今も塩田が広がっており、港の適地は見つからず、城塞は大きな土手のような砂洲の上に何とか築き上げた。理想的な港からは程遠いが、大陸の厦門、さらには日本との通行を考えると、長らく漢人や日本商人の密貿易の舞台だったこの地を選ばざるを得なかったのである。当時、台南にはわずかな数の漢人漁民が暮らしていたが、主役は圧倒的に多数の先住民シラヤ族だった。
城には、ドーヴァー海峡に面するオランダ南西端の州名と同じ名を付け、台湾における南西岸の拠点の意味を持たせた。今日、史跡として整備されている「安平古堡」の一角には、オランダ統治時代のこの城の赤レンガの壁が現存する。レンガはバタヴィアから運び込んだものだ。彼らはゼーランディア城の対岸にオランダ風の市街地を形成し、道路はレンガで覆ったという。
オランダ人は嘉義の地を「ティラサン(Tierasan)」と呼んだ。平地の先住民ピンポ(平埔)族の支族が暮らし、部族名から名付けたとされ、後にやって来た漢人はこれに「諸羅山」の字を用いた。嘉義から阿里山郷までは直線距離で30km強である。オランダ人が「アリサーング(Arissangh)」と呼んだこの地名に、漢人は「阿里山」の字を当てたが、オランダ語表記の由来は分からない。
ゼーランディア城日誌には1630年4月17日の項に諸羅山が初めて登場し、その後も頻繁に登場する。また、二林渓、笨港渓、北港渓、虎尾渓など濁水渓沿いの交易拠点の集落名も記録、鹿肉や鹿皮の取引、鹿狩のために侵入してきた漢人との紛争の記述もある。オランダはこれより先の1609年8月に長崎の平戸に商館を開設しており、鹿皮は江戸初期の日本への重要な輸出品であった。
オランダ東インド会社がインドネシアのバタヴィア(現在のジャカルタ)に置いたインド・アジア統括本部、バタヴィア城の記録「バタヴィア城日誌」には、1636年2月の項に、諸羅山はじめ各地の先住民集落19社の長老がゼーランディア城すぐ東のシラヤ族居住区「新港(現在の台南市新市区)」に集まり、行政長官ハンス・プットマンスの訓示を受けた後、服従の宣誓を行った、と記されている。「新港」は、ピンポ族の支族であるシラヤ族の南の拠点である。
台湾に派遣された初代宣教師ゲオギウス・カンディディウスは、この服従の儀式の後に新港に学校を開設して先住民の少年70人にローマ字を教え、布教活動を本格化した。また、同年、彼は「諸羅山に布教の途が開かれた」と報告し、学校開設と教員の配置準備にかかったとある。さらに行政長官は南北数カ所にオランダ人政務官を配置して徴税と、時に軍隊を派遣して治安維持業務に当たらせるなど、オランダの台湾統治はこの年から本格化したのである。
一方、ゼーランディア城日誌には、オランダが1655年に諸羅山に商務官ニコラス・ローエニウスを配置したこと、同年に学校教師ディヴク・シュルテスが諸羅山にいたこと、さらに9月に牧師ムーシュが諸羅山に派遣されたことが記録されており、紅毛井や蘭堤の由来を裏付ける傍証と言えそうだ。また、この地は商務官を置くほどに交易活動の拠点になっていたと推察できる。
オランダは台湾進出に際し、植民地の労働力として福建省から多数の漢人移民を入植させる計画を進めていた。しかし、明王朝は「海禁政策」で大陸沿岸部の漁業はもとより、交易活動や漢人の海外渡航を禁じていた。ここに国の掟を潜り抜ける海賊の出番がある。福建省辺りから漢人労働力を導入するにしても、明王朝と直接的な衝突は避けねばならず、オランダは海賊に頼るしかなかっただろう。顔思斉はオランダとの商売仲間ではあるが、オランダの領台前の人物であり、オランダの二つの日誌に顔思斉の名前、開拓の記載はない。にもかかわらず顔思斉による開拓伝承が生まれたのは、嘉義に開拓の歴史があったからであろう。注目すべきは、ゼーランディア城日誌の1633年12月初めの記録に「海盗劉香」と呼ばれる海賊王が登場、50艘のジャンク船団を率いて安平に現れたとの記載があることだ。「ジャンク」は漢人の船を意味するスペイン語やポルトガル語由来の言葉である。3本マストに裂いた竹を編んだ帆を張り、船足はオランダの軍艦より早く、機動力があった。しかも一艘に100人から150人を載せて航海した。操船要員を含めて50艘の船団で7500人を一航海で運べたのである。また、入植するにしても畑を潤す水と平地が必要だ。当然、河川の近くにしか適地はなく、濁水渓添いの平地に位置する嘉義は有力な入植先だったと見ていいだろう。
漢人の反乱も参考になる。福建省から台南に移住してきた漢人・郭懐一は開拓と農業に携わった農民のリーダーだが、重税に苦しむ仲間の漢人4、5千人を率い1652年9月7日夜に台南で蜂起、家屋を焼いて略奪行為に及び、オランダ人8人、黒人若干名を殺害した。反乱は、ほぼ一週間で鎮圧され、オランダは漢人3、4千人を処刑した、との報告が台湾から届いた記録がバタヴィア城日誌に見える。統治開始から30年近くなり、漢人の移住者が相当の規模に達していた証でもある。
時代が漢人の明国から満洲人の清国へと変わろうとしたころ、福建省で海賊でありながら海賊取締の長官も兼ねた鄭芝龍は、平戸で武士の娘の日本人女性との間に子をもうけた。明王朝は朱元璋が建てた王朝であり、この「朱」姓の使用を許されたことから国姓爺と呼ばれることになる海賊、鄭成功だ。「反清復明」を掲げ清国に戦いを挑んだ鄭成功は漢土で果敢に戦ったが、頼みにした徳川幕府の支援を得られず、台南に逃れた。「明史」によると鄭成功は2万5000の兵力を率いてオランダ人勢力を台湾から追い出して政権を樹立したが、ほどなく病死。その息子・鄭経は清国に降伏し、鄭氏の台湾統治は20年余で幕を閉じた。満洲人王朝の清国は1684年に台湾を版図に組み入れると、行政組織として台南に台湾府を置き、行政区域として台湾県、鳳山県、諸羅県の3県を置く。阿里山は諸羅県の管轄地となった。諸羅が県となったのは、まとまった漢人社会が既に成立している拠点だったからだろう。さらに、諸羅には砲を備えた城が築かれ、清国の台湾統治の要の都市へと発展する。1786年に起きた、反清を掲げる秘密結社・天地会の林爽文の反乱では、住民が清国軍に協力して城を守った。皇帝はこれを称える聖旨「嘉其死守城池之忠義=城下を懸命に守ったその忠義を嘉する」を贈る。これにより「諸羅」は住民の忠義を称える「嘉義」に改名され、台湾で初めての漢語の都市名が登場することになったのである。反乱の後、清は城に石組みの城壁を築いて防御を一層強化した。漢人はひたひたと押し寄せ、漢人社会は膨張して行った。
阿里山ツォウ族の「ツォウ」とは、彼らの言葉で「人」あるいは「人間」を意味する。漢人は「ツォウ」という音に、古代の山東半島辺りにあった東夷の国の名と同じ字である「鄒」を当てた。夷荻と蔑んで、侮蔑的な名称をつけたのだ。したがって、ツォウ族の名誉のためにも、表記は漢字ではなく「ツォウ」あるいは「Tsou」を使うべきだろう。
ツォウ族が暮らすのは標高800メートルから約1500メートルの辺り。阿里山郷の丘陵は曽文渓や陳有蘭渓の流れで深く浸食されており、浸食されずに残った丘の上が彼らの生活の舞台である。耕地は狭く、隣の集落に向かうにも一度渓流まで下り、また丘に上らなければならないような地形が多い。長い間「小米」とよばれる粟、サツマイモ、アズキなどを焼畑農業で栽培し、渓流での漁労と阿里山でのイノシシ、キョン、ヤマヤギ、クマなどの猟で生計を立ててきた。嘉義から阿里山郷への中間点に当たる竹崎郷一帯は漢人社会とツォウ族との境界域だったが、このあたりの丘陵地では鹿狩りもできたようだ。嘉義一帯では、河川の漁業権や山林の猟場の権利を巡って、先住民たちが激しい戦いを繰り広げていたことが記録されている。
阿里山のツォウ族にとって、自分たちの生活領域の一角に巨大な城塞に守られた漢人社会が出現したことは、大きな衝撃だったであろう。ツォウ族の行動原理の第一は、高一生もそうだが、「ツォウ族は人口もはなはだ少なく、先住民の中で最も弱小な民族である」という強い自覚である。彼らはこのことを常に胸に刻んで、外来勢力といかにして平和な関係を取り結び部族を守って行くかに腐心したのである。
実は1786年に起きた林爽文の反乱に際し、清国軍の将軍は阿里山特富野社の頭目マオタオ(毛魯桃拉)らに命じて阿里山の守備に当たらせ、彼らは大きな手柄を立てた。彼らの功績を認めた知事は翌年、マオタオらツォウ族18人を含む先住民30人を引き連れて首都北京に案内する。乾隆帝は彼らに七度も拝謁を許し、祝の宴は10回に及んだという。彼らは「朝服」などの褒美を下賜され、観光を終えて台湾にもどった。これは、阿里山ツォウ族が外来勢力と正式な関係を結んだ記念碑的な出来事だった。清王朝は圧倒的な文明の何たるかを演出して見せたのだ。日本軍が台湾に入ってきて激しい攻防戦の末に嘉義城を攻略すると、先住民の中でツォウ族が真っ先に帰順し、日本の統治に従うことを表明したのも、眼前で新たな外来勢力が軍事力を誇示し、強力な統治者の出現を彼らの眼に焼き付けたからだと言える。
高一生は1908年(明治41)7月5日、阿里山郷の大集落特富野に属する楽野村に、有力氏族「ヤタウヨガナ」の家系に三男として生まれた。ツォウ族としての名は「ウオン)」。福岡大学の宮岡真央子教授(文化人類学)によると、ツォウ族は父系氏族社会で、名はツォウ族全体で「太郎」「次郎」「三郎」というようなありきたりの11種しかなく、成長するに従い呼び名も変わって行く。したがってルーツを示す氏族名こそが重要となるのだという。高一生の場合、ウオンの後ろに氏族名の「ヤタウヨガナ」が付く。ツオウ語の発音は難しく、原音に近いように無理矢理アルファベットを充てると「uongu ‘e yatauyongana」となり、カタカナ表記は「ウォグ・エ・ヤタウヨガナ」、通常の会話の速度で発音すると「ウォンゲ・ヤタウヨガナ」となる。日本の先住民統治の最前線に配置された警察官たちは、各人がどの氏族に属するかを把握することを最重点にして日本式命名法を取り入れ、氏族名から姓を取り、名はその人物にふさわしい内容の名を充てて戸籍を作った。高一生は「ヤタウヨガナ」から「矢多」姓、名は「一夫」と付けられたが、彼の聡明さが際立ったことから後に同音の「一生」に変えられたのである。
日本が残した戸籍には彼の父は「矢多阿巴里」、母は「矢多アサ子」と記載されている。父は村人に「アヴァイあるいはヤヴァイ」と呼ばれていたことから「阿巴里」あるいは「雅巴伊」の字を当てられていたというが、日本式の名ではない。なぜだろうか。祖父の民族名は「アヴァイ・デンユアナ」である。高一生の氏族名「ヤタウヨガナ」とは異なる。つまりアヴァイはヤタウヨガナ一門に迎えられ、その氏族名を受け継いだ外部の人物なのだ。なぜそのようなことが起きたのか。ここにこそ、台湾の新しい統治者・日本とツォウ族との重要な結びつきが絡んでいる。高一生が日本の新しいエリートとして育てられる運命の歯車は、この父親が回したのである。
(文中敬称略)
〔主な参考文献〕
◎『香港・濁水渓』邱永漢(中公文庫)
◎『バタヴィア城日誌』村上直次郎訳注、中村孝志校注(平凡社東洋文庫)
◎『熱蘭遮城日誌』江樹生譯注(台南市政府)
◎『阿里山鄒族的歴史興政治』王嵩山(稻郷出版社)
◎『ツォウの名前の過去と現在;台湾原住民族の固有名回復に関する一考察』宮岡真中子(国立民族学博物館調査報告、2019-02-01)
◎ “Zeelandia, A Doutch Colonial City on Formosa (1624-1662)” J.L.Oostrhoff(Springer Link)
◎『高山自治先覺者 高一生傳記』巴蘇亜・博伊哲努(行政院文化建設委員會)