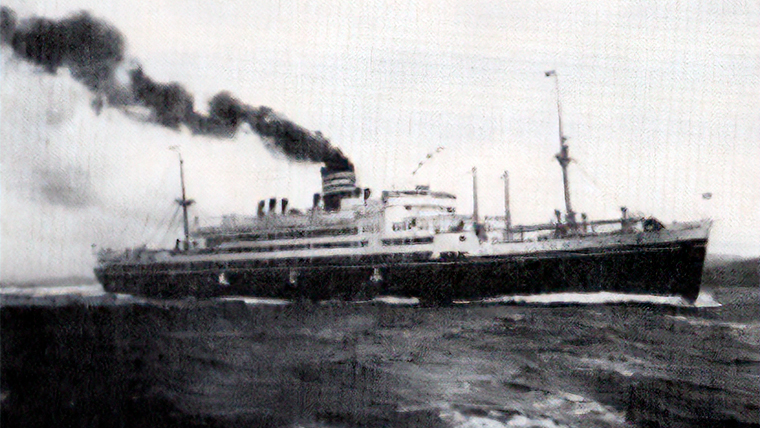基隆港の白米甕砲台(はくべいが・ほうだい)跡(wikipedia)
基隆港の白米甕砲台(はくべいが・ほうだい)跡(wikipedia)清王朝にとって、212年間統治した台湾は3年に一度小乱、5年に一度大乱が起きる厄介な土地だった。したがって統治の主眼は「台湾を反乱の基地にしない」ことだった。鄭氏の政権を倒すと、移住民十数万人を強制的に帰朝させ、女性の渡航を禁止し、さらに移住民と先住民との交流・通婚を禁止し、定住者が増えることを極力阻止しようと図った。だが、乾隆帝25年(1760)に移民の禁を緩め、家族の帯同も認めると、移住者が増えて争いが頻発するようになった。
日本と清国が講和へと向かい始めたころ、台湾社会は騒然としていた。降ってわいた台湾割譲に、地方の有力者や地主、富豪たち、つまり台湾社会の指導的立場にある民間人たちが騒ぎ始めたのだ。「軍用金や兵器を納めて来たのに」「自分たちの財産は大丈夫なのか」という不満や不安が渦巻き、知事の唐景崧に清への割譲反対の声を伝えるよう申し入れを繰り返した。彼らを力づけたのは、ロシア、ドイツ、フランスによる三国干渉に日本が屈し、遼東半島の割譲をあきらめたことだった。彼らは列強を引き込めば割譲は白紙に戻せると期待していたのだ。
知事たちの反乱
台湾知事の唐は、清王朝内の台湾割譲反対の急先鋒の実力者、両江総督兼南洋大臣の張之洞とは師弟関係に当たり、二人は緊密に連携していた。李鴻章の進める講和路線を、列強を誘い込んでつぶそうと秘密裏に策謀を練っていたのだ。張は、台湾出身で官僚試験に合格したばかりの邱逢甲が帰省したのを利用し、邱に「全台湾人民義勇軍」を組織して統領になるよう命令。さらに張はロシア、イギリスに鉱山の租借権などのエサをちらつかせて台湾への支援を画策したが、乗ってくる国はなかった。そこで唐が思いついたのが「台湾民主国」建国構想である。台湾を新国家に仕立て、承認する列強と条約を結び、優遇策で支援を取り付ければ日本を抑えることができるという筋書だ。
ただ、これは清朝への反逆となる。動きを察知した李鴻章は日本が北京に攻め入る事態へ発展しかねないと憂慮、5月20日に知事の唐を解任し、即座の離台と官僚たちの清国への帰還を命じて先手を打った。台湾で反乱を起こす者があれば、それは清国とは関係ない暴徒に過ぎない、という外交的な措置だ。さらに李鴻章は総理大臣・伊藤博文に打電し「自ら水陸両軍を派遣して、以って弾圧し、平安を保つべきなり」と伊藤に台湾の武力鎮圧を勧めさえしたのである。
唐は文官ではあるが、知事として台湾守備の最高司令官の権限を持っている。血の気の多い唐は、師である張の制止を振り切って突っ走り、5月23日に「台湾民主国」の建国を宣言して総統に就任し、25日に独立式典を開いた。台湾民主国は年号を「永清」と定め、紺地に黄色の虎を描いた「虎旗」を国旗とした。守備の清国兵は各拠点都市に駐屯している。唐は邱逢甲指揮下の義勇軍を台中に、台湾守備軍の副司令官だった劉永福を「大将軍」に就け、台南の守備に当たらせた。さらに唐は大陸で傭兵を募集し、知事の直属守備隊とした。
大将軍となった劉永福はこの20年ほど前、ヴェトナムと清との国境地帯で客家の農民兵を主体とする「黒旗軍」を編成し、ヴェトナムに侵攻したフランス兵をジャングルに誘いんでは殺害するゲリラ戦を展開。清仏戦争でも1883年からフランス軍と戦った強者である。日清の開戦間際、清王朝は劉に「黒旗軍」の再編を命じ台湾に派遣していた。
日清講和条約の発効からほぼ1月後の1895年(明治28)5月29日、初代台湾総督の樺山資紀は、台湾の正式な引渡しを受けるため台北の外港である淡水港に着いたが、清国兵の銃撃を受ける。樺山総督はすかさず台湾北端の基隆港へと回った。基隆港は東、西、南の三方を山に囲まれ、細長い水路が北へ向かって海につながる天然の良港である。三方の山には海を見下ろす砲台があり、ここを攻略しなければ台北を目指せない。樺山が北白川宮能久親王率いる近衛帥団に命じ、基隆郊外に上陸を開始させると、清国兵の抵抗は散発的で、難なく砲台を占領した。引渡式のため急ぎ基隆港にやって来た李鴻章の養子、台湾交接全権委員・李経方は「暗殺される恐れがある」と上陸を拒否。樺山総督は仕方なく6月2日、基隆港の日本軍艦上で李経方と引渡式を終える。李経方は、台湾に展開する軍の抑えがきかないことを説明した。
「残酷だが皆殺しせよ」
戦闘を覚悟して樺山は進軍したが、基隆から敗走した清国兵や台北に駐留していた守備兵は、台北や周辺で略奪に明け暮れていた。傭兵部隊で士気も低く、懐を温かくして国に帰ろうとしたのだ。独立を叫んでいた台北の有力者たちは、秩序回復には日本軍を頼るしかない。彼らは一人の若者、辜顕栄を密使に仕立てて基隆に送り込む。辜は樺山に台北の状況を説明し、道案内を務めた。日本軍の台北入りが近づくと、清兵たちは雪崩を打って淡水港に逃走し、降伏した。総統・唐景崧は、日本軍の台北入り前日の6月6日夜、部下たちと共に変装して淡水港から清国・厦門に逃走、台北陥落を伝え聞いた邱逢甲も清国に逃げ帰っている。6月7日午後、日本軍が台北城に着くと、住民が城門から縄梯子を垂らして招き入れ、城門を開けてたやすく城内に入ることができた。日本は捕虜にした3千人ほどの兵の大半を清国へ送還し余裕の体であった。樺山は「本島の未来については尊慮を労するに及ばず(心配しなくても大丈夫)」と打電。そして6月17日、彼は台北で台湾総督府の開庁式典を行い、台湾の統治が正式に始まったのである。
ところが近衛師団が台北から南進し新竹に入ると事態は暗転し、樺島の楽観は吹き飛んだ。日本兵は客家の農民や元清国守備兵の激しい攻撃に遭遇したのだ。客家農民はいわば自警団であり、猟銃があればいい方で、落とし穴を掘り、竹やり、こん棒、弓矢、青龍刀で戦った。彼らは民衆と同じ身なりで、攻撃したかと思うと素早く民衆の中に身を隠し、あるいは森林地帯へ逃げ込んだ。不案内の土地で軍服を着た集団は格好の標的であり、油断すれば背後から襲いかかられる。孤立し、全滅状態になる小隊もあり、予想外の苦しい戦いを強いられた。
当初、台湾に向かう樺山に政府が命じた指令は「やむを得ない場合には兵力をもって強制執行すべし」という穏当なものだった。ところがゲリラ戦に遭遇するに及んで「沿道の住民が良民かそうでないか分からないから残酷だが皆殺しにせよ」という強硬な方針に変わった。客家たちが故郷を守るための抵抗は、日本軍の蛮行が火に油を注いで女性も戦闘に参加するまでに燃え盛ってしまった。樺山が想定しなかった、とんでもない事態になったのである。
客家は、古代に中原の地である陝西省一帯から戦火を逃れて各地に散った漢人集団の末裔だ。最も古い時代の漢語である「客家語」と質実剛健な習俗を守り、反骨精神に富む集団である。台北に隣接する新竹の地は、客家が多く暮らす地域だ。少し後になるが1910年の台湾の人口調査によると、福建系漢人249万人、客家40万人、平地先住民のピンポ族5万人、山地先住民4万人という構成で、客家集団の大きさが分かるだろう。
台湾で「義民」となった客家
18世紀末に秘密結社・天地会が起こした反乱で、この地の客家は義勇軍を編成して反乱鎮圧に尽力した。乾隆帝は亡くなった義勇兵200人をたたえ「褒忠(忠義をほめる)」との直筆の扁額を贈った。これを機に地元では「義民廟」を建立、今日に至るまで台湾客家信仰の中心地となっている。どこへ行っても「お客さん」、つまりよそ者扱いされてきた客家は、台湾の地で「義民」という輝かしい旗印を得たのである。清王朝が台湾に送り込んだ劉永福率いる「黒旗軍」は、客家の宗教儀式で神が宿る旗と考える「黒い生地の旗」を掲げている。これほど分かりやすいシンボルはなかった。劉永福の来台もまた、台湾の客家の抵抗精神に火を付けたのである。
さらに日本軍には脚気(白米偏食によるビタミンB1不足が引き起こす深刻な病気)、コレラ、マラリアの蔓延という見えない敵も襲いかかった。病気による兵力の損耗が著しいため、軍は南進を停止し増援部隊の到着を待った。10月入って南進を再開し9日に嘉義城を攻略すると、樺山総督は台南に陣取る劉永福に書面を送って「台湾割譲は大清国皇帝の決定である」と投降を促した。これに対し劉は女性への暴行や家屋を焼き払い殺戮を重ねる日本軍の軍律の乱れと暴虐を指弾し、勧告を拒否した。
しかし、第二師団を率いる中将・乃木希典(後に第3代総督に就任)が海路で台南に到着し包囲網を敷くと、安平のイギリス領事が劉を訪問し撤退を勧告。劉は19日に英国汽船に乗り込んで厦門へ逃走し、台南は無血開城して旧清国部隊や黒旗軍兵は投降した。
こうして11月18日、樺山総督は台北から大本営参謀総長宛てに電報を打ち、反乱鎮圧に半年もかかったことを詫びた上で「未開の地今後或は一二草賊の起こるを免れ難しといえども今や本島全く平定に帰す」と報告した。平定はしても反乱は続くと認めざるを得なかったのだ。
日清戦争とそれに続く台湾平定の戦いの極めて特異な点は、戦死977人に対し病死はコレラ5211人、脚気4064人と、病死が異様に多いことだ(陸軍医務局公式記録)。とりわけ脚気についてはその後、軍医を務める作家・森鴎外も巻き込んで陸軍を揺るがす大問題となった。日清戦争で手に入れた台湾は、このような大きな代償を払って統治が始まったのである。植民地戦とはいえ、軍事力でひたすら突き進んだ結果台湾の民の恨みは深く、反乱は何年も尾を引くことになる。
阿里山で生まれた新しい絆
植民地台湾には、どれほどの民が暮らしていたのだろうか。1885年10月に福建省から切り離されて台湾省となった台湾の初代巡撫(知事)劉銘傳は、翌年4月に人口調査を行った。統治が及んでいるのは台湾の西側半分と、北東の海岸部だけだったが、戸数は約50万7千戸、人口は約254万6千人と記録されている。日本の第4代総督・児玉源太郎が1905年に実施した戸口調査では、戸数約58万5千戸、人口約303万9700人だった。ただし、これには山地の先住民は入っていない。
ではこのころのツォウ族の人口はいかほどだったのか。1915年の調査で、戸数240戸、人口2391人、わずかこれだけである。山地の先住民の中で最も人口が少ないグループだ。したがって弱小ゆえの生存戦略を選択せざるを得ない。日本軍が南進を一休みした1895(明治28)年6月、総頭目ウオンが率いる60人余りのツォウ族が山を下り、嘉義の北の雲林にあった民生部の出張所を訪ね「帰順」、友好を誓い出た。山地先住民の帰順表明はこれが最初である。2年後、この時の総頭目と副頭目は長崎や東京への観光旅行に招待されている。
帰順表明から4カ月。彼らは自分たちの決断の正しさを目の当たりにした。阿里山の入口の嘉義城が10月9日、わずか1日で日本軍に破壊されたのだ。嘉義城の城壁は市街地を囲む周囲約2800メートル・幅8メートルの環状の石の土台の上にレンガを積み上げ、高さは6~7メートル、上端の幅5メートル。大砲を備え、城壁の上は馬に乗って走ることができた。東西南北四ヵ所の城門は外門と内門の二重構造で、しかも城壁の外周には幅10メートルの塹壕をめぐらせ、規模も大きく堅牢で門を固く閉ざしている。ツォウ族を威圧していた嘉義城を、日本軍は砲撃で門を破壊しては突撃を繰り返し、陥落させたのである。阿里山にこだました砲撃の轟音は、ツォウ族に新しい時代の到来を告げたのだった。そして、ここから高一生のファミリーヒストリーが始まる。
ツォウ族の指導者たちが帰順を表明し、総頭目が日本への招待旅行を楽しんだ2年後の1899(明治32)年、千人近いツォウ族が暮らす最も大きな集落、トフヤから二人の若者が地方行政組織である嘉義事務所を訪れ、嘉義で日本語を教えて欲しいと願い出た。この二人こそ高一生の父となるアパリ(阿巴里)と、友人とおぼしきウオング・ヤイシカナである。実は台湾総督府は総頭目や副頭目に日本旅行で見聞したことを村で話させる機会を設け、若者たちの憧れを駆り立てていたのだ。試しに日本語の手ほどきをすると二人は思いがけないほど良い成績を収めた。喜んだ台湾総統府は半年後、二人を制度発足から間もない台湾人子弟のための初等教育機関、嘉義公学校に入学させたのである。先住民子弟の学校はまだできていなかった。こうして二人は新しい統治者・日本とともに歩み、人生を切り開き始める。
清朝は山地先住民の統治にはまったく手を付けず、漢人には山地に入ることを禁じていた。台湾総督府も山地の出入りを居留地の様に厳しく統制しながら、警察機構、つまり派出所をきめ細かく配置して統治しようと準備を進めていた。山地の事情や人間関係に通暁した先住民子弟の日本語習得は、大いに期待されたのである。ツォウ族の領域に隣接して暮らす宿敵のブヌン族は帰順せず反乱を起こすことも多く、反日ゲリラとして山地に潜む漢人グループもおり、阿里山の入口の要衝の地・嘉義には軍を駐屯させた。ここでアパリは一人の日本軍人と出会う。仙台で創設された陸軍第二師団歩兵第五連隊の早坂徳四郎少尉である。アパリが日本語を学び始めて2年たった1901(明治34)年9月15日、アパリは早坂ら兵士6人と役人1名で編成した阿里山探検隊に案内人として同道した。見込まれたのである。早坂は一週間の活動記録を克明に日記にしたため、写真も残していた。日記にはアパリの名が記されている。部隊に戻った早坂は荷物運びのツォウ族の若者5人とアパリを兵営に招き、酒をふるまったという。この資料は、千葉県柏市に住む早坂少尉の孫である早坂明男さんが今から20年ほど前、祖父の家を取り壊す際に、押し入れの天袋から見つけた。統治初期の先住民と日本との関りを解明する貴重な資料である。写真のアパリは大きな眼と鋭いまなざしで、意志の強さを感じさせる風貌だ。
〔主な参考文献〕
◎『日本統治下の台湾-抵抗と弾圧』許世楷(東京大学出版会)
◎『日清戦争-東アジア近代史の転換点』藤村道生(岩波新書)
◎『台湾での戦闘』国立公文書館アジア歴史資料センター
◎『台湾総督府警察沿革誌第二巻』国立国会図書館デジタルコレクション
◎『阿里山鄒族的歴史與政治』王嵩山(稻郷出版社)
◎『高一生研究7号』高一生研究会(2007年9月1日)
◎『臺灣重要歴史文献選編一』許進發(國史館)