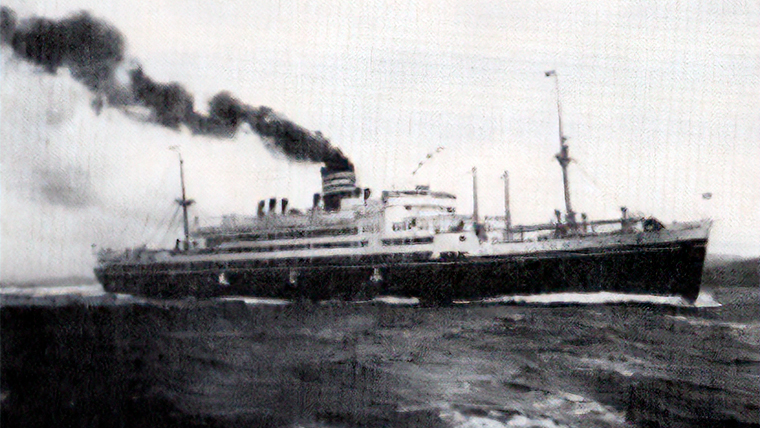矢多一生が台南師範学校でテニスや吹奏楽に青春を謳歌していたころ、台南の地は基幹産業である製糖業の活況に沸いていた。1902年(明治35)に3万トンだった製糖量は、8年後には27万トン、さらに矢多が師範学校に入学して5年後の1929年(昭和4)には1296万トンへと飛躍的に生産量を伸ばした。製糖過程の副産物としてアルコールも生産するため、裾野の広い製糖業は急成長を続け、市場は日本国内だけでなく海外へと広がった。製糖会社は砂糖の最終商品である菓子製造にも手を伸ばし、台湾製糖は森永製菓の大株主へ、三菱合資が創設した明治製糖は明治製菓の親会社となった。台湾経済は製糖業による繁栄で黄金時代を迎えていたのである。経済学者、矢内原忠雄が主著『帝国主義化の台湾』で喝破したように、サトウキビは台湾に「糖業帝国主義」を出現させたのだ。
台湾物産の太宗
台湾史は、砂糖抜きには語れない。16世紀に植民地経営に着手したオランダは、台湾海峡を挟んだ明国の福建省を中心に、労働力として漢人を大量に入植させ、耕作用の水牛や黄牛をインドネシアから輸入してサトウキビ栽培を開始した。秀吉や信長の時代から、台湾を統治していたオランダは、台湾で生産した砂糖を日本にもたらしており、台湾が砂糖の産地であることは、日本でもつとに知られていた。
明治に入ると「文明開化」で砂糖の消費量が急速に拡大する。台湾の砂糖は香港を拠点とする英国商人が、台湾の漢人糖商から買い付けて日本へ輸出していた。明治元年の日本の砂糖消費量が約23万担(約1万3800トン)だったのに対し、台湾領有の前年の明治27年には約10倍の約228万担(約13万6800トン)へと急増、1868年(明治元)に92万円だった支払額は、14.5倍の約1332万円へと膨れ上がり、関税自主権を持たない日本の国家財政上の一大問題になっていた。しかも国内での製糖業奨励の試みはことごとく失敗しており、製糖業が台湾統治の一大目的となるのは運命づけられていたともいえる。
かくて第四代台湾総督児玉源太郎の発議、外務卿を務めた大立者の井上馨の後援で、三井家が資本を拠出し、1900年(明治33)12年10日に「台湾製糖株式会社」が誕生した。創立に際し、宮内省が1000株を引き受け、その後、増資の度にこれに応じていることからしても、同社が準国策会社であったことが分かる。日本がそれまで砂糖消費量の大部分を輸入に頼っていたことや、興隆を極めているヨーロッパのテンサイ糖による製糖業に打ち勝てば、巨大な世界市場を手にすることができるという思惑があったからこそのことだ。
「我が社は夙に国家百年の大計を思ひ、国産糖の自給自足を図り、更に進んで之を海外に輸出し、糖業をして本邦重要産業の一たらしめんと欲し、他に先んじて同地に新式製糖事業を創始したり」とは、台湾製糖社史が高らかに述べているところだ。
台湾製糖株式会社が誕生すると、台湾総督府は翌1901年、農学博士の新渡戸稲造を総督府の殖産局長として招いた。後年、国際連盟事務局次長に就任し、英文の著作「武士道」を著わした新渡戸は、女子教育に力を尽くし五千円札に肖像が採用された人物である。児玉総督は新渡戸を迎えた年の11月5日、官邸に県知事や総督府高等官、「内地人本島人紳士」など約250人を招いて殖産興業に関する訓示を行い、「糖是れ本島物産の太宗たり」と述べて糖業の振興を殖産興業の首座に置き、その決意を披瀝した。「太宗」とは大元の意味である。
新渡戸が着任わずか四ヵ月後に提出した「台湾糖業の改良意見」書は、品種改良、道路や灌漑施設の整備、開墾の奨励、各種補助金の投下、大規模製糖工場の建設などを網羅した総合的なものだった。刈り取ったサトウキビは急速に糖度が低下する特徴がある。新渡戸は迅速に加工工場へと運ぶ輸送手段として、鉄道網の整備に重点を置くよう提言、これが糖業発展のポイントとなる。
総督府は直ちに新渡戸の提言を採用し、1902年(明治35)6月14日発布の「台湾糖業奨励規則」となって糖業振興策が動き出した。このスピード感こそ、台湾統治の大きな特徴といえる。
インド・ベンガル地域から中国大陸を経て伝わったとされる台湾のサトウキビに代わり、総督府が導入を図ったのは、多くの日本人移民が農業労働者としてサトウキビのプランテーションを支えていたハワイの「ローズバンブー種」と呼ばれる新品種だ。「ハワイ大茎種」とも呼ばれる新品種は人の背丈の3倍ほどにもなり、病害虫に強く、単位面積当たりの収量も多かった。小規模で家内工業的なそれまでの製糖場は姿を消した。原料のサトウキビを安定的に確保するため、製糖会社は広大な農地取得競争を続け、それまで砂糖の生産・販売権を握っていた清朝の商人やイギリス商人を台湾から駆逐。各地の零細農民は製糖会社の小作人、しかも前受金で縛られた農業労働者の集団へと姿を変えて行った。用地取得あるいは払い下げの過程では、総督府の強権介入もあったという。
サトウキビ栽培の契約農家も急増し、最盛期には台湾の全農家戸数の3分の1に当たる12万戸強がサトウキビ栽培に従事していたが、売上代金の前貸金に縛られ、買入価格も製糖会社が一方的に決める時期が続いた。
世界に支店網を構えた台湾銀行
砂糖にはもう一つの顔がある。台湾に富をもたらした砂糖は、富の集積により金融資本へと姿を変え、日本の南進を支えたのである。それは台湾銀行という特異な銀行の足跡と重なる。1899年(明治32)に設立された台湾銀行は台湾の中央銀行であり、資本金500万円のうち100万円を政府が引き受けた。株式募集では皇室も株主となるほどで、募集株数の4倍近い15万8570株の応募があり幸先の良いスタートを切った。
領台当初、台湾の貨幣は大陸同様に銀を基軸としていたが、流通していたのは銀塊であり、取引の都度、重さを秤で計量しなければならなかった。台湾銀行が開業するや、一円銀貨を基軸とする兌換銀行券(紙幣)を発行、旺盛な資金需要に応えて行く。翌年には総督府は「台湾度量衡条例」を発布し、清朝方式を廃して日本式に統一した。貨幣と度量衡の日本化で、台湾を完全に中国大陸から切り離し、日本の経済圏に組み入れたわけだ。
台湾銀行の支店・出張所網は本国では東京、横浜、大阪、神戸、海外は中国大陸の厦門を皮切りに香港、上海、福州、汕頭、広東と続き、シンガポール、インドネシアのスマランとバタビヤ、フィリピンのマニラ、インドのボンベイ、さらにロンドン、ニューヨークへと拡大の一途をたどる。内地の日本人にとって、物資も豊かで、俸給で特別に優遇され、退職官吏の天下り先も多い台湾は桃源郷として映って行った。
矢多の波乱の門出
矢多一生は台南師範学校普通科五年課程を終えると演習科一年課程に進み、農業指導の知識や技能も身につけて1930年(昭和5)3月17日に卒業した。台湾人のための教育施設の公学校でも教えることができる資格、甲種本科正教員免許状を取得し、4月11日には台南州甲種巡査に任命されて、故郷・阿里山達邦の駐在所に勤務しながら「蕃童教育所」でツォウ族の子どもたちを指導し始めた。
だが、社会人となって21歳の矢多一生が世に出たとき、世界規模の経済恐慌の嵐が吹き荒れていた。1929年10月24日、ニューヨーク株式の大暴落に端を発した大恐慌で各国で銀行が次々に倒産、日本では推定で36万人が失業し、農村危機が深刻化して娘の身売りが急増した。そして第一次山東出兵、済南事件、張作霖爆死事件、満州事変と、日本は大陸での戦争へと突き進み始めていた。暗黒の昭和の始まりだった。
足元では、植民地台湾に黄金時代をもたらした製糖業で、そのすそ野に位置する農民たちの争議が頻発して各地で農民組合が結成されるなど、民族意識も高まり始めていた。そして10月27日、総督府・日本政府を震撼させる事件が起きた。
台湾の地理的な中心、標高約1148㍍にある台湾の東西横断交通の要衝にして桜の名所だった、台中州能高郡(現在の南投県仁愛郷)の霧社で同日早朝、先住民タイヤル族でセイダッカと称するグループのうち6集落の壮丁約300人が蜂起。小・公学校の運動会に集まっていた日本人の官民や学童、郵便局や駐在所などを襲撃し136人を殺害、銃器や弾薬などを奪ったのだ。日本統治下での最大の悲劇、「霧社事件」である。
首謀者のモーナルーダオ(莫那魯道、当時47歳)はマヘボ社と呼ばれる集落の世襲頭目で、日本国内に招待旅行されたこともある人物。当時の日本側資料には、モーナルーダオの日本人巡査に嫁いだ妹が、夫に捨てられ村に戻るという“不名誉”に甘んじさせられたこと、事件の3週間ほど前に村で婚礼があり、たまたま祝宴の席近くを通りかかった日本人巡査に彼の息子が酒を勧めたところ、断られて杖で手を打たれたため、この巡査を親子で殴りつけたことなどが決起の理由とされている。しかし、本当のところはよく分からない。日本人統治への強い反感が底流にあったことは確かだろう。
総督府は軍人と警察官を大量に動員し鎮圧に当たったが、山間地ゆえに困難を極め、二ヵ月がかりでようやく反乱を収束させた。日本人の殉職者55人という数字が、この反乱の凄まじさを物語っている。事件はモーナルーダオの自殺で幕を閉じたが、同族出身で日本の教育を受け同地で巡査をしていたダッキス・ノビン(花岡一郎)、ダッキス・ナウイ(花岡次郎)兄弟の自殺は、高一生に少なからぬ衝撃を与えたことだろう。面識はなかったとはいえ、花岡一郎は台中師範学校を卒業した先住民エリートであり、自分と同じ立場だったからだ。
統治が最も上手く行っていると思われていた霧社での反乱に、総督府は先住民政策を根本から改めなくてはならなかった。事件の余燼がくすぶる翌1931年(昭和6)1月、石塚英蔵総督以下総務局長、警務局長、台中州知事などが辞職に追い込まれた。そして12月28日、先住民政策の新たな指針である「理蕃大綱」が制定された。政策の大転換が始まったのだ。
「理蕃大綱」では「蕃人」を「一視同仁の聖徳に浴しめること」、つまり「日本人化」と「皇民化」を推進し、授産に力をいれ、特に水稲栽培を重視することが盛り込まれた。集落には日本式の神社の設置も決まった。さらに同年、総督府は「蕃人青年団訓令」を発し、「蕃童教育所」の通学地区ごとに青年団を置き、若者に社会改革の先導者の役割を負わせることにした。こうして卒業から一年余り、故郷の村に巡査兼教育所の教師として戻った矢多一生は、皇民化政策のレールの上で、村を豊かにする道を模索することになる。皮肉なことではあるが、皇民化路線という大政策の歯車が回り始めたことで、矢多一生は保守的で頑迷な長老が納める村の近代化を進めやすくなったのである。
【主要参考文献】
『帝国主義下の台湾』矢内原忠雄(岩波書店1929年、1997年南天書局復刊)
『日本統治下の台湾』許世楷(東京大学出版会、1972年)
『臺灣製糖株式會社史』臺灣製糖株式會社東京出張所(1939年)
『臺灣銀行四十年誌』株式会社臺灣銀行(1939年)