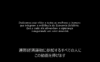上海のとある安宿に泊まっていた時のこと。山東省出身という面白い女性に出会った。年齢は40歳前後だろうか。少し親しくなると、彼女はさまざまな自説を披露してくれた。
「解放後、男女平等を唱えるようになった結果、女性は男性と同じノルマを与えられるようになった。でも女性は体力的には男性より劣る上に、子育てや家事などの仕事の負担は依然としてまだ大きい。その結果、女性は以前より疲れ果ててしまうようになった。だから、男女を別々に扱う昔の価値観の方がずっとすばらしかった」といった趣旨のものだ。そして、かつての儒教思想が具えていた長所を挙げていく。
筆者はそのすべてに賛同できたわけでは決してなかったが、その説にはある程度の説得力があった。そこで私は彼女に興味を持ち、「何のお仕事をしているのですか?」と尋ねてみた。すると、山東省で私塾を開いている、という。実はここ数年の間に、中国のあちこちで、伝統的な儒教教育を施す私塾が開かれているらしいのだ。
「興味があるので、ぜひ見に行かせてください」
「あなたの次の目的地は蘇州なんでしょ。蘇州に中国で一番条件の整った私塾、復興学院があるから、そこを見たらいい」
彼女によれば、そこには何と淑女を育てる「淑女学堂」なるものまで付設され、琴や書画などの教育を施しているという。
教育の権利を家庭に
そもそも、旧社会のジェンダーをあえて強調した教育を行う、というのは、中国ではイデオロギー的にもかなりのタブーであるはず。むしろ中国では、男女平等を原則とし、性差の強調を控えた教育をしているせいか、男女の区別がつきにくい少年少女によく出会う。そんな中、敢えて「淑女」を育てるというのは、いかにもチャレンジングだ。好奇心に駆られ、蘇州に到着後、さっそくウェブサイトを調べてみると、かなりきちんと作られたもので、単なるカルチャースクールとは異なるようだった。
さっそく実際に訪れてみる。蘇州の古い市街地を走る顔家巷にあり、古い建物を利用したその門構えは、いかにも古風で私塾らしい。

▲淑女学堂の入り口

▲学院長の付強氏
中に入ると、すぐに院長の付強氏を紹介された。河南省出身の付強氏は学院の内部を案内しながら、復興学院には、本体である私塾や淑女学堂のほか、唐代の服飾の研究と復興を趣旨とした漢服研究所、そして「国学伝代工程」というプロジェクトを通じて国学の究明と実践を行っている国学クラブなどがあることを説明してくれた。教室には、経典を読む部屋のほか、古琴を習う部屋や、書画を学ぶ部屋なども。残念ながら、外でイベントに参加中ということで、学生は一人もいなかった。

▲書画を学ぶ部屋

▲漢服研究所の入り口
付氏によれば、現在、復興学院では13歳以上の中学生が10数人学んでいるという。「国は教育を法律で束縛すべきではありません。肝心なのは良い教育を受けさせることです。150年前、子どもの教育権は父母にありましたが、現在は国家に委ねられています。でも本来、子どもから一番近い存在は父母です。国に教育を行う権利はありません。また、子どもを学校に通わせないことは、子どもに教育を受けさせないことを意味するわけではありません」。実際、中国でも日本でも、かつての教育は、家庭や書院で行われ、そこから思想家や詩人、官僚、宰相など、多くの文人や才子が育った。
付氏の見解によれば、現在、中国全土にはこのような書院が500カ所ほどあり、各家庭で開かれている私塾に至っては1万を超えるはずだという。
洗脳から自己本位へ
こうなると、気になるのは、中国の既存の教育システムとの共存だが、驚くべきことに、正式な学校としての資格を持たず、国の定める指針に従った教育も行っていないにも関わらず、国からの干渉はないという。「現在、中国では既存の教育に疑問がもたれ、いろいろな教育モデルの模索が行われています。とくに文化芸術関連に関しては寛容です。そんな中、復興学院のような存在も黙認されているのです」と付氏。
全日制のカリキュラムからは、すでに2人の卒業生が社会に巣立っている。制度上は学歴を持たないことになる彼女らは、自ら茶道会館を開いたりして生計を立てているという。
「ソ連式教育の影響を受けた現在の教育には、マイナスの要素が多い。まさに暗黒ですよ。脳が洗脳されます。科学的な体系は、思考をむしろ脅威にさらすのです。でも本来、教育は人間的なロジックに基づくものでなくてはなりません」
「全世界が共有しているゴールは、お金を稼ぐこと。だから今日の学生は『儲かる』専門を選びがち。でも学問とは本来、将来の就職や出世とは切り離された自由な場であり、各自が心のまま行うべきものです。そもそも人は、何を学ぶべきかを自分で知っているのですから」と付氏。そんな中、復興学院が重視するのは、生徒一人一人が「内から自分を変える」ことだ。カリキュラムにおいては、「琴棋書画」を通じて、生徒たちをある心身の状態へと導いている。
「文化の精髄を伝えている楽器、洞蕭(尺八に似た楽器)や古琴を学生に与えると、彼らはひとりでにコツをつかみ、演奏の仕方を習得していきます」と付さん。「皆、外に何かを見つけようとしています。でも人は自らの中に真理を見つけるべきです。だから学校とは、静かで知恵が育まれる場所でなくてはなりません」。
学院のカリキュラムは複雑に編まれているが、それらは少人数を対象にした、「全面的で的確」なものだと付氏は強調する。「アメリカや日本では一つの学校に数千人の学生がいたりします。だから学習の効率が悪いのです。本来なら、教育の選択とは生活の方向を決めるもの。中国人に合ったスタイルがあり、そこには中国の伝統に基づいた特質があるべきです」。
「淑女」を育てる
付氏は、氏のいう「的確」な教育を受けた全日制の学生の一人が、最初の半年でいかに変ったかを、ビフォア&アフターの二枚の写真で示してくれた。雲南から来たという活発で明るそうな現代っ子が、確かに澄ました表情の「淑女」へと様変わりしていた。現在すでに4年間、ここで学んでいるという。

◀復興学院の学生の写真(2008年の4月と10月に撮影したもの)
一方、淑女の養成にターゲットを絞った「淑女学堂」については、現在学生は20人ほど。中には上海から来ている女性もいるという。一般的には24歳から25歳前後の、ポスト‘80世代が多い。集中的に学ぶ学生もいれば、仕事しながら学ぶ人も。やはり「自らの理想」の実現のために学び始める人が多いということだが、付氏は「時代的な要因も大きい」と語る。それまでの接触があまりにも少なかったことが、彼女らの中に伝統音楽や書画への、強い興味をかき立てる結果となっているというのだ。
確かに、北京に住む筆者の友人の中にも、OLをしながら古箏を学び始め、「いずれは故郷で古箏教室を」という野望まで抱き始めた30代の女性がいる。伝統音楽に携わる他の専門家の話からも、近年、優雅な伝統音楽の響きが、多くのホワイトカラーの女性の憧れの的となっていることは、確かなようだ。伝統と疎遠であった時代への「反動」が、まさに淑女学堂の人気の追い風となっているといえる。
西洋の教育は野蛮?
「一人一人に自分の真実があればよい」と語る付氏。その意見には、確かに耳を傾けるべき点も多い。だが外国、特に西洋の文化を語る段になると、付氏の論調はかなり排外的なものになる。「ヨーロッパには文化がなく、西洋の学校や病院はもっとも文明に欠くもの」と考えているからだ。「保護者たちは、将来のためにと、子どもに学校教育を押しつけます。でも、たとえ有名校であっても、教育について理解しているとは限りません」。服と健康に関しても、中国の方が科学的だと付氏は主張する。「中国の服は、前が二重で後ろが一重です。それは、前の衣で内臓を守らねばならないからです。でも、西洋の服は前も後ろと同じで一重。内臓に良くありません。服装自体も醜い。どんなにデザインに苦心しても、『真実』からは離れているからです」。付氏によれば、そういった文化の「おかしさ」に気づいた西洋の文化人が最後に行きつくのは「発狂」だという。
では、「復興学院」は西洋的価値観に基づく既成の教育を「補う」存在なのか? 「違う」と付氏は答える。「補充ではなく、ここで得られるのは『正しい学問の道』です」。つまり復興学院はむしろ、ミッションスクールのような、宗教をバックボーンに据えた学校に近いらしい。もっとも、ここで中心に据えられているのは「漢」の思想だ。「中国における宗教とは、祖先の教えです。でも教育の主体を占めていた思想、『祖先たちの精神』が現在、破壊されています。そんな中、当学院は東洋的な秩序や尊厳を学べる場所なのです。理想的なプランとは、工場や会社に就職する18歳までの間に、人としてどのようにあるべきかを学んでおくことです」。
対象は漢人の子弟のみ
ここで多くの人が連想するのは、孔子学院かもしれない。だが中国文化の海外での普及を旨とする孔子学院と復興学院とは、やはり系統をだいぶ異にしているようだ。復興学院は、国内でのみ事業を展開しているからだけでなく、生徒を「漢人の子弟」に限っているためだ。
ここで筆者は疑問を覚えた。
「漢民族とは、もともとさまざまな民族が融合して形成されたものですよね。それなのに、他の民族はシャットアウトするんですか?」
「漢民族という言葉は正しくない。中国には実際には『漢』があるだけです。夷狄と対置された華夏というアイデンティティです。少数民族には、独自の生活の能力、彼らなりの残すべき特色があります」
「西洋人の中にも、中国人に負けぬほど中国文化に関心のある人がいますが」
「西洋人は内面を構成するものや能力が違います。情熱だけでは足りません」
「中国で育ち、言葉も考え方も中国人に近いような人もいますよ」
「外側のイメージが内面にも影響するので、駄目です。学術的な交流なら構いませんが」
「でも、本当にそんなに優れた教育なら、もっと多くの人に門戸を開かねば、とは思わないのですか? あなたのおっしゃる『文明的でない』、暗黒の世界にいる人々に、救われる機会を与えようとは思わないのですか」
「全日制で教育を行うということは、かなりの欠損が出ることです。本来、授業時間から換算すれば、学費はとても高くなるはずなのです。そもそも経済的な補助が必要なものである以上、『身辺』の人しか救うことはできません」
つまり、「狂気」に向かうだけの西洋思想に支配されつつある世界において、ノアの箱舟に乗れるのは身も心も「漢人」である人々だけだ、ということになる。
今年は4713年?
もちろん、こういった「漢」至上主義が、現代中国において顕著な、西洋文化への極度な傾斜に対する反動として生まれていることは間違いない。幼児期からの英語教育に象徴されるような、西洋文化の「スタンダード化」は、確かに十分な議論を経ないまま、中国国内においてどんどんと進行している。
言語だけではない。音楽や暦などについても、日本と程度こそ異なれ、やはり西洋的なスタンダードは中国人の生活の中に定着している。中国にも伝統的な楽譜の記し方や、「簡譜」と呼ばれる独自の数字譜はあるが、正式に音楽を学ぶ場合はやはり五線譜が使われているし、暦についても、通常は西暦が用いられている。それらを踏まえ、付氏は「楽譜、暦、節句のすべて」を「中国伝統のものに改めるべき」と主張する。
とはいえ、皇帝の存在しない今、年号についてはどうするのか。すると、「漢民族の祖先とされている炎黄(炎帝と黄帝)の出生年から数えればいい」との答え。
「では今年(2012年末現在)は何年ですか?」
「4712年です」
まさに気の遠くなるような「復興」。新興宗教の勃興さえ連想させるこの動きは、少なくとも今のところは、基本的な理念に自己撞着が目立ち、中国において主流の座を獲得できそうには思えない。だが氏の言うように、復興学院のような私塾が国内で本当に増えているとすれば、やはり排外的な中華原理主義とでもいうべきものが台頭していることになる。
もちろん、他者への「強制」や、権利の剥奪がない以上、その存在はまったく自由で、外部の者が非難すべきではない。だが、教育が政治的イデオロギーと連動しやすいことは、万人の知るところだ。今後、中央から弾圧された場合、逆に民衆の支持を得ていくこともあり得る。特に、日中の過去の不幸な歴史へと話が及んだ際の、付氏の高圧的で妥協を許さない口調は、筆者にちょっとした不安を抱かせた。そして、「漢の文化こそ文明的」とし、「理想的教育」を「漢人」だけにもたらそうという彼らの動きが、何かのはずみで狭隘なショービニズムの温床とならないことを、祈らずにはいられなかった。