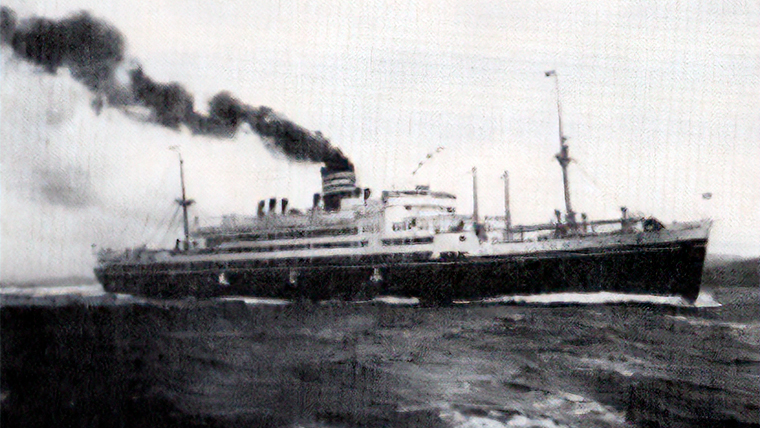台南師範学校を卒業して故郷の阿里山・達邦で警察官兼蕃童教育所の教師として働き始めた矢多一生は、1935年(昭和10)に発足した阿里山青年団の初代団長となる。当時の台湾の山地は警察の厳しい統制下にあり、台湾人はもとより日本人も出入りを制限されていた。こうした状況で、矢多は台湾総督府の威光を背に、青年たちと共に村の古い習慣を改めようと取り組み、水田耕作や新しい農作物の栽培などの活動にも指導力を発揮し始めた。活動の核となった達邦青年団は「陋習打破(家屋内埋葬の習慣)」や水田耕作などの取り組みが特別に優秀であるとして、総督府から表彰され助成金を与えられている。矢多の活動は、山地先住民の模範となるべきものであると、総督府の覚えがめでたかったのである。
1940年(昭和15)、矢多は初めて日本を訪れる機会を得た。しかもこの年2回も訪日したのだ。
一回目は5月3日から22日まで、高砂青年団内地観光団の団長としての訪問だった。一行は引率の日本人巡査7人を含む総勢64人。基隆から出港した近海郵船・富士丸は門司港に接岸し、一行は列車に乗り換えて大阪城、伊勢神宮、奈良から名古屋の熱田神宮、皇居、さらに日光東照宮などを訪れた。矢多は旅行の感想を台湾総督府警務局理蕃課が発行する機関誌「理蕃の友」に寄せている。「神国日本の感銘」という「理蕃の友」が用意した標題から分かるように、矢多の文章は、理蕃課が期待したであろう優等生的な文章が連なり、どこかしらじらしくもあるが、矢多の苦しい胸の内も推察できる。
ただ、岡山県・高陽村(岡山市に隣接する現・赤磐市)の農業視察の部分では、彼の率直な思いが綴られているように思う。高陽村では村人が総出で一行を歓迎し、宿泊の世話には青年団男女が当たった。矢多は同村で養豚や養鶏などの副業が盛んなこと、土地を利用し尽くす勤勉さ、産業組合の経営に心打たれた。矢多は高陽村の年間労働日数が260日~280日と阿里山より80日~100日も多いということを聞くに及び「数年前までは貧乏村だった高陽村が、村長の指導の下、青年団の総力を挙げた取り組みで、今では天下の模範村になったことは当然だ」と感嘆した。その上で「我が阿里山地方も、皆の者が心を協せて一所懸命働けば、此の半分位の優良村になれるのではないか」と故郷の発展への思いを新たにしている。
矢多が取り分け感銘を受けたのは、青年団の心根だった。彼らは布団の上げ下ろし、炊事、風呂の世話までまめまめしく体を動かし、夜は青年団主催の歓迎大演芸会を開いて「忠臣蔵」を演じて一行を楽しませた。そのもてなしの心の奥にある温かい人間性に打たれたようだ。矢多は青年団男女について「私達を軽蔑するやうな素振りは少しもなく、總て内地人と同様に全く遠来の友達といふ気持で待遇して下さいました」と感謝の念を記している。
山地先住民は警察の厳しい統制下の閉鎖空間で暮らしている。はつらつとした日本の男女の若者集団と接するのは初めての経験だったろう。矢多の感想文では、内地観光では「どこでも至れり尽くせりのもてなしを受けた」と書いているものの、高陽村の青年団への感謝を表す中で、意図的ではないにしても「私達を軽蔑するやうな素振り」がなかったことを書き留めていること自体、旅行中に「私達を軽蔑する素振り」を受けたことが多々あったのだろうと推察できるのである。
台湾先住民を対象とする「内地観光」は、台湾平定直後の1897年(明治30)から1941年(昭和16)まで合計17回実施された。日本の委任統治領となった南洋の島々からも同様に島民が観光団として派遣されたが、どちらもその目的は、文明国日本の発展ぶりを見せつけ統治に役立てることだった
文豪・永井荷風の日記文学『断腸亭日乗』には、荷風がたまたま目撃した台湾からの観光団の様子を書き留めているくだりがある。1918年(大正7)5月4日の条である。
築地けいこの道すがら麹町通にて台湾生蕃人の一行を見る。巡査らしき帯剣の役人七、八名これを引率し我こそ文明人なれと高慢な顔したり。生蕃人の容貌日本の巡査に比すればいづれも温和にて陰険ならず。今の世には人喰ふものより遥かに恐るべき人種あるを知らずや(原文のまま)
荷風らしい観察眼による痛烈な批評である。この一文で台湾先住民統治の核心をずばりと衝いている。
矢多が書き記したことには日本への批判めいたことは何一つないのだが、つい書いてしまったと思わせる部分がある。それは「初めて乞食を見た驚き」のくだりである。「内地人は皆金持ばかりと思って居たのに、乞食というものがあるのに吃驚した。親類の者は何故援助しないだろうか。京都では特に多かった。可愛想だから十銭與へたら土面に頭をすりつけてお禮を言って居た。私も泣き度くなった」。優しい矢多の精神の発露であろう。
観光団は下関から大阪商船の高千穂丸で帰国の途に就いた。
内地観光団の見聞よりも遥かに矢多の人生に影響を与えたと思われるのが、同年11月の訪日である。矢多は九歳年長の新竹州・角板山のタイヤル族の指導者、日野三郎(1899-1954、部族名:ロシン・ワタン)と二人して、宮城前広場に天皇・皇后が出席した内閣主催の「紀元二千六百年式典」に台湾高砂族代表として派遣されたのである。この派遣で二人は名実ともに「高砂族」の代表として認定されたと言える。
「紀元二千六百年式典」は、「初代天皇とされる神武天皇は紀元前660年に即位した」という『古事記』の解釈を拠り所とし、日本政府が5年がかりで準備した一大イベントである。『古事記』には「神倭伊波礼毗古の命」が宮崎県・高千穂から東征し、荒ぶる神を鎮め、まつろわぬ人々を征討して畝火(畝傍山のふもと)の白檮原の宮(奈良県橿原市)で即位したという記述がある。この年を紀元前660年と決めたわけだ。わが国で最初の「史書」とされる『日本書紀』では神武天皇は「神日本磐余彦天皇」と表現されており、治世76年の春、橿原宮で亡くなり享年127歳と記している。
日本政府はなぜこのような祭典を企画したのだろうか。1931年(昭和6)の満州事変、翌年の満州国建国宣言、さらに国際連盟脱退へと、日本は国際的な孤立化の道を進み始めていた。国内的には憲法学者で貴族院議員・美濃部達吉が掲げ、学会の通説となっていた「天皇機関説」、統治権の主体は国家であり、天皇は国家の最高機関であるとする学説に、政友会と勢力を増してきた軍部や右翼が手を組み公然と難癖をつけ事件にまで発展した。彼らは政府に「国体明徴」、つまり日本が万世一系の天皇が統治する国家であることを国民に知らしめ再認識させよと圧力をかけ続け、1935年に政府に二度にわたる「国体明徴宣言」を出させたのである。この結果、日本政府は「紀元二千六百年式典」開催に取り組むことになる。さらに南洋庁管轄下の南太平洋パラオ島にはパラオ神社、満洲国には建国神廟が建立された。
こうした流れの一つに、宮崎市の「八紘一宇の塔」の建設がある。「八紘一宇」とは「日本書紀」の「八紘をおおいて宇となす」の文言を根拠とした造語で、世界万国を日本の天皇の下に統合する思想のスローガンとして用いられた。ちなみに昭和天皇は美濃部の天皇機関説について「機関説でいいではないか」と首相・岡田啓介に語っていたのである。日本は「国体」を金科玉条とする軍部の横暴な力が統制不可能な状況にまで強まり、国家総動員体制へと突き進んで行った。
戦後、「紀元2600年」思想はGHQ(連合国軍総司令部)に否定されたが、きちんと評価されるべきこともある。それは日本政府がドイツ人のリヒャルト・シュトラウス、フランス人のジャック・イベール、イギリス人のベンジャミン・ブリテンなど世界のそうそうたる音楽家たちに祝典音楽の作曲を依頼したことである。日本での上演機会は極めて少ないが、彼らの作品は今日でも世界中で演奏されている。
作曲当時75歳の大御所だったシュトラウスの作品「大編成オーケストラのための日本国天皇統治2600年祝祭音楽」は、彼らしい複雑な作曲技法を駆使しオーケストラが大鳴動する壮大な音楽であり、本人が指揮した演奏はレコード録音された。日本では12月に東京と大阪で総勢160人余りの特別編成のオーケストラで演奏された。イベールの「祝典序曲」は華麗で輝かしい音楽であり、東京でシュトラウスの作品と同時に演奏された。ブリテンの「シンフォニア・ダ・レクイエム」は祝祭とは趣を異にする音楽であり、オーケストラが練習したものの、なぜか上演はされなかった。ただ、1956年2月に、来日したブリテン自身の指揮で初演されている。これらの曲はユーチューブで簡単にアクセスできるので、「皇紀2600年」という冠を外して、純粋に音楽として聴いてみられることをお勧めしたい。
さて矢多一生と日野三郎の話に戻ろう。二人は台北で1935年に開かれた「高砂族青年団幹部懇談会」で初めて出会っているが、二人が打ち解けて会話を交わしたのは1940年の「紀元二千六百年式典」出席がきっかけになったと思われる。東京でなら、二人は食事を共にし、共通語の日本語で比較的自由な意見交換ができたと思われるからである。ただ、阿里山を思考の中心に据える矢多とは違い、日野は政治志向の強い人物だった。それには、日野の出自が大きく影響している。
日野三郎は、台北県三角湧のタイヤル族総頭目ワタン・シェッツの長男として生まれた。ワタン・シェッツは日本の統治に最後まで武力による抵抗を貫いたが、近代装備の日本に手向かい続ければ部族が滅ぼされると悟り、1909年(明治2)、自ら角板山で警察に出頭し「息子ロシンに日本の教育を受けさせること」を条件に人質として差し出し、日本に帰順した。ロシン・ワタンは「渡井三郎」と名付けられ、角板山蕃童教育所、桃園尋常高等学校を経て1916年に総督府医学校に入学、先住民出身の医師第一号となった。彼はタイヤル集落の公医として活動、各集落の生活改善にも積極的に取り組み、次第に山地警察の信頼を勝ち得ていった。そして1929年、警察の意向を受けて四国の名家、日野家の娘と結婚し「日野三郎」と改名、医師活動の傍ら角板山青年会会長も務めた。こうして矢多一生との出会いの場が準備されたのである。
「紀元二千六百年式典」への出席が二人を結び付けたのではあるが、警察の統制下にある山地では自由な交流ができたわけではない。二人が手紙のやり取りをしたり、自由に面会できるようになったのは日本が敗戦によって台湾を去ってからである。同時に、これは二人の悲劇の出発点となるのである。
【主要参考文献】
◎『摘録 断腸亭日乗』永井荷風著、磯田光一編(岩波文庫)
◎『理蕃の友』台湾総督府警務局理蕃課
◎『岡田啓介回顧録』岡田啓介(中公文庫)
◎『昭和天皇語録』黒田勝弘・畑好秀編(講談社学術文庫)