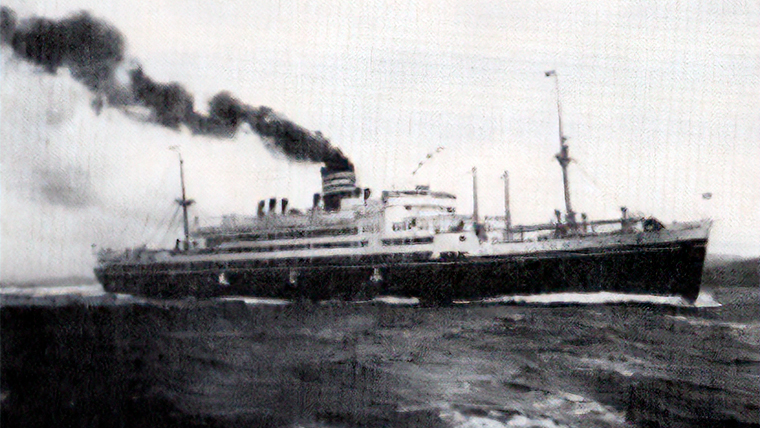高一生の生涯をたどるこの連載で、どうしても触れなければならないのは、なぜ日本が台湾を統治するようになったかの歴史である。少し長くなるが、お付き合いいただきたい。
九州と本州を隔てる関門海峡が幅400メートルほどにまで狭まり、潮の流れが最も速くなる壇ノ浦に、関門橋は架かる。橋のたもとから西側のやや小高い丘の縁に、源平の戦いでこの海に入水した幼帝・安徳天皇を祀る赤間神宮があり、その西隣に「春帆楼」がある。山を背に、海峡を繁く行き来する船影を見渡すこの割烹は、明治の元勲、伊藤博文の勧めで明治14~15年ごろに開業し、屋号は伊藤が命名、さらに伊藤の指示で県知事がフグの食禁を解き、フグ料理の公許第一号店となった。
1894(明治27年)に起きた日清戦争の講和を話し合う下関会議の会議場としてこの春帆楼を選んだのは、時の総理大臣で全権として会議に臨んだ伊藤博文である。総勢百人を越える清の使節団は、近くの引接寺に滞在した。江戸時代に朝鮮通信使一行が宿泊所とした古刹である。
日清戦争が起きると、戦時の天皇直属の最高司令部である大本営が広島に置かれた。戦線にできるだけ近い都市は、当時の山陽本線の西の終着駅だった広島であり、ここには陸軍第五師団が駐屯している。しかも、明治政府が招請したオランダ人土木技師、ローウェンホルスト・ムルデルが設計した宇品軍港は1890年に完成し、港まで17キロメートルの鉄道も敷設されて、兵員と物資の輸送の拠点として最適だった。明治天皇は広島に移り、帝国議会の仮議事堂もこの地に建築された。広島は“臨時首都”の観を呈したのである。
この戦争は朝鮮を「属国」として来た清国と、これを「自主独立の国」として影響下に置きたい日本が、農民を主体とする新興宗教の東学教徒の反乱を機に1894年7月、相次いで朝鮮に出兵し戦端を開いた。日本は朝鮮国王の父・大院君を擁立し、清国との宗属関係を破棄させた。そして8月1日、日清双方が宣戦を布告したのだ。清国の本音が露骨に表れているのは、光緒帝の宣戦詔書である。この冒頭「朝鮮は大清国の属国であり、二百年余り貢物を納め続けて来たことは世界にあまねく知られている」と前置きし「倭人は正当な理由なく派兵し漢城(首都ソウル)に突入した」と、日本人に対する蔑称である「倭人」という表現で露骨に日本を貶め、戦争を発動したのである。信じられないことだが、戦端を開いても、日本には朝鮮をどのような国にするかという具体的な青写真があるわけではなかった。
日本は北へと逃走する清国軍を追って攻め上り、9月中旬には朝鮮からすべての清国軍を放逐するとともに、黄海海戦で北洋艦隊に勝利した。北洋艦隊はドイツとイギリスから購入した最新鋭戦艦で編成した清国の海軍力のシンボルであり、開戦前に二度にわたり日本を訪問。親善という名目だったが、砲艦外交で威嚇した経緯がある。黄海海戦の勝利の後、日本軍は朝清国境の鴨緑江を渡り、清王朝の父祖の地・遼東半島に進んで北洋艦隊の本拠地・旅順を占領。さらに翌1895年2月、山東半島にある同艦隊の軍港・威海衛の砲台を占拠した。ここに至って清国は講和を求めたのである。戦争目的は達成したはずだが、ここで突然、日本は領土獲得を目指す。
清国は1885年1月末に「講和使」を広島に派遣した。ところが清国使は地位もそれほど高くなく、二人が携えて来た「全権委任状の不備」を理由に日本は会議を拒否した。この時点では、清国側にはまだ時間稼ぎの余裕があったが、2月の威海衛の陥落で、もはや李鴻章を派遣して講和に応じるしか道は無くなったのである。
大本営がある広島との往来に便利な港で戦線に近い下関の地は、講和会議の開催都市にふさわしく、春帆楼は下関を代表する社交場だった。1895年(明治28)3月20日、日本側全権・伊藤博文、外務大臣・陸奥宗光、清国側全権の李鴻章と元駐日公使で李鴻章の養子である李経方が次席全権兼通訳として会議が始まった。下関会会議では、日本側は伊藤と旧知の間柄で手紙のやり取りもしていた李鴻章を交渉の場に引き出すことに成功した。外交交渉で決断を下せる人物は、西太后の信頼厚い李鴻章をおいて他にはいないと日本は考えたのである。李鴻章は北洋艦隊を所管する北洋大臣と、首都とその周辺省を管轄する最高位の地方長官、直隷総督を兼ねる清朝の改革派の大立者である。
米国が仲介に乗り出したこの講和会議で忘れられがちなのは、交渉が始まった時点では戦闘が継続中だったことである。伊藤と数時間も談笑する72歳の李鴻章を、陸奥は「老翁に似ず容貌魁偉言語爽快」と評した。顔や体つきは古希を越えた老人とは思えないほど立派であり、言葉をよどみなく繰り出してくると誉めているのだ。その李鴻章は、日本側の覚書に「もし休戦を望むのであれば天津や山海関などの城塞を日本が占領し、清国軍隊は一切の軍器、軍需を引き渡すこと」や「休戦中の日本軍事のすべての費用を清国が負担すること」などを盛り込んでいるのに驚き、「顔色を変えて『過酷なり』」と連呼して、日本政府に再考を求めた」と陸奥は記している。
全滅に近い形で北洋艦隊を失い、しかも日本軍は清国領土に入り、天津を伺っている。天津は首都北京の喉元にある。日本側は勝ち戦を進めており休戦の必要はないと強気の姿勢で押し、西洋列強が介入する機会を封じて一気に決着をつける算段だった。伊藤には李鴻章に名物のフグ料理を馳走する気持ちもあったかもしれにないが、下関は日本艦隊を見せつけるには効果的な場所だったことも確かだ。
日本は清国に更なる圧力をかけた。嘉義の西方約60キロメートルにある台湾海峡の戦略の要地、澎湖島を24日~25日に占領したのである。清仏戦争でフランスが澎湖島を占領して講和への圧力をかけた史実に習ったのだろう。戦争の主目的ではないが、台湾の割譲については列強も許容するだろうとの読みもあり、南洋進出の拠点となる台湾領有への布石を打ったのである。
清朝の断末魔1 アヘン戦争と太平天国の乱
歴史を少し遡る。19世紀半ば、清国と貿易を行っていたイギリス・東インド会社は、茶葉の輸入超過で代金の支払いに苦しんだが、清に売る魅力的な商品にも事欠いていた。そこで、インド・ベンガル地方でアヘンを増産し、これを清国に売りつけて貿易の黒字化を図った、何ともあくどい政策である。アヘンは奔流となって清国内に蔓延し、貿易決済に用いる銀の流れはイギリスへと逆流する。英国の香り高い紅茶文化に隠された暗黒の歴史だ。
アヘンを取り締まる清国が、押収したアヘンを焼却するに及んで、英政府は賠償を要求、清国はこれを拒否し1840年のアヘン戦争に至ったのである。戦争とはいっても、戦場は沿岸部に限られ、イギリスは一方的な勝利を収める。そして香港の割譲を勝ち取り、それまで広州の指定貿易商に限られていた貿易の仕組みを改めさせ、広州、厦門、寧波、福州、上海を自由貿易港として開かせた。巨額の賠償金を手に入れたのはもとよりのことであった。
アヘン戦争の結果、清で銀が不足し銀価格が高騰する事態が生じた。清では税金を銀で納めなければならず、日ごろ市中に流通している銅銭を銀へと両替して税の支払いに充てるのだが、清国内の銀不足から銀価格は2倍になっていた。つまり税金が2倍になり、当然、物価も高騰する。清朝の支配に対する反感が急速に高まり、ついに1850年秋、新しい宗教教団「拝上帝会」を組織した洪秀全が、南の国境に近い広西省で蜂起し、1851年1月「太平天国」を国号として独立を宣言。洪秀全は漢族の客家出身の貧しい読書人で、官僚登用試験の「考試」に落ち続けた人物である。客家については次稿で詳しく説明する。太平天国軍は「滅満興漢──満洲人政権の清王朝を滅ぼして漢人の政権を再興する」をスローガンに掲げ、兵を挙げる。地主への小作料不払いや清国政府への税金不払いの運動が頻発していたこともあり、太平天国軍は客家の農民や少数民族のチアン族を主体に膨れ上がり、怒涛の様に進軍して南から駆け上り清軍を圧倒、一時は首都北京にまで迫った。
清朝の断末魔2 アロー戦争とフランスのヴェトナム侵略
イギリスは反乱に苦しむ清国にチャンス到来とばかり再び襲いかかる。1856年10月、広州港に停泊中だった香港船籍のアロー号に清朝官憲が立ち入り調査を行った際「イギリス国旗を引きずりおろした」と抗議し、これを開戦の口実とした。イギリスは、今度はフランスを誘い、共同出兵したのである。英仏軍は広州を占領した後、天津に向かい砲台を占拠。さらに首都北京に進軍し、西太后の離宮・圓明園を略奪・焼き討ちするという破壊活動を行い、皇帝は熱河省へ難を逃れた。清王朝の権威は地に落ちた。これがアロー戦争、または第二次アヘン戦争と呼ばれる紛争で、この結果、イギリスは香港の対岸の九龍半島を得た。さらに新たな開港地として台湾では淡水と台南が1858年に、さらにその5年後には基隆と高雄も開港する。列強によって、台湾の扉は力づくで、こじ開けられたのである。
アロー戦争のさなか、フランスは清国の保護国、つまり属国だったグエン王朝のヴェトナムを清国から引きはがしにかかる。宣教師の保護を名目に1859年、南部のメコン川デルタ地帯に派兵し、現在のカンボジア、ラオスを手に入れる。
14年間にも及んだ太平天国の乱は、清王朝の土台を根底から揺るがせた。この大乱では、清の正規軍が弱体化して乱を鎮圧できず、官僚の曾国藩が組織した「湘軍」や、李鴻章が組織した「淮軍」という漢人の義勇軍の活躍で、ようやく抑え込むことができたのだ。これ以降、清国の権威はますます弱まって軍事では「義勇軍」が中心となって行き、李鴻章は北洋艦隊の創設へと動く。
太平天国の乱から約20年。フランスは1883年8月から足掛け3年にわたる清仏戦争を始めた。そして清国に王手をかけるべく1884年8月に台湾の基隆港を攻撃、2000人の兵を上陸させた。さらに翌1885年3月には澎湖島に攻め入り、圧倒的な火力で清の守備兵を制圧して4カ月にわたり占領、軍事力で清に講和を促した。清は敗北を認め、フランスは全ヴェトナムを保護領とする目的を果たして澎湖島から撤兵したのである。明治新政府はフランスの澎湖島占領を、軍事的圧力で講和を促す鮮やかな戦略の勝利と受け止めたようだ。歴史を振り返れば、17世紀初め、明国との貿易を求めて拒絶されたオランダは、1622年に澎湖島を占領し砦を築いた。これに動揺した明国はオランダと戦火を交え、1624年に澎湖島を返してもらうかわり台湾をオランダに与える、との協定が成立した経緯がある。
清朝の断末魔3 日本軍の北京攻略作戦
さて、講和会議を筋書通りに進めた日本の運命が突如暗転する。下関会議さなかの3月24日、宿舎に引き上げる途中の李鴻章が、警護の隙をついた26歳の日本人暴漢に短銃で左ほほを撃たれるという、とんでもない事件が起きてしまったのだ。弾丸は目の下から鼻の奥に達して止まり、命はとりとめた。日本の外交的大失態である。形勢は逆転。日本政府は28日、病床の李鴻章を見舞って清と休戦することを約束、ただし台湾、澎湖列島およびその近海に展開する遠征軍は除いた。両国は3月30日、休戦日数を3週間に限った条約に調印したのである。この後、全権を引き継いだ李経方が交渉の表に立ち、交渉を重ねたが、日本が求めた台湾割譲に対し、戦地になっていない台湾の割譲は「非理」であると食い下がった。そこで日本は4月13日に宇品港から直隷決戦への増援軍を派遣。日清戦争のシナリオを書いた陸軍参謀本部次長の川上操六は直隷決戦、つまり首都北京の攻略を主目的に作戦を立案しており、これに沿って駒を進めようとしたのだ。李鴻章は直ちに北京に電報を打つ。北京が攻め落とされればクーデターさえ起きかねない。清朝の主戦論者たちはようやく矛を収め、17日に講和条約(下関条約)を締結するに至るのである。
条約の第一条は「清国は朝鮮国の完全無欠なる独立自主の国たることを確認する」を掲げ、清国と朝鮮の冊封関係を終わらせるという日本の開戦目的は達せられたはずだった。ところが第二条で「(大連や旅順がある)遼東半島、台湾とその付属諸島、澎湖列島」の割譲が決まり、国際社会に衝撃が走った。日本が世界に示した戦争の大義を大きく逸脱し、広大な領土割譲が決まったからである。イギリスやフランスにとって、清国との戦争は開港による貿易拡大が主目的だった。ところが日本は領土を求めたのである。日本は重慶、蘇州、杭州などの開放、開放都市での製造業の自由など経済的要求も実現させたが、イギリスが得た香港や九龍半島と比べはるかに広大な領土獲得は、強欲と批判されても仕方あるまい。遅れて列強の仲間入りを目指した日本は、通商という低コストで国を富ませる道ではなく、他国の領土を奪い取る覇道を選んだ。明治の若い政権には外交の知恵の蓄積がなかったと言うべきか。軍事コストだけでなく国際社会における政治的コストを慎重に検討したとは思えず、尊大な清国への感情的な「膺懲=ようちょう。懲らしめ」思想が戦争の動機のようにも思える。景気の良い主戦論に引きずられ、日清戦争の勝利の方程式が日本陸軍に組み込まれ、後世に災禍をもたらすことになるのである。
老獪な李鴻章 策に溺れる
伊藤博文は老獪な李鴻章が何を企んでいるか気づいていた。李鴻章の策略とは「夷を以て夷を制する–自分の手は汚さず、外国勢力を使って眼前の敵を押さえる」という伝統的な戦略である。李鴻章は清の軍事的非力を良く認識していた。日清の開戦前、イギリスに日本の出兵阻止を要請し、ロシアには日本の朝鮮からの撤兵の調停を求めた。両国が開戦するとイギリスとロシアは中立を宣言したが、11月には英・米・独・露・仏の各国公使に「朝鮮の独立・賠償支払いを条件として」調停を求める。さらにロシアとの結びつきが強い李鴻章は、交渉の経過を列強に漏らしながら、特にロシアに日本への領土割譲を覆させようと図ったのである。
日清両国が講和条約を締結してからわずか6日後の4月23日、ロシア、ドイツ、フランスの公使が日本外務省を訪れ「日本の遼東半島占領は、清国の首都を危うくし、朝鮮国の独立を有名無実化し、極東の平和に障害を与える」と勧告し、遼東半島の放棄を求めた。ロシアが主導した三国干渉である。アメリカ海軍大学教授のサラー・ペイリンは『清日戦争1894-1895』で「ロシア海軍は1895年3月に地中海艦隊を極東に移し、条約批准時の4月20日には太平洋に30隻の軍艦を配していたし、陸軍も満洲方面へと移動させていた」と書いている。三国干渉は、武力による威嚇であり、日本は薄氷を踏みながら戦争をしていたのだが、国民にはそうした事実は伏せられていたのである。
ここに至って日本は遼東半島を清国に返還した。李鴻章の論見通りかというと、実はそうではない。清が強国なら李鴻章の戦略は成功しただろうが、既に清は落日国家、足許を見られた。ロシアは日清の講和成立から5カ月後の9月、皇帝ニコライ二世の戴冠式に出席した欽差大臣・李鴻章に、清国の領土である満州内でのロシアの鉄道建設 を認めさせ、翌年9月に「東清鉄道密約」を締結した。ロシアは満州北部を東西に貫通する約1500キロメートルの東清鉄道を建設し、首都ペテルブルグと太平洋側の唯一の不凍港、ウラジオストックとをシベリア鉄道で結んだのである。次いで清に遼東半島 の租借を強要し、東清鉄道の中央部の都市ハルピンから南へ長春、奉天(瀋陽)、大連、旅順 へと延びる南部支線約770キロメートルを敷設、旅順を強固な要塞で固めた軍港に、大連を商業港にし た。李鴻章は策に溺れ、ロシアを領内深く引き込んでしまったのである。李鴻章がロシアから巨額の賄賂を得たとの説もある。
日清戦争は近代国家・日本の対外戦争の原点である。重要な天然資源があるわけでもない遼東半島を求めてロシアを挑発し、日露戦争、革命後のソ連・シベリアへの出兵、満洲とモンゴル境界でのノモンハン戦役と、戦争の目的があいまいで、とかく軍が暴走しがちな戦争を日本は戦い続ける進路を選んでしまった。その意味でも、日清戦争はその後の世界を揺るがす世界史的な戦争だったと位置づけられるべきだろう。
こうして、からくも手に入れた第一目標ではない新領土・台湾へと日本は勇躍乗り出す。初代総督樺山資紀は日清戦争で海軍軍令部長、作戦立案と指揮を務めた人物だが、眼前にとんでもない運命が待ち構えているとは、知る由もなかった。
(文中敬称略)
〔主な参考文献〕
◎『蹇蹇録』陸奥宗光(国立国会図書館デジタルコレクション)
◎『晩清史』胡禮忠、戴鞍鋼(中華書局)
◎『李鴻章──東アジアの近代』岡本隆司(岩波新書)
◎『日清戦争──東アジア近代史の転換点』藤村道生(岩波新書)
◎ “The Sino – Japanese War of 1894-1895” S.C.M. Paine(Cambridge University Press. 2003)