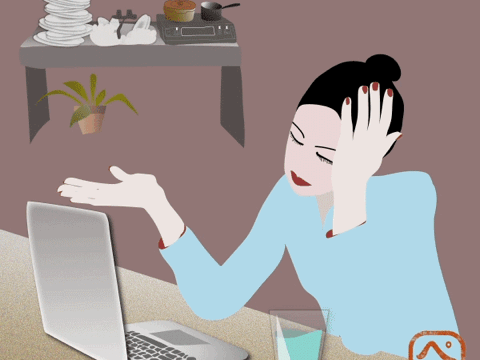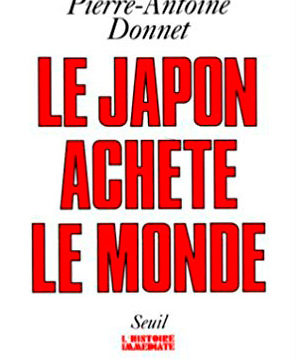優秀な中国の旅行代理店
過去3回の中国・チベット旅行のうち2回は北京の旅行代理店で旅程を組んでもらった。中国との往復航空チケットだけ自分で手配し、訪問希望地を伝え、後の手配は全てお任せ。ホテル、観光名所のチケット予約、移動手段の確保など、全て事前にやっておいてもらう。やりとりは電子メール、言葉は英語、支払いはクレジットカード。完全カスタムメイドなのにわずか3日ほどでアレンジが終わる。
中国到着後は一人のガイドが全旅程をアテンドするのではなく、移動ごとにガイドと運転手がリレー交代する。高速列車に乗るときには、プラットフォームまでガイドが見送ってくれ、目的地に着くと新しいガイドが現れる。車の長距離移動にはガイドはつかず、中国語オンリーの運転手と水入らずになる。朝、昼、晩の食事は全部、代金に含まれている。中国の都市はどこも巨大で、空港や鉄道の駅は中心地から離れていることが多い。それに観光名所はどこも中国人が圧倒的で外国人向けにはできていない。ひとたび、大都市を離れると、中国語が分からなければ赤ん坊同然。ガイドと運転手だけが頼みの綱だ。
旅行を始めると、あらためて北京のネット旅行代理店の周到なコーディネートぶりに感心する。それを可能にするのは中国全土の緊密な均質的サービスネットワークだ。日本基準よりは荒っぽいが、無駄で過剰なサービスはなく、杜撰なミスや行き違いを恐れる必要もない。どこに行っても支払った対価に見合ったサービスが効率的にきちんと提供される。
各地で案内してくれるガイドと運転手は皆フリーランスだ。人となりや雰囲気はそれぞれだが、きちんとサービスして、もらった金の対価を提供しよう、できればチップをもらおうとする努力は共通している。飛行機の遅れ、道路の渋滞、観光地の入場制限や要人訪問に伴うホテルの変更など、広大な中国旅行にリスクは多い。ガイドは仲間同士で絶えずリアルタイムの情報を交換しながら、刻々と変化する状況に自律的かつ柔軟に対応する。実際、わたしたちの旅行にもいくつかハプニングがあったが、ガイドの対応は的確だった。
石原さとみ似のリリー
「ハロー。マイネーム・イズ・リリー」——彼女が今回、東チベットを案内してくれるガイドだった。リリーは正真正銘の中国人。石原さとみ似の小柄でスタイリッシュな美女だ。
観光ガイドはハードな仕事だが、とりわけ、中国の辺境地域のガイドは過酷だ。大都市では客に土産店で買い物させたり観劇させたりするとガイドはキックバックがもらえるが、辺境ではそうした追加収入の機会もないから効率が悪い。客の飛行機は頻繁に遅れ、到着が深夜になることもしばしばだ。毎朝、出発は早く、帰りは遅い。移動範囲は数百キロにも及び、一旦、出発すれば、数日間は自宅に戻れないのが普通だ。道中は事故の危険もあり責任は重い。外国語で地方の歴史や文化を説明し、外国人の突飛な質問にも臨機応変に答えるにはハイレベルの語学力、知識と教養が必要だが、同時に早朝から博物館のチケット取りに並ぶような泥臭さや体力、不測の事態にはすぐに予定変更する機知や決断力も求められる。
外国人に日常的に接しているせいだろうか? リリーには地方都市の中国人からイメージされる野暮ったさがなかった。広尾の女子大キャンパスや丸の内のビジネス街にいても違和感がないだろう。それでいて、日本人とは異質な中国的タフネスも持ち合わせていた。
「これまで中国の省は全部、仕事で旅行したよ。外国で行ったことあるのはオーストラリア。一番、住みたいところ? 杭州。すごくいいところだよ」
リリーの憂鬱
「ねえ、東京のマンションて、いくらぐらいするの?」
リリーとの旅行の2日目。臨夏回族自治州の農村地帯に突如、現れたマンション群を車窓から驚いて眺めているわたしたちに助手席のリリーが尋ねた。
「大きさによるけどね。300万元くらいかな」
「ふん。それって日本人の年収の何倍くらい?」
「まあ、稼ぎによるけど…10倍くらいかな」
「うわあ、いいなあ。中国は30倍くらいなんだよ。ひどいでしょ。だからすごく働かないといけない」
若く見えるがリリーは28歳だという。蘭州で生まれ育ち、地元の大学を出た後はずっと外国人向け旅行ガイドをしているそうだ。独身、親と同居、家事や料理は母親にお任せ。わたしたちの払った旅行代金から逆算すれば、日本の同年代の事務職よりはるかに報酬は少ないだろうが、お洒落な服を買うには困らなそうだ。
若い世代のせいか、他のガイドと比べて訛りのない綺麗な英語を喋る。愛らしい顔だち、ファッショナブルな外見、頭の良さ。上海の外資系金融機関や茅場町のIT企業にいても不思議でなかった。だが、ここは人口13億人の国。競争は日本の10倍はきつく、コネでもない限り、地理移動しながら社会階層を上っていくのはそう簡単でないのだろう。
華奢で都会的な雰囲気のリリーにわたしたちは親近感を持った。リリーはこの先、この厳しい職場で過酷な長時間労働を続けながら、結婚して子供を育てていけるのだろうか? 他人事ながら心配になった。
リリーはクールに言った。
「そうよ。中国じゃ、結婚、出産は大変よ。だって、不動産買うのにすごく働かなきゃならならないもん。でも働いてばっかりいたら、子供産めないよ。だから、中国はもう一人っ子政策がないけど、どんどん子供は少なくなる。日本と同じね」
客にとって安価で快適なサービスは、こうした過酷な労働に負う部分が大きい。中国社会の急速な発展の光と陰、残酷な矛盾は目の前の小さなリリーにも集約されていた。
チベット人の村に到着
次第に草原が拓け、車がチベット人居住地域に差し掛かった。
見ると、草原には柵が設けられており、その向こうにレンガ色の村落が見えた。
リリーは乾いた調子で紋切り型のガイドをした。
「チベット人遊牧民が放牧して家畜が草を食べ尽くしてしまうから、遊牧をやめさせて定住させる政策が取られてます。この村は政府が新しく作ったもので、チベット人は補助金をもらって格安で住めます。電気も水道もあって快適で清潔です。ここに住むか住まないかは遊牧民自身が決めることができます」
なるほど、これが悪名高き遊牧民の定住政策か。
中国政府は過放牧による草原砂漠化を防ぐため、ここ十数年、チベット人遊牧民の遊牧を規制している。だが、インドのチベット亡命政権によれば、砂漠化の本当の原因は遊牧民ではなく、漢民族の移住による人口増加や工業化だという。遊牧民を定住させる中国政府の真の目的は、2000年続いてきたチベット人の伝統的生活様式の抹殺だ。定住政策は即刻止めて、むしろ、中国政府は草原の管理を完全に遊牧民に任せるべきだと彼らは主張している(参照)。
レンガ色の埃っぽい村落に入ると、伝統服を着た日焼けしたチベット人がしゃがんで所在無げにタバコを吸っていた。そこに漂う無気力な空気はアメリカのグランドキャニオンで見たネイティブ・インディアン、ホピ族の居住区に漂っていた空気と似ていた。あるいは、マレーシアの瀟洒な避暑地キャメロンハイランドに突然現れたオランアスリ(マレーシアの山岳民族)をも彷彿とさせた。いずれも物質的優位性を持った征服民に先祖の地を追われ、伝統的な生活様式や生きていく糧を失い、かといって近代社会にも同化、適応しそびれた人々だ。
「遊牧は止めて定住したチベット人は、どんな仕事をしているの?」
わたしはリリーに聞いた。
「観光業です。チベットは空気が綺麗で夏、涼しいけど、中国は空気悪いし、暑い。だから、中国人、チベットにどんどん訪れてます。単にお寺を見せるだけじゃなく、観光客を馬に乗せたり、テントで遊牧民体験させたり、踊りを見せたり、そういう新しい観光が生まれてます」
たしかに、ロードサイドには観光用のテントやレストラン、チベットショーなどの看板などが散在していた。だが、それらは一様に薄汚れていて覇気がなく、一体、営業しているのかしていないのかすら、わからなかった。
わたしたちもそのうちの一つのテントで食事をする予定だったらしく、リリーはあるテントの前を通ると、道傍に車を止めさせた。そして、「ここで待っていて」と言って自分だけ降りると、ドラム缶に薪をくべて湯を沸かしている太ったチベット人中年女性に駆け寄った。顔見知らしく、リリーを見ると中年女性は銀歯を出して笑い、彼女の中国名を呼んだ。
サービスの綻び
車に戻ってきたリリーはため息をついた。
「食事の用意、できてない。チベット人、ほんとにトロい。いつだってそう。何度言っても理解しない」
それは東京の人が田舎の悠長な時間感覚に嘆息するのと似ていたかもしれない。チベット人が食事を作っているあいだ、手持ち無沙汰なわたしたちはリリーにいくつかの質問をした。だが辺境ガイドのくせに、リリーはチベットに関心がなく、その文化や風習についての説明は曖昧で適当だった。
一方、わたしたちも徐々にリリーのイライラやチベット人に対する冷淡さの理由がわかってきた。訪れた東チベットの草原のチベット人の店は、どこもまるで商売気がなく、サービスもおざなりだった。「客は神様。金をもらったら確実に見合った対価を提供するという中国の鉄壁ルールもここまで来ると綻びが見えた。
金を出したい観光客はいるのに、なぜチベット人は金のために一生懸命働かないの? リリーに尋ねる代わりにわたしは自分で考えてみた。
遊牧という先祖代々の生業を不本意な形で奪われたから。観光という押し付けられた仕事には意味が感じられず、やる気を持てないから。
あるいは、政府からの補助金のおかげで本気で稼がなくても生きていけるから。
あるいは、もらった金に見合うサービスをきっちり客に提供するという発想がそもそも遊牧民社会にないから。
あるいは、チベット人は骨の髄まで漢民族を憎んでいて、命令されるのを嫌がるから。
おそらく、これら全てが入り混じっているのだろう。鉄柵で囲まれた草原、殺風景な村落、薄汚れた観光用アトラクション。ここが将来、スイスのような一大観光地に発展する姿を想像するのは難しかった。たとえ発展するとしても、それは中国人が中心となった発展だろう。もし中国人が経営する草原レストランがそこにあれば、リリーは迷わず、そちらと取引するはずだ。チベット人はヤクやテントと一緒に、ただ草原を彩るインスタ映えする被写体であってくれさえすればいい。それが商売をする側の本音だ。
草原の憂鬱
苦しみながら社会の掟に服している人たちは、それに服さない人を憎む。それがリリーのチベット人に対する本音の感情かもしれない。
「はっきり言って、あの人たち、恵まれてる。あんな家、政府に建ててもらって。こっちは小さなマンションでも年収の30倍なのに。毎日、ぼーっと祈ってばかりで仕事もしない。これ全部、あたしたちの税金だよ。ほんとに呑気なもの」
リリーは吐き捨てるように言った。陽に照らされた痩せたリリーの目にはクマができていて、最初に見たときより随分、疲れて見えた。
「思い切って、チベット人のところ、お嫁に行ったら? 家は広いし、きつい仕事や住宅ローンと無縁の生活が送れるよ」
わたしは半分本気、半分冗談で言ってみた。
一瞬、リリーの顔に驚きと不快の表情が浮かんだ。が、すぐに無知な外国人の下手なジョークだと知って笑った。
「ホァーイノット。ヤクの乳絞りしてね。こんな風に踊っちゃったりしてね!」
リリーはチベット人の踊りを真似て、自分のシャツの袖をつかんでクルクル、辺りを剽軽に飛び回って見せた。
リリーは愛らしく健気だったが、同時に残酷で尊大だった。
もちろん、リリーがここのチベット人遊牧民と恋に落ちて結婚し、20年後、草原のレンガ住宅で子沢山の主婦となっている姿は想像しにくい。
同じように、このレンガ村に住むチベットの遊牧民がリリーに惚れて、追いかけて都市に引っ越し、30年ローンを払いながら身を粉に働く姿も想像できない。
水と油。異なる時間感覚、異なる倫理、異なる生き方。それは憧れにつながることもあれば憎しみにもつながることもある。秘境チベット、牧歌的な草原で実際に繰り広げられているドラマは空の色とは裏腹に陰鬱で物悲しかった。