回る人たち
チベット人の習俗の大きな特徴の一つは、「回ること」だ。チベット語で「コルラ」と言う。寺の境内の周りを回る、バルコル(ラサの巡礼路)を回る、仏塔の周りを回る。据付けられたマニ(祈祷)車を次々と回しながら、あるいは、手に持つデンデン太鼓のようなマニ車を右回りに回しながら。あるいは、数珠を操り、経文を唱えながら。五体投地をしながら。
有名なカイラス巡礼も「回る巡礼」だ。巡礼者はカイラス山の中腹52キロの巡礼路をひたすら、回る。一回、回る人もいれば、数回、回る人、数十回、数百回、回る人もいる。何回でもいい、回ることが目的なのだ。聖地を回り功徳を積めば、来世でより良く生まれ変われると巡礼者は考える。距離やスピード、目的地に到達するかどうかなど、目に見える客観性は意味を持たない。
チベット人の円環志向はユニークだ。日本のわたしたちは、神社では本社や奥社に続くまっすぐな参道を歩き、本殿で拍子木を打つと踵を返し、来た道を引き返す。仏教のお寺も日本や中国のものは円環的な巡礼路がない(あるいは四国巡礼だけは円環的かもしれない)。インドのヒンズー教の世界観は円環的だといわれる。マンダラはインド起源といわれ、円環的なカイラス巡礼はインド人もやる。だが実際、ヒンズー寺院でコルラしている人はあまり見たことはない。欧米のキリスト教の教会でも、中東や東南アジアのモスクでも人は回らない。唯一、イスラム教の一派であるスーフィー教徒の人々がグルグルと回って踊るのを知っているが、果たしてこの回旋舞踊とチベット人の円環志向に関連があるのかないのか、よく分からない。
わたしも旅行中はチベット人に混ざり、クルクル回し、グルグル回った。寺の仏塔の周りは真剣に経文を唱えてながら行く人も、肩を並べ陽気におしゃべりに講じる群れもあるが、途中で立ち止まる人、ダラダラ、ノロノロを歩く人はいない。老人も意外なくらいキビキビと早足で歩く。彼らを真似て早足で歩くと、息切れするほどではなく心地良い疲れを覚える。お香の香りを嗅ぎながら、手と口を動かしながら歩けば、いつしか頭が空っぽになる。機能性重視の無機質な日本のウォーキング・エクササイズより、よほどリラックス効果は大きい。
「いいね。日本でもやりたいくらいだね」——夫もすっかりコルラにはまっていた。
△これは昨年旅行した東北チベット、アムド地方の名刹、ラプラン寺のコルラ(撮影/筆者)
イェルパ寺の参拝
セラ寺、ジョカン寺など、ラサの名刹は、巡礼者と観光客の入り口や参拝の時間帯が違う。巡礼者と観光客は別々の場所から入り、違う順路を回る。観光客はガイドから仏像の謂れやお寺の歴史のレクチャーを受ける。
こうしたガイド付きの寺社拝観は日本でもおなじみだ。ガイドの話は、はじめのうち興味深くても、じきに退屈してしまう。仏像の名も、仏教の象徴体系も、建築様式も、いつの間にか左の耳から右の耳に抜ける。はじめは新鮮だったチベットの仏像もタンカも密教法具も飽きてきて、しまいにもうたくさんという気分になるのは、京都の寺巡りやヨーロッパの教会巡りと同じだった。
ところが、チベット人巡礼者に混じりチベット式「円環」拝観をしたらそれまでとまるで違う体験になった。
イェルパはラサ郊外、東北方面に車で1時間ほど、標高4,200メートルのところにある。岩に掘られたこの洞窟寺院は歴史的な成就者が修行した由緒ある場所であり、チベット人にとって重要な巡礼地の一つだ。わたしたちが訪れた日は、「ツェチュ(チベット暦7月10日)」の法要の大タンカ開帳式の日だった。通常の観光コースから外れているせいか、イベント日なのに観光客はわたしたちだけだ。大勢の巡礼者に混じってタンカを見物し、草原でピクニックをした後、寺の内部に入った。
イェルパは敦煌の莫高窟などと同じように、いくつもの石窟の小部屋でできている。拝観料はなく、仏像には英語や中国語のキャプションもなく、境内に「禁煙」「撮影禁止」などの札もない。そこは観光化していないチベット人の信仰の場所だった。
「ここが、グルリンポチェが修行をされた部屋です」、「これは文成公主が使った台所」、「これはダライ・ラマ5世とその従者たちを描いたタンカです」——はじめのうちは他の名刹めぐり同様、案内のチベット人ガイドが説明してくれていた。だが、いつしか、ガイドは説明を止めてしまった。押し寄せる巡礼者の波に押し流され、とても一つの場所に立ち止まっていられなくなったからだ。それに、巡礼者の経文の声が轟音のように響く狭い石窟内では、説明の声もかき消されてしまう。いつの間にかガイドはガイドであることを止め、運転手と一緒になって熱心に祈りを捧げ始めていた。
わたしと夫も、周りを見よう見まねで百元札を仏像の台座に置き、周囲に散乱している他の人が布施した少額紙幣をお釣りとして拾い集めた。そして、新しい部屋に入り、仏様を拝むたびに、それを一枚一枚、ねじり込むように置いていった。途中から、羞恥心も周囲への遠慮も捨て、思い切って「セムチェンタムチェー、デーワーヨンガショー(あらゆる生きものが幸せでありますように)」とチベット語で繰り返してみた。
岩場に張り付いた急な階段を登ったり降りたり。石窟の小部屋は果てしなく続く。岩に掘られた石窟の数は合わせて百を超えていたかもしれない。わたしたちは次から次へと部屋を移動した。
千手観音、緑ターラー、文殊菩薩に弥勒菩薩、阿弥陀如来に金剛手、地蔵に虚空蔵に毘沙門天に歓喜仏。ミラレパ、グルリンポチェ、アティーシャ、ソンツェンガンポに大黒天、パルデンラモ…。最初のうちは、飛び込んでくる視覚情報を過去の学習知識とつなげて記憶に止めようとした。
だが、次第に虚しくなってきた。人並みに押され、仏像のズームインとズームアウトを果てしなく繰り返すうち、頭で情報を整理することができなくなった。そもそも、そんな風にいちいち立ち止まっていたら、とても巡礼者の波の中を進んでいけない。
どのくらい歩いただろうか? 部屋の出入りの単調な繰り返しに、だんだん手足が痺れて感覚がなくなり、クラクラと軽くめまいがしてきた。進んでも、進んでも、極彩色のサイケデリックな金銅仏のズームインとズームアウトのパターンが続く。バターランプとサン(香木)の匂い、低く響く人々の経文を唱える声、長年の人の手垢で磨耗した岩肌。周囲の景色はバターランプの炎にヌメヌメと照らし出されて揺れている。
果てしもない巡礼路そのものが人生であり、コルラやマンダラは生きることそのものなのだ、と思った。チベット人的には、人生は今生で死んでも終わらず、意識は六道輪廻の円環をぐるぐる回り続ける。現れては消える仏像、忿怒相や柔和相。それらは、その時々の人生の局面の様相を示すシンボルだ。そもそも人の一生にはキャプションも注釈もないのだから、仏像にキャプションは要らない。
札ビラを投げ出せば投げ出すほど、日頃の姑息な計算高い了簡から遠ざかって、解放された。次第に理屈でものを考えなくなり、時間の感覚がなくなり、自分が自分だという感覚が薄れていった。
もしかしたら、五十余年の人生で初めて、わたしはちゃんとしたお寺参りをしたのかもしれない。
驚くべき信仰の炎
イェルパはリアルタイムの中世的信仰の場だった。ダンプカーも電気ドリルもダイナマイトもなかった時代の高地の岩場にこれだけ多くの石窟を掘り、無数の金銅仏を延々と設置し、荘厳し、補修し、維持管理するには、どれほどの集団的な意志と忍苦、労力を要しただろうか。観光地化が進むチベットだが、今もこうした修行場、巡礼地はたくさん残っている(もしくは壊されたが徐々に再建されている)という。
チベット社会の叡智、富、知識の大部分はイェルパのような宗教施設や僧院に集約されてきた。中国占領前のチベットは国民の十人に一人が僧侶、尼僧だったという。生産力に乏しい高地の遊牧社会がそうしたシステムを営々と養い、再生産してきた。原動力となったのは、およそ想像しがたいほど深く強烈な信仰のエネルギーだ。
では、チベット人がなぜそれほど信仰にのめり込んだのかといえば、心身を使い尽くす帰依が強烈な多幸感をもたらすものだったからに違いない。
過酷な自然条件下の短い人生、単調な生活。労苦や病苦、社会で生きることの桎梏、愛欲の煩悩や執着。帰依の対象に文字通り全てを投げ出す心身が一体化した祈りは、俗世を忘れさせ、脳をエンドルフィンで満たし、言い知れぬ平穏と幸福感をもたらす。信心深いチベット人は、死後、全ての財産を寺に布施するという。そして、まるで手で蝿を追い払うように、来る日も来る日も数珠を繰り、マニ車を回しながら、一瞬一瞬の邪念や煩悩を脳内から静かに追い払う。
骨の髄まで仏教に浸ったチベット人にとって、単なる物質的向上はあまり意味がなかったのだろう。なんと1940年代までチベットには移動、運搬用の車輪が存在しなかったという(ハインリッヒ・ハラー著『チベットの七年』より)。これほど法輪やマニ車が好きな人々なのだから、作り方を知らなかったはずはない。鎖国をしていても外部との交流はなくなっていなかったから、車輪の便利さは知っていたはずだ。だが、物質的向上にさして関心がなかったゆえ、それを作らず、使わなかった。
そんな円環文化に、中世の眠りからとうの昔に覚め、進歩の道をまっしぐらに走る巨龍の文化が衝突したらどうなるか?
それが中国によるチベット支配だ。占領から数十年、被征服民は圧倒的な力の差で征服民にねじ伏せられたままだ。チベット独自の社会制度は完膚なきまでに破壊され、彼らは父祖の地で二級市民の地位にある。だが、その中世的信仰の炎は征服民の当初の予想をはるかに超えて荒々しく燃え続け、未だ鎮まる気配はない。今回の旅行はそんな炎を感じる旅でもあった。



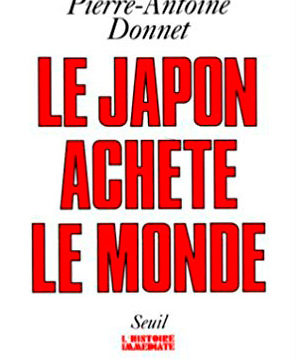






























![左小祖咒【万事如意 Live】正宗[日中字幕版]](https://shukousha.com/wp-content/uploads/2014/02/Zuoxiao_MV01-100x62.jpg)
