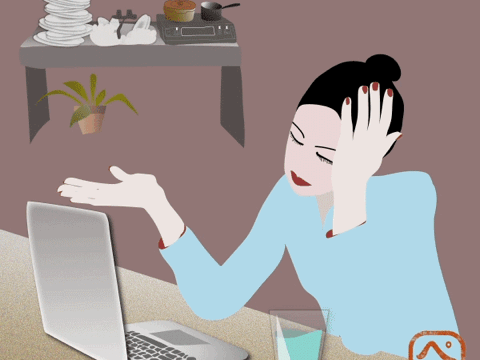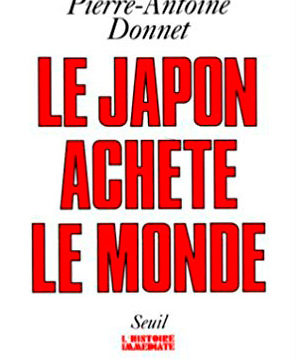一昨年、91歳で大往生を遂げたわたしの義父は商社マンだった。
日本が独立を回復する1年前の1950年。戦後一番乗り、弱冠25歳でGHQの許可を得て東南アジアに渡った。シンガポール川の河口、ボートキーに並ぶ華僑のショップハウスをドブ板営業して松坂木綿を売り、外貨を稼いだという。
60年近くの時を経て彼の地を再訪した義父はシンガポール川河畔に立ち尽くし、つぶやいた。
「わあ。変わったなあ。何にも残っとらんけど懐かしいなあ。サヤオランジュプン。ラアダラカイン。ムラムラ……」
「お義父さん、何ですかそれ? マレー語?」
「セディケ、セディケ」
どうやら当時の義父とボートキーの華僑商人の商談はマレー語だったらしい。
だが残念なことに、シンガポールを再訪した義父のマレー語はあまり現地で通じなかった。義父のマレー語が錆び付いていたせいではない。60年のあいだにシンガポールで普通に通じる言葉がすっかり英語に変わってしまっていたのだ。
英語と中国語が公用語のアジア唯一の国
シンガポールには4つの公用語(マレー語、英語、中国語、タミール語)がある。公共空間では英語が圧倒的に優勢である。
英語話者には実に快適な場所だ。だからアジア経済にアクセスするゲートウェイとして、欧米企業にとって最高の立地である。
「租界地の雰囲気を残す、欧米人にやさしいアジアの都市」としてシンガポールは長く香港と肩を並べていた。だが21世紀になり香港が徐々に英語が通じにくくなりつつあるなか、シンガポールの頭が一歩抜きんでる傾向にある。欧米企業のアジア太平洋地域の本拠地は、税が安くて英語が通じ、安全で清潔なシンガポールにますます集中している。
そして、中国語もかなり通じるし、学びやすい。
ジム・ロジャースという往年の有名ヘッジファンド・トレーダー兼冒険家は、中国語が学べるという理由でシンガポールに移住した。60歳を過ぎて子宝に恵まれた彼はシンガポールに居を移し、二人の娘を現地校に通わせ、英語と中国語のバイリンガルに育てている。
中国本土からの高度人材や富裕層の移民も増えている。香港の俳優ジャッキー・チェンや中国の俳優ジェット・リーなどもシンガポール市民であるらしい。中国人にとってもシンガポールはストレスなく生活できる場所なのだ。
もともと複雑な言語環境
世界の二大言語である英語と中国語で生活ができるグローバル都市という稀有の環境はゆっくりと自然に生まれたものではない。建国以来、シンガポールは教育とメディアを通じ、世界でも稀な言語エンジニリングの実験を繰り広げてきた。
その正史は1819年に英国人スタンフォード・ラッフルズが島を大英帝国の東西貿易の拠点としたことに始まる。
今日、シンガポールは中華系人口が国民の7割強、マレー系が1割5分、残りがインド系という多民族国家だ。この人口構成はイギリスの植民地だった20世紀初頭から変わっていない。
シンガポールのインフラとプラットフォームを作ったのがイギリス人だとしたら、今日、そこに住む国民は、そうしたプラットフォームに惹かれて移住してきた人たちだ。
シンガポールが発展した19世紀、アジアには近代的な国民国家がなかった。だからシンガポールにきた人にも、自分は「インド人」「中国人」「マレー人」などの自覚がなかった。移民のアイデンティティーはあくまで宗教や「お国言葉」で規定されていた。
「お国言葉」はきわめて多様だった。
- 中華系:福建語、広東語、客家語、海南語、潮州語など、華南諸地方の「方言」
- インド系:タミール語、パンジャブ語、ヒンディー語、ベンガル語、グジャラート語などの異なる言語系統
- マレー系:アチェ語、ブギス語、マカッサル語、スンダ語、イバン語など
もちろん、この3つの系統からはみ出てしまう言語系統の人たち(アラブ人、ペルシャ人、ユダヤ人など)もたくさん住みついていた。
「お国言葉」別のアイデンティティは移住時期や職業、所得の違いでさらに細分化されていた。住む場所と生活様式がちがう人々に同胞意識はなく、従うべき掟もまちまちだった。
建国後の苦労
第二次世界大戦後、そんな植民地からイギリス人がいなくなった。自治やマレーシア連邦への参加を経て、一種マネジメントバイアウトのような形でシンガポールは「国」になり、住民は「国民」になった。
新政府は国民を便宜上「中華系」「マレー系」「インド系」「その他」に分けた。そして、旧宗主国の言語でビジネスに使われる言葉の「英語」に、各民族を代表する言語「中国語」「マレー語」「タミール語」を加え、シンガポールの4つの公用語とした。
だが、現実にはそれら公用語は多くの人にとり自らのアイデンティティと一致しない言語だった。
インド系の公用語が「タミール語」とされたのは、シンガポールには歴史的に南インドのタミルナドゥ州からわたってきた人が比較的、多かったからだ。北インド出身の人々にとって、タミール語は文字からして異質で、英語以上に親近感のわかない言語だった。
一方、中華系の公用語である中国語は、「マンダリン(北京官話、現在の中華人民共和国の公用語)」と決められた。だが国民に馴染みがないという点ではインド系にとってのタミール語と五十歩百歩だった。ほとんどの中華系シンガポール人は華南出身者なので、華北の言葉であるマンダリンを耳にしたことも口にしたこともなかったのだ。
とりあえずこの4言語を公用語にしたのはあまりに雑多な国民を抱えたシンガポール政府の窮余の策だったといえる。4つにまとめなければ収拾が取れないほど新国民のアイデンティティはバラバラだった。
その後、「4つの公用語の学校」が作られた。最初はどの学校も算数と理科が英語で教えられ、それ以外の科目は民族公用語で教えられた。親は英語、中国語(マンダリン)、マレー語、タミール語の学校から自分の子供の行く学校を選択できた。
だが、英語以外の学校はどれも国民に不人気だった。「民族の公用語」と「お国言葉」のギャップは先ほど述べたとおりだ。だから、英語学校以外の学校に通う子供は、科目の学習にくわえ、実質的に二つの新しい外国語を同時に学ぶことになった。
結局、シンガポールの公教育は基本的に「全部英語(+日常生活に困らない公用語)」に一本化された。そうした方針は、欧米の外資系企業の誘致のために国民の英語力向上を図りたいシンガポールの国益にも合っていた。
こうして「外は英語、うちは母語(方言)」というシンガポール独自の言語環境が生まれたのだった。
北京官話を話そう!
この環境にもう一捻りが加えられたのが1979年のことだった。リークアンユー首相の肝いりで「スピーク・マンダリン(北京官話を話そう!)」キャンペーンが繰り広げられたのだ。
1979年といえば、中国が改革開放路線に舵を切って間もない時期。米中の和解など国際秩序は大きく動いていた。だが後の中国の奇跡の経済成長と大国化はまだまだ予測が難しかった時期である。
だが、リークアンユー首相はすでにその時点で中国が大国となると予想していた。そして、「中国全土の13億人とつながる」ため、感傷を捨て、時間の無駄である方言を使うのを止め、中国語を学ぶときにはマンダリン以外を学ばないよう国民に要請した。
すでに英語を話すシンガポール人の中国語力を向上させることで、自国を未来の大国中国と豊かな欧米間のヒト、モノ、カネの奔流の結節点にしようと目論んだのだ。
中国がシンガポールと協力したいと思うのは、シンガポールが英語を通じ欧米社会とつながっているからです。英語が上手なだけでなく、中華人民共和国の人々とさまざまなトピックスを語り合えるくらいシンガポール人は北京官話も得意なのです。
リー首相は政策の本気度を示すため、30代になってからマンダリンをゼロからマスターした自らの実績を誇示し、人々が慣れ親しんだ福建語や広東語のテレビ放送、ラジオ放送はすべて禁止してしまった。
それにより、多くの中華系の人々が愛着ある母語を使えなくなった。家族の歴史、過去とのつながりは辿りにくくなった。方言しか話さない高齢者が社会から孤立したり、世代間のコミュニケーションがうまくいかなくなったり、様々な問題が起きたらしい。
だが、リークアンユーはひるまなかった。経済発展のために、世の趨勢を見よ、感傷を捨てよ!と国民を叱咤激励した。
英語、ラテン語、福建語、日本語、マレー語、マンダリンの6ヶ国語を習得したリークアンユーは、自分の子供には完璧な英語、マンダリン、マレー語をマスターさせた。
恒産なければ恒心なし
建国から50年あまりを経たシンガポールでは、丸々二世代が言語環境激変の波をかいくぐってきたことになる。メディアと教育のコントロールを通じ、本来そこにあった多様性を殺し、過激な言語エンジニアリングを断行した同国のやり方には諸論あるだろう。
拙速な言語政策のせいで自国民は英語もマンダリンも中途半端だと自嘲するシンガポール人もいる。
だが、今日シンガポールがグローバル経済の結節点として絶妙な立ち位置に立ち、未曾有の経済繁栄を謳歌しているのは事実だ。そこには徹底的に効率性を重視した言語政策の効果もあると考えるのが妥当だろう。
一方、経済的なゆとりができたシンガポール人には、集団レベルで現状をありのままに受け止めた上で感傷に浸り歴史を振り返る余裕が生まれてきた。背伸びの必要がなくなった今、過去を回顧し、失われた過去とのつながりを取り戻そうとする動きが百花繚乱である。
最近のシンガポールでは、プラナカン(インドや中国とマレーとの混血の人々)やユレイシアン(アジアとヨーロッパの混血の人々)の言語、歴史、料理など学ぶムーブメントが盛んだ。
また中心街では、歴史的建造物のリノベーションや飲食店、宿泊施設等へのコンバージョンが進んでいる。2005年にはカンポングラム(マレー系歴史保全地区)にマレー文化遺産センターが、2015年にはリトルインディア(インド系歴史保全地区)にインド・ヘリテージ・センターができた。さらに2017年には数十年ぶりに福建語のテレビシリーズが復活したという。
さらに昨年はシンガポール出身の作家ケビン・クアンによる世界的なベストセラー小説『クレイジー・リッチ・アジアンズ』がハリウッドで映画化された。
映画はアジアを舞台にしたハリウッド流ロマンチック・コメディだが、小説を読むとまた別の肌合いがある。マレー世界にひっそりと生息してきたプラナカンのファミリーヒストリーと独自の文化の襞が繊細に美しく表現されているのだ。
ほぼ全員が英米大学留学体験者で流暢な英語話者である富裕な登場人物の会話には頻繁に福建語、マレー語、広東語のイディオムが入り混じる。そして、それらの言葉のニュアンスが世界の読者に対して章末の注釈で丁寧に解説される。
「日陰のマイナー文化」でしかなかったシンガポール独自の融合文化は今、世界的な発信力をどんどん高め、外国人が魅了するようになっている。そして、それがソフトパワーとなりシンガポール経済をさらなる高みに引き上げようとしているのだ。
生き残りに必死な時代、国民の方言使用を(泣きの涙で)弾圧したリークアンユーも、今日のローカル文化の百花繚乱を草葉の陰で喜んでいるにちがいない。