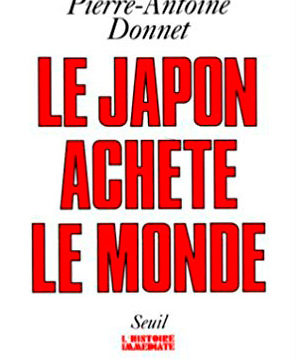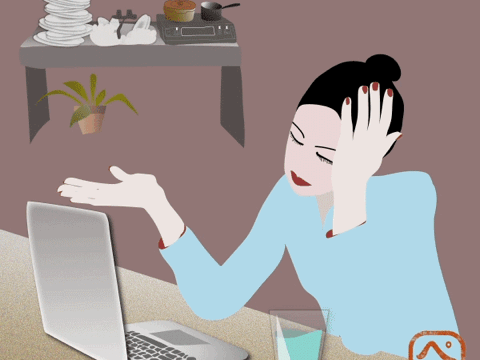国に愛おしさを感じるとは一体、どういうことだろう。それも自分の国ではなく他人の国に。
若くて元気な熱帯の都市国家、シンガポール。日本から飛行機で南に一路7時間。時差は1時間だ。
東京都23区の広さの島に500万人の人口。国といっても外国人だらけ、まるで租界地のようだ。建国からわずか54年のこの歴史的な東西交易の結節点にはあらゆる所得層、人種、国籍、文化・宗教背景の人間がひしめき合って暮らしている。
狭い、といっても島内を埋め尽くす木々の間に高層建築の住居、オフィスが散在しているから、ごみごみした印象はない。熱帯なのに蚊に刺されることはなく雑草もあまり生えていない。道は渋滞しない。バスと地下鉄のほか、どこでもタクシーが捕まる。チャンギ空港から中心部までタクシーで20分程度。電子マネーはそこまで普及しておらず現金とクレジットカードがどこでも通用する。
静と動のコントラスト
高級ホテルや富裕層が住むコンドミニアムにひとたび足を踏み込めば、そこはサマセットモームの小説を彷彿とさせる気怠い植民地の空気が今も漂っている。そんな空間は金が金を生んで回り続けるグローバル資本主義マシンの上澄みに生息する人にだけの特権的世界だ。
シンガポールの魅力はこうした富裕層の住居がゲットー化していないことだ。
コンドミニアムと道を隔てただけの場所には庶民的な団地(HDB)が広がる。そんな団地のマーケットの一つにギンモー市場(Ghim Moh Market)がある。マーケットにはホーカー(特定のメニューに特化した小さな屋台)、屋台レストラン、美容院、医院、エステ、スーパー、八百屋、魚屋、肉屋、パン屋、雑貨屋、衣料店、祭礼用品店、証券会社、銀行、漢方薬店などが立ち並び、およその日常品の買い物はそこで済ませられる。
コンドミニアムやホテルの静謐さと対照に、そこには喧騒と温かさ、効率的で便利な暮らしと相互扶助の人情がある。老人も、共働き夫婦も、子供も、朝から晩まで集っては飲み食いし、おしゃべりする。屋台の主人、商店、客は顔見知りが多い。ギンモーの独居老人はつくづくしあわせだ。
早朝から深夜まで人の流れが絶えないギンモー市場。格差が広がり不動産が年々高騰するシンガポールでホーカーセンターは庶民のオアシス。さまざまな軽食のほか、デザートやドリンクも充実していて安い。ギンモーの全てのメニューにチャレンジするには1ヶ月以上かかるだろう。
ギンモー市場では福建語、タミール語、マレー語、ベトナム語、タガログ語など、エギゾチックな言語が飛び交う。だが誰もが英語を理解するから心配は要らない。流れ者はおらず、窃盗は重罪だから安全このうえない。食品衛生は政府の折り紙付だ。お釣りをごまかされる懸念もない。目を覆うような貧困も悲惨はなく、トイレは洋式で清潔だ。
 1シンガポールドル80円換算で200円の海南チキンライスと100円のサトウキビジュース。チキンライスの発明者は海南島出身の移民という。茹で鳥と揚げ鳥のバージョンがある。マレーシアにもタイにも似た料理がある
1シンガポールドル80円換算で200円の海南チキンライスと100円のサトウキビジュース。チキンライスの発明者は海南島出身の移民という。茹で鳥と揚げ鳥のバージョンがある。マレーシアにもタイにも似た料理があるシンガポールのローカルフードのうち、わたしの一番の好物はフライドホッケンミー。残念ながらフライドホッケンミーの屋台はギンモー市場にはない。バスに乗り、中心部に近いウォータールー通りのホーカーに向かった。
 ストリートフードの王者、フライドホッケンミー。二種類の麺をエビ、イカ、もやし、ネギ、厚揚げなどとともに炒め、スープを絡めた一品に、サンバルブラチャンという独特の辛味発酵エビペーストとライムをかけて食べる
ストリートフードの王者、フライドホッケンミー。二種類の麺をエビ、イカ、もやし、ネギ、厚揚げなどとともに炒め、スープを絡めた一品に、サンバルブラチャンという独特の辛味発酵エビペーストとライムをかけて食べるホッケンは「福建」、ホッケンミーは「福建麺」。19世紀後半、政権が衰退し政情の混乱が続いた清朝末。人口が稠密で貧しい福建省から多くの人が海外に出稼ぎに行き、そこに定住した。多くの人が労働力のみを元手にアメリカにわたり、大陸横断鉄道の建設に従事したが、南洋(東南アジア)のヨーロッパ植民地にわたる人も多かった。こうした事情から、今日の中華系シンガポール人は福建省を父祖の地とする人が多い。
南洋にわたった商才ある福建人が故郷のソウルフードを現地食材を使ってアレンジし、現地の単身労働者向けに屋台で売ったのがフライドホッケンミーである。
フライドホッケンミーはどうやらわが国の長崎ちゃんぽんと兄弟であるらしい。福建人はやはり19世紀半ばに江戸時代唯一の開港地だった長崎に来て商売していたのだった。そういえば、優しい塩味やトロッとした食感に共通点がある。本場福建省の福建麺もいつか試してみたい。
一方、シンガポールのインド系は南インドのタミールナードゥ州出身者が多い。だから、ホーカーではマサラドーサなどの南インド料理が気軽に楽しめる。東京でも最近は南インド風ミールス(定食)の店が増えたが、日本風に上品にアレンジされた料理はシンガポールの野趣あふれるミールスと少しちがう。10年前、初めて指を使って混ぜて味わうインド料理の素晴らしさを体感したが、今回の旅行でもそれを再び堪能することができた。
ローカルとグローバルが一体化した料理を満喫しながら、シンガポールという国のなりたちに改めて思いを馳せた。
人は生まれながらにして不平等
前回、わたしは移民についてのコラムで、
その大半が英国植民地時代に祖国を捨てて移民として島にやってきた人を祖先とするシンガポール人には、人の生まれながらの格差は所与の世界の現実なのだった。
と書いた。
「生まれながらの格差は所与の現実」を強調したかったのだが、「英国植民地時代に祖国を捨てて」というくだりはあまり正確ではなかった。実際には、シンガポールがイギリスの植民地になる19世紀よりはるか前から、マレー半島やスマトラ島などの近隣地域にはいろいろな民族が行き交い、住み着いていた。
マレーの半島や列島地域はもともとは農耕に適さないジャングルだ。島々が内海を囲むように連なっている地形が一種の「地中海」のようなマレー世界は、古来より海上貿易に適した場所であり、マレー人はそれを主たる生業としてきた。
そして、海のシルクロードの通り道にあるマラッカ海峡近辺の寄港地には、インド人、ペルシャ人、アラブ人、中国人など、より高い文明をもった地域の商人が往来し、滞在、定住し、現地の人々と混ざり、さまざまな知識、文化、宗教を伝えた。
チャム、ブギス、アチェ、ミナンカバウ。扶南、シュリビジャヤ王国、マジャパヒト王国、マラッカ王国などがその主役だ。
民族(ネイション)や国境という近代国家の概念がアジアに入ってくるずっと前から、一言で「●●人」とくくることが難しい集団や部族が興亡し、競争し、服従し、協力し、共存してきたのである。
最近、にわかに脚光を浴びているプラナカンというエスニック集団もまた、こうした近代的なネイションの枠組みに収まらない人の例といえよう。
そんな歴史を鳥瞰すれば、ヨーロッパ勢力によるマレー地域植民地化の歴史はほかの地域と少しちがっていることに気づく。
一般に、大航海時代以降のヨーロッパ人による世界支配は、圧倒的な文明力と軍事力を背景にヨーロッパ人が「先住民」を騙し、その土地を奪い、社会制度を破壊し、支配者になったということになっている。
だが、マレー世界の物語はそうした一方方向のものではなかった。圧倒的なヨーロッパ人の力に地元民が押しつぶされたわけではない。19世紀初頭の大英帝国とオランダによる「分割」が起きる前、長くヨーロッパ人は他の商人達と横並び勢力の一つに過ぎなかった。地域にいた非ヨーロッパ勢力だって決して未開で素朴な「先住民」ではない海千山千の商人たちだった。
ヨーロッパ人が作ったのは、安価で安定した港湾使用料、船舶修復技術、治安の良さ、快適な滞在インフラ、言語環境といったプラットフォームとサービスを提供する港だ。そしてそんな港が運行する異民族の船に「選ばれる」ことで支配勢力は栄えたのだ。
もちろん、時代が下れば、ヨーロッパ人の力が他を圧倒したのは事実だ。とくに産業革命以降、その主眼は、土地とヒトと「搾取」し、植民地を自国の工業品の市場とすることに移っていった。
だが、少なくともシンガポールにはそんな搾取すべき資源もヒトもいなかった。そもそもそこはほとんど無人島だったのだ。ジャングルを調査し、都市を作り、多様なヒトを呼び込み、インド、中国などとの三角貿易により膨大なモノとカネが行き交うシステムを整備する基礎を作ったのがイギリス人だったのである。
ヨーロッパ人であろうがなかろうが、誰もが商売目的で島にやってきたという点では同じ穴のむじなであり、同じ穴のむじなである以上、お互いがお互いの「こころ」を理解することができた。
商人が儲けられるかどうかは、時間、運、リスクテイク、勤労、協力などの諸要因で決まる。当然のことながら、発射台(時期、資本の多寡、知力、体力、リスク許容度)がちがえば、もたらされる結果もちがう。
他者の行動規範を理解しつつ、同化は迫らず、差異を所与のものとして平和的交換による共存共栄を図る。
こうした精神こそが今日のシンガポールの国家DNAと言える。
シンガポールは内に民族融和と道徳性を重視しつつ、外には自由競争と結果の不平等を許容する。政府はグローバルスタンダードの法制度が執行される環境を作り、島内を万人にとって快適な場所にする。汚職は少なく、政府は小さい。福祉はあるが所得の再分配は重視しない(相続税がない)。
また国を挙げて必死にヒトとカネ(外資系企業や観光客)を呼び込む努力を惜しまない。ナイトサファリから空中プール、MICE、カジノからデジタルアートまで、無から有を生み出し、弱みを強みに変えていく姿はまるで魔法のようだ。
有能な移民を寛容に受け入れる反面、貧しい国の単純労働者は徹底的に酷使し、使い捨てることにさしたる罪悪感は覚えない。そして、繁栄の基盤である安定と治安のために、メディア規制や個人の自由の抑制を必要悪として認める。西洋市民社会の理念を十分理解しつつも、それをシンガポールになじまないものとして退ける。
「人間は生まれながらに不平等です。それは事実です。不平等は決してなくなりません」と述べる故リークアンユー。生き残りの厳しさと背中合わせの徹底したリアリズム
シンガポールは「明るい北朝鮮」などとも揶揄される。だが、わたしに言わせれば、北朝鮮とシンガポールはまるで異質だ。前者の独裁が、武力を独占した為政者が自らの肥大したエゴと権益を守るためのものだとしたら、後者は丸腰の小国が商売で生き残るための必要悪としての独裁だ。
ラクサ・クッキーとネイションビルティング
恒例の年初や独立記念日のスピーチ。強面の父親と違い、シンガポールの二代目指導者、リー・シェンロン首相は温厚でハンサムだ。リー首相は笑顔で「仲間であるシンガポール市民の皆さん(My fellow Singapore citizens)」と語りかける(そして同じスピーチを完璧な中国語、マレー語でも行う)。
昨年の独立記念日のスピーチでは、6月に歴史的な米朝首脳会談がシンガポールで開催された成果を強調するとともに、会談中にはシンガポール政府から世界の報道担当者にラクサ風味(=ラクサはマレー由来の辛味とココナツ味が混ざったラーメン。典型的なホーカー料理)のクッキーが配布されたことを報告した。
その姿はまるで自社の広報宣伝を先頭に立って行い、その経営姿勢を社員にアピールする中小企業の社長のようだ。首脳会議でワサビ味せんべいを配ったと報告する安倍首相の姿も、キャラメルトフィーを報道陣のワシントン土産に渡したと国民に威張るトランプ大統領の姿もにわかには想像できない。
リー首相がラクサ風味クッキーに言及したのは故なきことではない。
シンガポール人の生活にとって食の重要性は高い。建国のはるか前から連なる移民の記憶と歴史を凝縮したローカルフード文化は、紆余曲折を経て着実に成長したシンガポール人としての国民意識を支えるシンボル装置なのだ。
植民地時代とちがい、シンガポールの建国以来、中国系国民の子供は、インド系やマレー系の子供と同じ学校に通い、同じ団地に住み、共に兵役を経験し、ロティプラタ(=インド系ストリートフード)やラクサ(=マレー系)を食べて育つようになった。建国から54年を経て、そんなシンガポールのマジョリティは、自分と似た顔をした異なる体制下の同じ民族よりは、異なる習俗や母語、宗教を持つ「隣のシンガポール人」こそが価値観、運命、将来を共にする仲間だと心から信じるようになっている。
国民や民族のアイデンティティは習俗や歴史や神話から自動的に生まれるものではなく、永続的なものでもない。そのことをシンガポールの現代史が明らかにしている。
10年前にわたしが住んでいた頃、シンガポールは「アジア初心者のお手軽コンビニ」のように言われていた。わたしも実際そう思っていた。だが、今回再訪し、それが間違いだったことを知った。
その後、さまざまな場所を訪れたが、シンガポールにはそのどことも違う独自性がある。そのありように目を凝らせば、さまざまなディテールに感動を覚える。
どこがそんなに素晴らしいのか。数回に分けて追ってみたい。