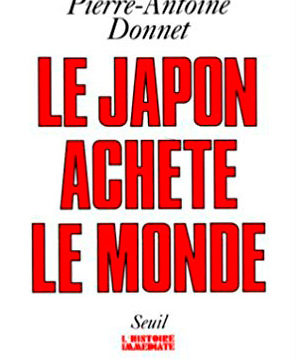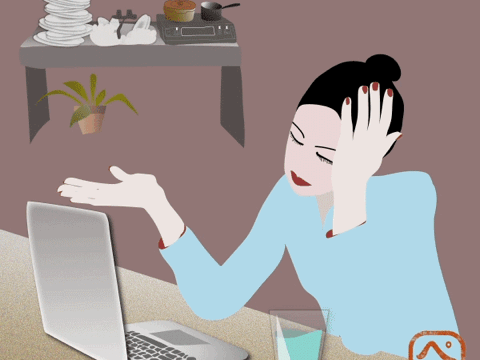◁チベット人は日本人と似ているが、男女ともに骨の細い華奢なお公家さまタイプの人はいない
体育会系といえば、高校時代を思い出す。
休み時間に廊下をふざけながら歩いていて、ふと気づくと、横にいたはずのバスケ部の友だちがいない。振り返ると、彼女は廊下の端でコクンと首を90度前傾させ、直立不動で凍っているではないか。見ると、前からバスケ部の先輩が歩いてくる。10秒ほど凍りついていた友だちは、先輩が通り過ぎるとたちまち生気を取り戻し、再び、何事もなかったかのようにじゃれついてきた。
何も大名行列や帝国陸軍じゃあるまいし…。当時、文化系部活に所属していたわたしには理解に苦しむ体育会系のしきたりだった。
次に、大学生になって体験入部した伝統芸能サークルでも、やはり体育会系とおぼしき習慣に出会った。
そのサークルは、必ずランチ代を先輩が後輩におごるのが不文律だったのだ。たとえ、その場にいるのが後輩5人、先輩1人でも割り勘はなし! なんという不条理。先輩と後輩には、大学に1年か2年早く入ったかどうかの違いしかないのに。
食事が終わると先輩はさりげなく会計伝票を掴み、カウンターに向かう。後輩はレジで支払う先輩の横をするりと抜け、外で待つ。そして、支払いを済ませた先輩が出て来ると、後輩は、頃合いよく頭を下げ、一斉に「ごっつぁんでした!」と叫ぶのだ。
その後社会に出てからは、さすがにガチの「犬型、体育会系カルチャー」はご無沙汰だった。チベットハウスのボランティアで、懐かしの体育会系カルチャーに再び出会うまでは。
思いがけないことだった。思いやりや慈悲、人間の平等や普遍性を説くダライ・ラマ法王の教えは、一見、体育会系カルチャーと無縁に見えるし、チベットのボランティアをする人は、どちらかというと猫型、文化系が多かったから。
ところが、ボランティアを使う側の人間、実際に近くで眺めた生のチベット人、チベット亡命政権や法王庁の偉い人たちは、正真正銘の犬型、体育系だった。誰もが、まるでアメフトやラグビーの監督や選手のように、心身ともにタフで強面。その組織は規律に満ちているのだ。
わたしが遠巻きに接したチベットの亡命政権や法王庁は、トップを頂点とした長幼の序と規律が徹底した体育会系の空間、タテ社会だった。世界的なポップアイコンにして慈悲の人であるダライ・ラマは、そんなタフで強面な人たちを束ねるリーダーでもあったのだ。
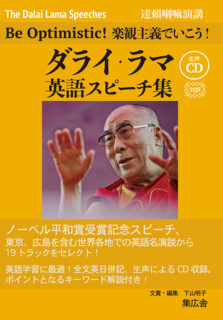
◁ガチの体育会系組織トップの言葉として聞くとスピーチにも違った迫力がある(書影をクリックすると当該書籍の解説ページへ移動します)
ダライ・ラマの講演で、法王は所定時間を過ぎても話を続けることがある。そんなとき、「法王さま、もうお時間ですよ、会場が閉まりますよ」と言える人は誰もいない。生き神様に物もうせる人はいないのだ。
個人的には自由闊達なチベット人も、ひとたび、組織の一員となると途端に体育会系DNAを発揮する。度重なるトップダウンの予定変更も方針変更もなんのその。上官の鶴の一声は絶対。黙々として決定に従う。文句を言わず、批判せず、決して理屈をこねない。
あるいは、そもそもチベットの遊牧民社会は昔から日本の稲作社会よりずっとトップダウン型構造だったのかもしれない。
あるいは、尊師への絶対的帰依を重視するチベット仏教が体育会系メンタリティのバックボーンなのもしれない。
あるいは、長く社会の基層だった大規模な僧院が厳格なヒエラルキー、規律重視と、クリアな意思決定構造を生んだのかもしれない。
あるいは、国を失い、厳しい条件に晒され、国際社会でもみくちゃにされるなか、亡命チベット組織の体育会系気質はどんどんバージョンアップしていったのかもしれない。
△チベット人が国を失った経緯、そして現在のチベット問題
ダライ・ラマはよく、「どうか、わたしの言葉に、それがわたしの言葉だというだけで従わないでください。本当に正しいかどうか、どうぞ自分自身で確かめてください」と言われる。
これはひるがえせば、法王の言葉に無条件に従う国民や信者があまりに多いことの証しだろう。それにダライ・ラマは不満なのだ。
さしずめ、廊下ですれ違った高校の友人の先輩なら、「あなた、はっきり言って、慇懃無礼よ、わたしが先輩だというだけで凍りつくなんて。わたしが本当に尊敬できるのか、確かめてごらんなさいよ。自分の頭で考えて判断しなさい! 自分が本当にそうすべきだと思うことをやりなさい!」と言うところか。
ダライ・ラマの偉いところは、そんな自らの体育会系組織の強みと弱みを認識し、その改革に取りみつつも、16歳から83歳に近くなった今日まで、一貫して重責を果たし続けているところだ。
自国民を鼓舞するダライ・ラマは驚くほどパワフルだ。
「元気出して、ファイトで行こうぜ! ファイト! ファイト!(といつも言われているようにわたしには聞こえる)」。そして、そのまわりにはいつも、法王のためならいつでも死ぬ準備ができているタフな男たちと、英邁な君主にして生き神様であるその人を無条件に慕う無垢な民がいる。
眼前に広がるそんな「チーム・チベット」の姿にわたしは痺れ、共感し、不覚にも涙を流してしまう。
実はそんなわたしも、ほんとうは「隠れ体育会系体質」なのかもしれない。

△2016年大阪にて。感動するわたしにカメラの方に向かせようとするダライ・ラマ法王