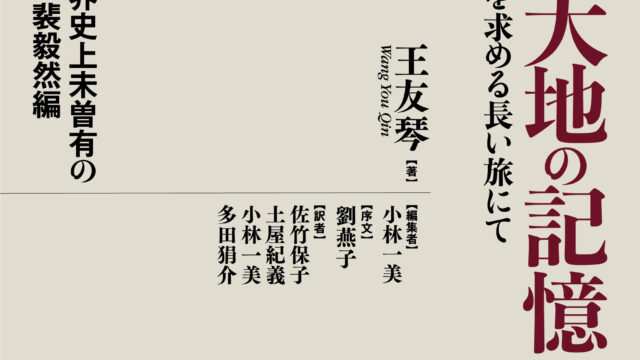紫の花伝書──花だいこんを伝えた人々
紫の花伝書──花だいこんを伝えた人々
細川呉港・著
四六判上製本/368ページ/本体2200円+税
ISBN 978-4-904213-13-1 C0095
発行/集広舎 発売/中国書店
ルート探究の心と花の種を運んだ心の共通点
ガルーダ三矢(評論家/コラムニスト)
本書の主人公は、先日読ませていただいた『アキとカズ 遥かなる祖国』(喜多由浩著)同様、まるで推理小説のように複数存在する。たまたまなのか? 最近の書籍の傾向? 流行なのか?
近年の読み物は安直で短絡的なものが好まれていると思っていたのだが、意外にも書籍の世界では逆の傾向が見られるのであろうか。ある意味有り得ると思うのは、じっくり「本を読もう」という人種は、元から安直で短絡的な風潮に流されていないのかも知れない。少なくとも「本を読む」という行為においては情報氾濫の日常とは異なる気分なのだろう。その意味では、特定の人種ではなく、より多くの人間にその側面があるのかも知れない。
それはそれで嬉しい話ではないか! 世の中がどのように変遷し、いかに世知辛くなろうと、荒んでゆこうと、短絡的にイラつこうと、「本を読む」という姿においては、昭和、大正、明治、それ以前の人間と何ら変わることなく、じっくり読み、学び、気付き、分かるを持ち続けているということだ。
逆に、分かり易さを求め、簡単で肯定的な意見情報を共感・共有するだけの浅い価値観の主流の時代は、もしかしたら今だけのことであって、近未来には短絡的情報を求め読書を嫌う人種とその逆の人種、そしてどちらでもないしどちらにもなれる、つまり、全く別ものとして別な向かい合いが出来る圧倒的多数の人間の三種に明確に分かれてゆくのかも知れない。
だとすれば、電子書籍のみならず、一冊の書籍でも安直さに応え風潮に迎合する出版姿勢が増えてきている状況は、近々「古臭い」ものになるかも知れないのだ。ならば、本書のような「いかにも本らしい本」を出し続けている出版社こそ、昔気質のようでいて、実は先見の妙があるとさえ言えるのではなかろうか。
本書はまた、その装幀にも嬉しい心遣いとプライド(誇り)が感じられる。ただただ分厚い雑誌のような気楽な本が好まれていると勘違いした一頃(今もか?)の本とは異なり、昔ながらのハードカバーで、テーマの「紫色の菜の花」に合わせ文字の色も表裏表紙の裏も紫で、表裏表紙には日本画を思わせる見事な装画があり、書棚に納めた時、独りささやかな自慢に浸れるような嬉しささえ得られる。
そんな付加価値の部分(これこそが肝腎な「ひと手間」なのだろう)で、読む前から「わくわく」したり嬉しく思える書籍に出逢えたのは実に久しぶりである。そう感じるのは私だけではないに違いない。
さて、本書の主人公と言うか主役級の登場者は、まず言うまでもなく、「花だいこん」という「帰化植物」であり、次いでそれを戦後の日本に運んだ様々な人物である。
「花だいこん」は、アブラナ科のオオアラセイトウ属、ショカツサイ属、ムラサキハナナ属などと日本語では色々に呼ばれる Orychophragmus属の越年草で、オオアラセイトウ、大紫羅欄花、紫花菜、諸葛菜、花大根、花だいこん、紫花だいこん、など多くの名で呼ばれる(その他にも本書では、原産地中国各地の呼称から、日本の各地での俗称まで驚く程多数の名前が紹介されている)。
科主アブラナのように、葉を食したり、茎を煮て食したり、菜種油を穫ったりするが、「だいこん」の語を持つのに根は食べない、言わば「紫色の菜の花」である。つまり、このひとつの「主人公」さえも、実に多様なキャラクターを有して、東アジアからヨーロッパに至るまで古今東西で活躍し、人々に親しまれた存在なのだ。「諸葛菜」の名に関しては、かの諸葛孔明が兵糧の為に栽培を奨励したという逸話さえ伝えられているという。これに関して本書は資料編で一項目を割いて述べている。
また、この「花だいこん」を日本に運んだ人物もまた、明治二十一年生まれの陸軍薬剤少将、横浜元町の高台に潜んでアメリカ軍の空爆を見ていた青年、戦後日本に亡命した、愛新覚羅とも縁のある政治家、蘭伯爵とも呼ばれ貴族院議員でもあった満鉄の総裁、日本女子大を出た満州開拓女塾の女先生と、これもまた身分地位を問わず実に多様なキャラクターであり、正に「花だいこん」の存在そのものを見事に表している。その意味では「花だいこん」は、階級闘争の域にも至らない幼稚なアンチテーゼのそれではない、階級を越えた純粋なサブカルチャーの素晴らしい実例とさえ言いたいほどである。
そして、これらの様々な主人公にも増してその存在感が強く感じられるのが、冷戦時代のキューバ渡航、雑誌『PLAYBOY』『MORE』編集部の経歴を持つ著者・細川呉港氏である。ドキュメンタリーな書籍において著者の存在感が強いのは「どうかと思う」という人もいるだろうが、本書では決してイヤミでもなくイヤラシくもない。それは、著者が四十五年もの歳月を掛けて、この「花だいこん」のルートを求めて来たからに他ならないのだが、それは先に挙げた「五つのルート」の「五人の運び人」、そして「花だいこん」を通じて、彼ら「運び人」と絡んだ様々な人々それぞれの想いや生き様を驚くほど深く掘り下げているからである。
著者自身は、その「花だいこん探究」の四十五年の大半を占める高度成長期~バブル経済期には、多くの日本人がそうであったと同様に「生きることで精一杯」だったかのような表現をして、やるべきこと、やりたいことに割く時間がなかったように語っているが、実際はどうであろう。「やるべきこと、やりたいこと」を持っている人間は、得てして本人は「もっと密度濃く時を使いたかった」と思うものなのだろうが、他者からしてみれば、「よくもここまでお見事に」というべき立派な仕事であったりする。
好感度をより高めるこの謙遜さに反して本書には、著者の揺らぎない信念、つまり「花だいこんを日本に咲かせたいと思った人々の心を探ることの価値と、それを読者に伝えることの意味」が、強く感じられる。
著者は、先に挙げた様々な地位立場の人間が一様に「長い戦争の中で、夢と希望を持ちつづけ、精一杯生きた、すばらしい人たちだった。みんな、戦後の焼け野原になった日本を、花で一杯にしようと思った」という共通の生き姿と想いで「花だいこん」を運んだとしている。事実そうなのであろうが、この著者なくてはその物語はひとつの大きなサブカルチャーのような動きとしてはくくれなかったに違いないのだ。
本書の面白みのひとつが、その点であろう。
例えば、ルーツやルートを探究したテーマとして「日本人のルーツ」や「稲作のルーツ」、七〇年代に話題になっただけでなく、欧米では未だに語りぐさのアメリカTVドラマのその名も「ルーツ」がよく知られているが、いずれもテーマが壮大過ぎるのに対して資料が少ないが為に、ひとつか数例の「ルート」を挙げて物語に仕立てるしか術がなかったのだろうと思わせる。
そもそも「ルーツ」を一点に限定することも難しければ、当然「ルート」も限定できない。しかし、本書では、著者の驚異的な探究心と、手を抜かない執拗とさえ思える、掘り下げ、調べ尽くす根気が、考え得る限りのルートを探り出し、それら事実性の高い個々を大きな物語に束ねた類い希な「ルーツ探訪」に仕立て上げられているのだ。いや、もはやありきたりの「ルーツ探訪」ではない。まさに「ルート探究」なのである。
もちろん言いかえれば、上記の「共通の想い」があったに違いないという著者の価値観のフィルターで全てを観、まとめたとも言える。しかし、私はその価値観のフィルターにもイヤミやイヤラシさを感じなかった。
例えば第三章で述べられている戦中南京で南方戦線で欠かせないマラリヤ薬の開発などに携わっていた陸軍薬剤少将の場合は、名も無き兵士が植えた「花だいこん」に一目で魅せられ、その種を貰い受けて日本に引揚げてきたのが始まりである。が、そもそもは、その名も無き兵士の「花を愛でる心」あってのことである。
南京で、名も無き兵士と少将という、軍務上では直接の関わりがないだろう人間同士が「花だいこん」とそれに「魅せられた心」で繋がった。そしてそのルートは、故郷茨城に繋がり、少将とは家族だが血縁ではない嫁(長男の嫁)の心へと繋がり、やがて新聞の投書から発展した「花だいこん談義」の読者へ繋がり日本中に広がるのであった。
物語はこのような誰もが心地良く思うだろう美談だけではない。第四章の上海ルートでは、戦中横浜の上海銀行支店長宅の庭園に咲いていた「花だいこん」をこっそり盗んだ人物とその母親の物語が描かれている。そこには一抹の政治活動の様子や、戦後の知識人層の間にあった戦争及び軍人に対する独特な感情も描かれている。「戦中に伝わったが、日本各地に広がったのはもっと遅い」と主張する上海ルートは、そのような心情も加わって陸軍少将の南京ルートと対峙する。しかし、ここでもやはり、最終的には「花だいこん」の可憐な姿に魅せられた人々によって、やがて日本各地に広がっていくのである。
物語には、戦中戦後の日本の昭和史が多く描かれており、そのいずれもが、既成の昭和史や戦史では語られなかったものである。それはまるで、あの夏目漱石の猫がその目で見た人間社会のごとく、「花だいこん」が観た戦中戦後昭和史のようでもある。
たとえば、とある人物が「花だいこん」を昭和天皇に献上したところ、植物学者でもあられた天皇が、「その名は正しくない」と指摘し、属主名の「オオアラセイトウ」の名を述べられたというエピソードも紹介されている。事実、学術的には「ハナダイコン」は、別属「ハナダイコン属」の属主である。
また、第五章の北京ルートは、戦後日本に亡命した満州国政治家で愛新覚羅の伯父に当る人物がその種を運んだものである。しかも彼は戦直後、捕われていた北京の監獄を脱獄しその際に監獄に咲いていた「花だいこん」の種を持って亡命して来たのだという。
また、新聞の投書欄の談義を通じて、引揚げの時に叶わなかった「花だいこんを持って来る」願いを数十年経って叶えたという華僑の物語もある。投書で知り、種を得て庭中に咲かせたというのだ。しかし著者は、その元北京大学講師と日本人妻の出逢いから、その後近年の悲惨な物語も深く掘り下げて描いている。「なぜそこまで?」と思わせる立ち入った内容でさえある。
また本書は、著者のとてつもなく非凡な記憶力と思いつき(?)によって、話は次々にリンクしていくので、前述した「分かり易い安直な」を好む人間には全く不向きな物語の展開を見せる。「花だいこん」が取り持つ縁から伊豆の温泉に飛べば、そのまま福岡玄洋社に飛ぶかと思えば、マラリア治療薬の話を語れば東南アジアにも詳しく。また、ある話では二十年も誤情報に惑わされていたことが判明し、「花だいこん」は、福岡の女郎屋にまで繋がり、そこで生まれ育った歌人の生涯にも迫る。第七章の満州ルートは、その歌人が女学生時代に満州帰国子女から得た「花だいこん」である。
偶然か必然か? 本書は、先日拝読し書評を書かせていただいた『アキとカズ』と同じ時代を同じ様に多岐に渡って詳しく掘り下げつつ、全てをひとくくりにする大きな視野とテーマを持つ「戦中戦後昭和しを面白く分かり易く俯瞰できる絶好な書物」という共通性がある。
出版年は、本書が二〇一二年、「アキとカズ」が二〇一五年と開きがあるが、同じような有益な学びを促す書籍を連発されるあたりは、ひたすら集広舎さんの出版姿勢に敬服するばかりである。しかも、この二冊は、これも偶然か必然か? 全く異なるセンスの著者によって描かれているがために、より一層その出版意図の深みに毅然としたバランス感覚さえ感じるのである。
そして、いずれもが、戦争中は敵同士、戦後から今日に至るまでの時代は、戦勝国と戦争犯罪国のようになっている東アジアの国々と日本とを深く繋いでいる。
中国と日本、韓国・朝鮮と日本は、対立感情ばかりでなく美談もあるのだ、というような単純な話はどこにでもあるだろうが、その類いより遥かに読み応えがあり、面白く事実を知り分かり、さらにそこに関わった人間の心情がつぶさに伝わってくる名著であると言える。
私は、たまたまこの二冊を続けて拝読したわけだが、まるで端からセットで読むべきだったかのような気さえする。しかもその順番は、出版年とは逆に『アキとカズ』~『紫の花伝書』であろう。それは前者の著者が新聞人(正確には新聞社編集委員)で、後者が雑誌編集者であるからゆえのものであると考える。
新聞の人間は、良くも悪くも「事実を大衆が好む物語に仕立て上げる」傾向にあり、雑誌編集の人間は、良く言ってバランス感覚に富むが、悪く言ってあれもこれもとバラエティーに富み過ぎる傾向がある。前者はその人間像と物語が痛切に身近に感じられる一方、それゆえに後味が切ない。ところがそこで、単独で読んだ場合、その「総花的」な展開の広さにテーマの中心が見えにくくなったかも知れない本書を読む。
本書のテーマの中心は、言うまでもなく「花だいこん」そのものなのであるが、紫色の菜の花に、その気持ち、想いを訊くわけにもいかない。しかし、前者を読んだ後であれば、切ないながらも大きなテーマを把握しかけているので、「花だいこん」の存在の意味がよりいっそう理解できるという仕組みだったのだ。
「アキとカズ」の書評でも似たようなことを述べたが、戦後七十年の節目に様々な振り返りと向かい合うことになるが、果たして来年、再来年、数年後、その感銘や共感はどのように薄れてゆくのだろうと考えると虚しさを禁じ得なかった。しかし、この二冊を読むことで感動や共感は異なったものに変質するだろう。
それもこれも、著者の飽くなき探究心の影響であろうと考える。その意味では、本書の本当の主人公は、「花だいこん」でも、五人の運び人でもなく、著者の「探究心」なのではないか、とさえ思える。
本書では、著者の想像や推測の部分は明確にそのように書かれており、それは決して多くない。それ以外は全て実際に足を使って調べ上げたものであり、より多くは、五人の運び人に関わった多くの人々の口から発せられた証言であるが、問われた人間を「語りたくさせてしまう」力がなければ語らないような深い心情が述べられている。著者の非凡な「探究心」にはそのような特別な力が存在するのだ。
その意味では、より真の主人公は、人間の「知りたい、分かりたい、伝えたい、記したい」という情熱であるとも言える。しかもそれは、「花だいこん」に関わり、魅せられた人々が「花だいこん」に抱いた想い「知りたい、育てたい、伝えたい、広めたい」と同質であったに違いないのである。