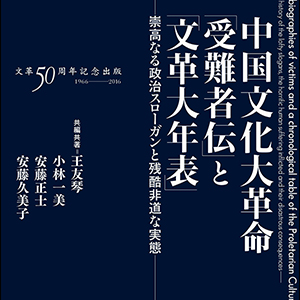中国の反外国主義とナショナリズム──アヘン戦争から朝鮮戦争まで
発行日/2015年04月12日
著/佐藤公彦
発行/集広舎
A5判/上製/2段組/381頁
定価/3,600円+税
中国流ナショナリズムの本質とは
「敵」であり続ける必然性
「中国もの」が毎月、溢(あふ)れるほど出版されていても、日本人など世界の人々は中国と中国人が理解できない。強烈な違和感を覚える隣国は近代から現在に至るまで、ずっと日本の最大の躓(つまず)きの石だった、と著者は看破する。
異文化と出会った時(とき)に中国は「外国人嫌い(ゼノフォビア)」と「神秘的な法術(邪教)」で対応してきた。具体的には「反韃子(ダーツ)主義」と「反外国主義」の形式で現れる。韃子とはモンゴルなどユーラシアの遊牧民を指すが、「東夷・南蛮・西戎、北狄」など中華周辺の諸民族の総称でもある。一方、「外国」の範疇(はんちゅう)には主としてキリスト教文化圏の西洋諸国が入るが、倭・日本は「韃子」と「外国」の二重性を持つ、と中国に認識されている。

「反韃子」と「反外国」の近代史はアヘン戦争と太平天国の乱、義和団(拳匪)事件など大清帝国の衰退期を経て、中華民国期の「反キリスト教運動」、そして中華人民共和国時代のキリスト教弾圧運動と今日の反日主義へと繋(つな)がる。その結果、「反韃子」で成立した中国人(漢民族)による中国人のための国家は必然的に対内的にはチベット人やモンゴル人などを弾圧の対象とするし、日本などは絶対に「敵」であり続けなければならない。
躓かされた日本は自省の念も含めて中国をマルクス主義の階級論に即して善意的に解釈しよう、と戦後に努力してきた。しかし、反帝国主義史観では「扶清滅洋」、すなわち「清朝を助けて西洋を滅ぼす」目標を唱えた義和団事件の解明には至らない。「人民」が「搾取階級」を打倒して「民主政権」を建立したという革命史観では中華人民共和国の専制的特徴について説明しきれない。社会主義の進歩史観は20世紀の流行だったが、それでも中国を分析する武器にはならなかった。
リベラル派歴史家は、「中国と中国人を区別しよう」との空論を死守しようと踏ん張る。「中国」という国家は中国人が運営しているからこそ、国際社会の異質な存在だ、と本書は中国流ナショナリズムの本質を解剖している。
楊海英(静岡大教授)
産經新聞平成27年(2015年)6月28日(日)読書面