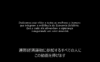バウルはプレム(愛)を唄います。そして、その無条件の愛、至高の愛の狂気を讃えます。なぜ人々はそれを狂気と見るのでしょうか? それは、プレム(愛)の在り処が「非日常」であるからでしょう。
バウルの唄
至純の愛を知った者は、
口を利こうが利くまいが
その眼を見ればわかるもの。
あの姿を知ってしまったからには、
称名もマントラも忘れてしまう。
閻魔の書記は、彼の行為の善悪を
どうして帳簿につけられるというのだ。
頭頂の宝石をなくした蛇のような
愛をあじわい知る者の両の眼
一体何をしでかすか
見当もつかないのさ。
シラジ・シャインは何度も言う。
ラロンよ、聞くがいい。
性愛の快楽にさ迷うおまえには
純粋愛なんて気配もない……と。
 徒歩でなければたどり着けない村。私がベンガルに住みだした当時は、道も付いていないそんな村がまだたくさんありました。荷物は牛車で運ばれます。人々はとても素直です。私はそんな村々を師に連れられて毎日のように唄を歌って廻ったものでした。泊めていただいたお家に井戸のないことも多く、そういう場合、飲料や顔や手を洗うのに使えるのは、遠くから運ばれて来た水瓶一杯の水だけです。水浴びや洗濯はもちろん池で、そしてトイレもないので人の少ない夜明け前に畑や林に出かけたものです。
徒歩でなければたどり着けない村。私がベンガルに住みだした当時は、道も付いていないそんな村がまだたくさんありました。荷物は牛車で運ばれます。人々はとても素直です。私はそんな村々を師に連れられて毎日のように唄を歌って廻ったものでした。泊めていただいたお家に井戸のないことも多く、そういう場合、飲料や顔や手を洗うのに使えるのは、遠くから運ばれて来た水瓶一杯の水だけです。水浴びや洗濯はもちろん池で、そしてトイレもないので人の少ない夜明け前に畑や林に出かけたものです。
夜になるとお祭りに村人たちが集まって来ますが、田園を越えた隣の村から畦道を歩いてやって来る人々の手にするランプの灯りが数珠繋ぎになり、とても美しく見えたものです。
土を盛り、足で踏み固めただけのステージの前の方は子供たちでいっぱいになります。テレビもない村では、年に一度の村祭りにやってくるバウルたちは、彼らにとって夢のスーパースターのようだったことでしょう。そんな子供たちには、一瞬一瞬が驚きの連続であったに違いありません。唄声も、楽器の音も、衣装も、踊りも、見るものと聞くものがすべて未知のもので驚きの対象です。ある意味で子供たちは「非日常」に住んでいます。
大河も細流も、清流も濁流もすべて飲み込む大海のように、愛は最大限に寛容です。そして、全てをたたえる大宇宙と同様に無限な愛。そんな愛と交わったなら、心は広く澄み渡り、寂しさや悲しみ、不安、恐れ、競争、毀誉褒貶、栄辱、驕り、これらすべては、海辺の砂浜の無数の砂粒の中の一粒のように取るに足らぬものと思えるでしょう。
 その愛は非日常です。心に取り付くもろもろの想いは「日常」です。愛は「日常」を含みますが「日常」にありません。ですから何の制約も受けません。制約を受けるのは「日常」の世界であり、「非日常」の世界はすべてにつながっているので制約を受けないはずです。制約があれば、すべてにつながることは出来ません。すべてを含むことも、すべてにあることも出来ないのです。そこでは善も悪も、聖も賤も、表も裏も、内も外も、すべてが対立せずにあります。すべてが連続しているのです。私たちは不連続で、個々がばらばらの世界に住んでいます。
その愛は非日常です。心に取り付くもろもろの想いは「日常」です。愛は「日常」を含みますが「日常」にありません。ですから何の制約も受けません。制約を受けるのは「日常」の世界であり、「非日常」の世界はすべてにつながっているので制約を受けないはずです。制約があれば、すべてにつながることは出来ません。すべてを含むことも、すべてにあることも出来ないのです。そこでは善も悪も、聖も賤も、表も裏も、内も外も、すべてが対立せずにあります。すべてが連続しているのです。私たちは不連続で、個々がばらばらの世界に住んでいます。
そのプレム(愛)は、すべてにつながり、すべてを包み、限界がなく、永遠です。ですからその愛は言葉を超越し、心を超越し、知識を超越するものです。言葉で表すことが出来ず、心で捉えることが出来ず、知識で分析することの出来ないものです。にもかかわらず、それによって「私」は包まれ、すべての存在と繋がっているのです。バウルにとって愛は「神」そのものです。有限なる「私」は無限のそれを知らずに過ごしています。
この世はすべて自然の恵みですが、その愛を垣間見ることは、その中でも特別な自然の慈しみにより贈られる“気付き”とでもいえばよいでしょうか。
バウルは、プレム(愛)を味わおうとします。
「救い」も「霊妙な力」も「悟り」も求めません。宗教学者による説教も、宗教書も不必要です。
神の戯れをこの人間の世界に見るのです。
ベンガルにロスゴッラというお菓子があります。カルカッタの甘い物屋さんの数は世界一で、ギネスブックに載っていると言われるほど甘い物が好きなベンガル人ですが、そのベンガルのお菓子を代表するのがこのロスゴッラです。
甘いシロップに浸かった丸くて白いお菓子。牛乳に酸乳を加え固まったものを材料にし、それを丸い団子にし沸騰しているシロップで煮ます。見た目と作り方は説明することが出来ます。でもその味をどうして完璧に表現することが出来るでしょう。舌触りがどんな感じか、一般の人が知っているものに例えることはできます。甘味がどんな風に口に広がるのか描写することは出来ます。でもその味は、ロスゴッラを食べたことのある人だけが知っているものです。ロスゴッラについての説明を読んだことのある人は、たとえ食べたことがなくても、それをまた他の人に説明してあげることが出来るでしょう。作り方を教えてあげることも出来るでしょう。けれども、味わうことは出来ません。食べなくては味わうことは出来ないのです。
例えばこんな人がいるとします。ロスゴッラについて書かれたものはすべて読み、ロスゴッラの歴史から、少し洋風になった現在のロスゴッラまであらゆることを知っている人です。でも、もしその人がロスゴッラを食べたことがないとしたら、味はすべての情報を総動員した知識からの空想でしかないでしょう。
そしてもう一人、ロスゴッラの歴史も作り方も知らない人がいるとします。でも、その人はロスゴッラを食べたことがあります。味わったことがあります。彼は、説明する言葉を持ちません。味わったその人にとって言葉によるどんな説明も物足りないでしょう。若しくは、どの説明も正しいけれど、それらのすべてを集めても味わいそのものを表すことは不可能であり、もどかしい想いをするでしょう。彼はロスゴッラを味わいます。
純粋愛を味わう者……彼の行動は正道を逸脱しているように映るかもしれません。彼の眼は「日常」を超えて「非日常」に絶えず向けられているからです。
 バウルは、“大いなる源”であり、すべてである至純の愛を味わおうとします。その愛に関する説明は必要としません。解釈を収集したところで、理屈の山にその愛は埋もれてしまうでしょう。それは、言葉を超越したものです。言語による独りよがりの空想は妄想と化するやも知れません。
バウルは、“大いなる源”であり、すべてである至純の愛を味わおうとします。その愛に関する説明は必要としません。解釈を収集したところで、理屈の山にその愛は埋もれてしまうでしょう。それは、言葉を超越したものです。言語による独りよがりの空想は妄想と化するやも知れません。
バウルに経典はありません。称名、瞑想、祭祀、供養の儀式、バウルは規定の一切に捉われません。一切の法式の枠を払い捨てます。あらゆる方式は「非日常」を「日常」に引き落とし「日常」の中に埋め込みます。
けれども、制約のない「在りのまま」は、「日常」を「非日常」に解放します。
それがバウルの修行といえるでしょう。
この人としての身体にすべてが存在します。この肉体も愛から生まれ、愛によって成り立っています。この地球が公転や自転をしているように、太陽系や銀河系が成り立っているように。
バウルはいわゆる「世捨て人」ではありません。
人生を“生き生き”生きるために、愛を、プレムを、味わおうとするのです。