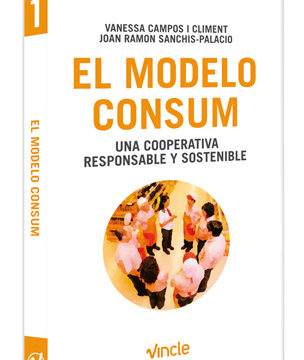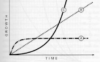社会的連帯経済に関するこの連載では、どうしても諸外国の事例の紹介が中心になりがちですが、今回は日本発で諸外国に広まっていった産直提携農業について取り上げたいと思います。なお、この産直提携については、以下の記事もご覧ください。
- フェアトレードについて(第11回)
- ブラジルにおけるフェアトレード(第89回)
- 中南米のスペイン語圏諸国におけるフェアトレード、およびその課題(第90回)
- フェアトレード促進のための公共政策:南米3ヵ国の事例(第104回)
- 報告書「フェアトレードビジネスモデルの新しい展開」(第105回)
産直提携農業は、1960年代に日本の消費者生協が1960年代に始めた取り組みがそのルーツとなっています。当時の日本は高度成長期で、各地でさまざまな産業が発展していましたが、その一方で有害な食品添加物や公害などの問題が一挙に噴き出した時代でもありました。このような中で食の安全を求める母親らが集まった消費者生協が、従来の流通網を通さずに直接生産者や農協から買い付けるようになったのが、産直提携農業の始まりと言えます。
産直提携農業について考える上で貴重な指針となるのが、1978年10月に開催された日本有機農業研究会の第4回大会で発表された「提携10か条」です。それについて、以下詳しく見てみることにしましょう。
▲みやぎ生協による産直提携の実践を紹介したビデオ
- 相互扶助の精神
生産者と消費者の関係は、単に農産物を作って売る人と買って食べる人の関係ではなく、それ以前に人間同士の関係であることを忘れてはなりません。生産者と消費者のうちどちらのほうがより偉いというわけではなく、平等な立場でお互いを尊重して助け合う関係を築くことが、産直提携農業の基盤にあるわけです。 - 計画的な生産
農産物の生産量については、生産者と消費者の相談の上で計画されます。消費者の希望を生産者が聞いたうえで、可能な限りその希望を満たす形で生産するわけです。もちろん、農地の条件次第では消費者の希望が実現不可能なこともありますので、その場合には生産者側の事情を消費者が理解することも必要となります。 - 全量引き取り
消費者側は、希望した生産物を全部引き取り、できるだけこの生産物をもとにして食生活を成り立たせる必要があります。当然ですが、生産者にこれだけの量を作ってくれと注文しているわけですので、その通りに生産された農作物は買う必要があるわけです。 - 互恵に基づく価格の取決め
農作物の価格設定についてですが、まさにフェアトレードと同じ精神がここで反映されることになります。生産者は、生産した農作物の市場が確保できたり、包装などの労力が省略できたりすることに感謝する一方、消費者は新鮮かつ安全な食品を手に入れられることに感謝し、お互いにとって納得のゆく価格設定を行うことが欠かせないわけです。 - 相互理解の努力
当然のことですが、生産者と消費者との間での提携関係を推進し続けるためには、お互いの事情をきちんと理解することが欠かせません。単に農作物が売れればいいや、あるいは有機野菜が手に入ればいいや、と考えるのではなく、お互いの状況を理解した上で、友情にもとづいた関係を築いてゆくわけです。 - 自主的な配送
流通についても他社に任せるのではなく、できるだけ自分たちで行うようにしています。生産者側と消費者側のうちどちらが担当するかは事例により異なりますが、あくまでも配送についても自主運営が重要視されるわけです。 - 会の民主的な運営
生産者グループと消費者グループのどちらにおいても、誰かのリーダーシップに頼りすぎるのではなく、各会員の可能な範囲において運営の仕事を分散してゆくことが大切です。 - 学習活動の重視
単に食材や市場の確保だけではなく、生産者も消費者も、グループ内での学習活動をきちんと行う必要がある。 - 適正規模の保持
グループの規模が大きくなりすぎると(人数・地域)上記の実践が難しくなるので、あくまでも円滑な運営ができるような会員数や地域の広さにとどめるのがよい。 - 理想に向かって漸進
とはいえ、生産者側も消費者側もこの理想が現実ではないことを認めたうえで、できるだけそれに近づく努力を怠らないようにする。
この提携10か条は、連帯経済の概念が生まれる前、そして社会的経済についても日本で知られる前に成立したものですが、この内容を見ると、協同組合の7原則など社会的連帯経済の諸原則と親和性があることがわかります。「7. 会の民主的な運営」はまさに協同組合の第2原則「組合員による民主的管理の実践であり、「8. 学習活動の重視」は第5原則「教育、訓練および広報」を体現しているものと言えます。さらに、「1. 相互扶助の精神」、「4. 互恵に基づく価格の取決め」や「5. 相互理解の努力」も、社会的連帯経済の精神を反映したものと言えます。
産直提携農業については、普通はフェアトレードの枠組みの中で語られることは少ないですが、その実践の性格を見ると、フェアトレードに非常に似ていることがよくわかります。フェアトレードというと、途上国の農民を支援するために先進国の消費者があえて高い値段を出してコーヒーなどの農作物を買うというイメージが強いですが、この記事の冒頭で紹介した記事をご覧になると、ブラジルやコロンビアでも国内で完結するフェアトレードの実践が始まっていることがわかります。特に、生産者と消費者との間での直接的関係という点では、まさに前述した産直提携農業の精神を実践しているということができるでしょう。
とはいえ、産直提携農業も課題がないわけではありません。最近発表された、「農協‒生協間産直を通じた地域農業振興」と題する報告書では、農家の高齢化や生協以外の民間企業の業界参入という近年の課題を取り上げたうえで、産直提携に直接参加している農家だけではなく農業や農村全体を支援したり、地域貢献を強調することで民間企業との差別化に生協が取り組んだりするようになっていると説明されています。具体的には、宮城県、滋賀県と広島県の消費者生協が、県レベルでの産直ブランドを作ったり、生産者と消費者との直接交流の機会を作ったり、環境保護の一環としての農業の側面を強調したり、クローバーを堆肥として育てたハーブ米という新しいブランドを作り出したり、消費者が産地を訪れて農業体験をしたりして消費者に農業の現場について関心を持ってもらったりしています。
産直提携農業の取り組みは、1980年代以降に世界各地に広がっています。米国など英語圏では、CSA(Community-Supported Agritulture)、あるいは日本語のままTeikeiという単語が使われています。また、フランスではAMAP(Associations pour le maintien d’une agriculture paysanne、農民による農業支援のための連合)と呼ばれており、全国組織が機能しています。これらの事例はURGENCIという国際ネットワークを結成しており、活発に交流を続けています。URGENCIはどちらかというと欧米が中心のネットワークですが、日本に加え、南米やアフリカ、そして中国やインドからも参加があります。
▲米国におけるCSAの実践例を紹介した動画
社会的連帯経済は、特にその概念が欧州や中南米で知名度が高いことから、社会的連帯経済の実践例についてもこれら諸国での事例が有名な傾向にありますが、こと産直提携農業に関して言えば、日本発の実践例が世界に広がり認められたということができます。日本初の社会的連帯経済の事例として、産直提携農業がさらに注目されることを祈ってやみません。