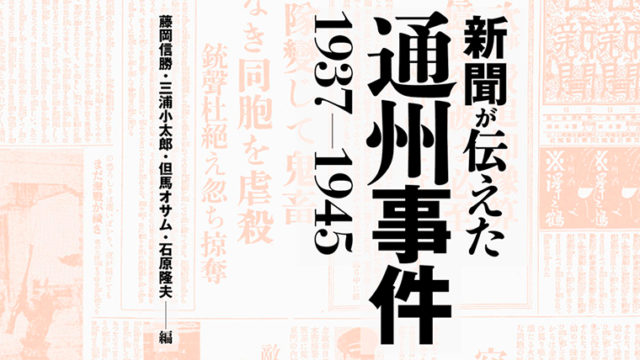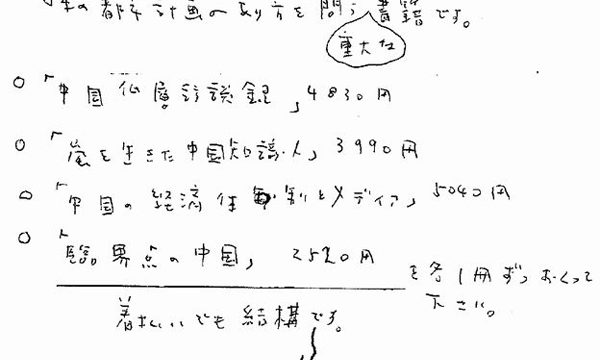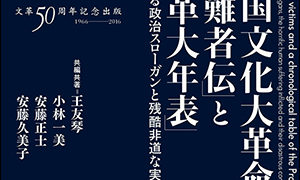書名:夏目漱石の見た中国
書名:夏目漱石の見た中国
副題:『満韓ところどころ』を読む
編著者:西槇偉・坂元昌樹
判型:四六判/296ページ
価格:2,500円+税
ISBN 978-4-904213-71-1 C0095
書評の著者、佐藤裕子先生(日本文学研究者。フェリス女学院大学教授。文学博士)のご許可を得て、日本比較文学会「比較文学」第62巻(2019年度、2020年3月31日発行)より転載いたします。
西槇偉・坂元昌樹編著
『夏目漱石の見た中国──『満韓ところどころ』を読む』(集広舎、2019年)
佐藤裕子
本書は、従来、評価の分かれている夏目漱石の『満韓ところどころ』に焦点をあて、「現地の視点からの実証的研究」(「まえがき」)として、「旅先で漱石は何を見たのか、それをどのように描いたのか。また、彼が見落としたものは何か、真実は何だったのか。それらを究明することで、作品に新たな光を当てることができるのではないか」(同)という問題意識の下にまとめられた編著である。「あとがき」によると、熊本大学が所蔵する旧制第五高等学校時代のラフカディオ・ハーンと夏目漱石に関する資料と研究上の蓄積を駆使し、「ハーンと漱石の両者の生み出した文学と思想」を「近代の異文化接触の視点から再考する」という地点から「越境と共生の文化学」(科学研究費補助金・基盤研究(C)平成二八 – 三〇年度)というテーマで共同研究を進め、本書はその成果の一つであるという。
内容としては、「まえがき」に続き、第一章は坂元昌樹氏による「大連の日の下で──語られる大連の風景と人々」、第二章は劉静華氏による「旅順体験における漱石の戦勝意識考」、第三章は西槇偉氏による「黍遠し河原の風呂へ渡る人──熊岳城温泉と黄旗山の梨園」、第四章も西槇偉氏による「怪物の幻影──熊岳城から営口へ」、第五章は申福貞氏による「『奉天』へのまなざし──夏目漱石の場合」、第六章が西槇偉氏による「老人を轢いた馬車の乗客は誰か──『盛京時報』の記事を手がかりに」、第七章が李哲権氏による「体液の変質としての文体 孤独な言語としての文体──漱石の『満韓ところどころ』を読む」という構成になっている。また、第一章から第六章までは、漱石が実際に滞在した街や都市ごとの章立てとなっており、第一章が大連、第二章が旅順、第三章が熊岳城、第四章が営口、第五章と第六章が瀋陽となっている。他に、コラムとして満州と『門』との関わりについて考察した平野順也氏による「満州に渡った安井」、『木屑録』に収められた漱石の漢詩における「海」の表現と、中国の漢詩との比較を論じた屋敷信晴氏の「漱石詩にみる水平線の系譜──日中の『海』観をめぐって」、漱石作品の朝鮮語訳者・金貞淑氏による「漱石先生への祈り──『明暗』の翻訳を終えて」。中国における漱石の旅程を全踏破した原武哲氏の「上海パブリック・ガーデン──犬と中国人入るべからず」、そしてフランス語訳『満韓ところどころ』について濱田明氏による「仏訳『満韓ところどころ』──吉本隆明の序文とオリヴィエ・ジャメ」の五つのエッセイが収められている。
このコラムの配置も、第一章と第二章の間に「満州に渡った安井」、第三章の後に「漱石詩にみる水平線の系譜」、第四章と第五章の間に「漱石先生への祈り」、第五章と第六章の間に「上海パブリック・ガーデン」そして第七章の後に「仏訳『満韓ところどころ』」が置かれ、論考とエッセイとの内容が穏やかに連動しており、漱石研究者のみならず、一般の読者にとっても、興味深い内容となっている。
また図版が多いことも、本書の特徴である。『満韓ところどころ』に描かれた一つの風景、一つの建造物が、作品が発表された一九〇九年前後の写真と、二〇一七年、二〇一八年に行われた実地調査で撮影された写真の二つが掲載され、その二つを比較することで、我々読者もまた本書と共に、漱石の辿った『満韓ところどころ』の旅程を、二つの時代を往還しながら体験することができるのである。
さて坂元昌樹氏による第一章「大連の日の下で──語られる大連の風景と人々」は、『満韓ところどころ』という作品が、従来どのように評価されてきたか、整理するところから始められている。氏は丁寧に『満韓ところどころ』の評価の変遷をたどりつつ、「『満韓ところどころ』に対する否定と肯定、批判と擁護という従来の分散した評価軸に対して、このテクストを読み直すとすれば、どのような立場が可能なのか。そもそも私たちは、一つのテクストとそれに現れた帝国主義や植民地主義の言説との関係を、どのように理解すべきなのか」という問題意識を提示した上で、エドワード・サイードの『文化と帝国主義』の「対位法的な読解」という立場を提起している。氏によれば「対位法的な読解」とは「ある文化テクストに対して帝国主義や植民地主義に関わる歴史や事実を直接的な因果関係として結びつけるのではなく、むしろそれらを並行的で多様な差異を介在させるものとして把握した上で、生産的な理解を探求する」というものである。そして氏は、サイードが「帝国主義には触れることができないような現実、帝国主義のコントロールをすり抜けてしまうような現実の『潜在的可能性』を示す作家として」、ジョゼフ・コンラッドの『闇の億』を挙げて論じていることを指摘した上で、漱石が『満韓ところどころ』の旅行に先立って発表した評論「コンラッドの描きたる自然に就て」(『国民新聞』一九〇九年一月三〇日)を引用している。氏は「漱石のコンラッド評価が、作品中の人間描写と風景描写の関係を含めたその小説技法の持つ特異性に注目」していることを挙げ、漱石のコンラッド批評が『満韓ところどころ』を読む上において、「テクストの中の人間と風景の語りそのものの持つ含意を、その語りの方法の分析や事物や事象の持つ象徴性の解釈を通して、改めて注意深く読み直すことの可能性を示唆」しているとして、『満韓ところどころ』の記述にサイードの指摘する「ゆらぎ」が含まれていることを指摘する。そして「紀行文『満韓ところどころ』の中で漱石が訪れた街の一つである大連を対象に、テクスト中の風景や日本人たちがいかに語られるかという観点から」「『満韓ところどころ』に対して、一方的な否定や断罪に与することも、安易な支持や擁護に傾くことも、いずれも可能な限り避けながら」検討するというのである。この姿勢が本書全編を貫いていることは言うまでもない。
氏は、漱石がみた大連ヤマトホテルの玄関の石段の上から見る大連市街の様子の中から「大連の日は日本の日よりも慥かに明るく目の前を照らした。日は遠くに見える」という箇所と、「慥向うの岡の上」の「オベリスク」の箇所を引用し、この「オベリスク」について「オベリスクは古代エジプトに起源を持ちながらも後にローマ帝国によって略奪の対象となった戦争と暴力の記憶を体現するものであることを考え合わせた際に、重要な象徴性を帯びるだろう。大連における同時期の日本人による支配と都市建設の背後に潜む歴史性が、そこに顕在化していると思われるからである」と指摘する。また旧日本統治時代以来の古い建物である「化物屋敷」(本書によると「日露戦争当時に日本軍病院として使用された建物」であり、「中村是公ら満鉄関係者が大連に渡った当初に、満鉄の仮事務所を設置した場所」で、現在は「満鉄で働いている『下級社員』の居住区」であるという)と呼ばれる、古びた薄暗い建物の「細い廊下の曲り角で一人の女が鍋で御菜を煮ている光景」(十六)に遭遇し、「薄暗い『化物屋敷』で生活する日本人の生活」や「大豆の塵に煙る『油房』での中国人の過酷な労働を語る叙述は、共に当時の大連において厳しい日常を生きる人々への普遍的な人間的まなざしが存在するように思われる。その人間的まなざしを捉えうるとすれば、それはテクストの帝国主義的な要素を批評するものではないか」として、「支配者の側(満鉄社員の家族)と被支配者(中国人労働者)という自明の対立関係のみにとらわれることなく、両者についての語りを並列的に捉える視点は、このテクストの持つ可能性を拓く」と指摘するのである。まさにサイードの「対位法的な読解」であろう。
さらに氏は「テクスト『満韓ところどころ』と並行的に読むことで新たな生産的な読解を生み出す可能性を持つテクスト」として「一連の幸徳秋水の著作」『廿世紀之怪物帝国主義』を挙げ、「『化物屋敷』での見聞を含めて、この中国・朝鮮旅行における漱石は、現地での日本帝国主義のもたらす状況に対して、複雑な違和の認識を語っているように思われる。そしてそのような違和の認識は、『満韓ところどころ』の中では『ゆらぎ』を含む語りでしか語られなかったものの、その後の小説へは確実に継承されていくのではないか。その意味で、漱石にとってのこの中国・朝鮮旅行は、無視できない認識上の切断としてあったのではないかと評価したい」と結論付けている。
さらに筆者が興味を引かれたのは、西槇偉氏の「老人を轢いた馬車の乗客は誰か──『盛京時報』の記事を手がかりに」である。あたかも一篇のミステリーのように、当時の地図、現場の見取り図、そして『盛京時報』の記事を手がかりとして、「四輪馬車の乗客は日本人で、しかも満鉄の重役だった」という事実にたどり着き、「紀行文に事故車の乗客にまったく触れないことは、思えば少々不思議なことではある。こうして、事実が明らかとなってみれば、それを伏せた理由も明瞭であろう」として、「満鉄の招待で旅した漱石」が「満鉄の宣伝も兼ねた紀行文に満鉄の重役の乗った馬車の事故を当時の主要メディアである『朝日新聞』に書けるはず」がないことを指摘し、隠蔽された事実を明らかにしている。
また「現地の視点からの実証的研究」ではないものの、ロラン・バルトの「文体は(中略)〈体液の変質〉である」として、『満韓ところどころ』の文体こそ、後の「漱石的ヒロイン」たちのイメージと描写に連綿と受け継がれていることを指摘した李哲権氏の第七章「体液の変質としての文体 孤独な言語としての文体」も興味深い。まさに本書は、新たな『満韓ところどころ』研究の地平を切り開いたと言えるだろう。