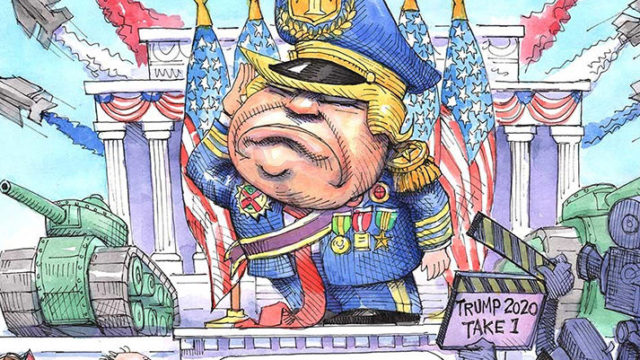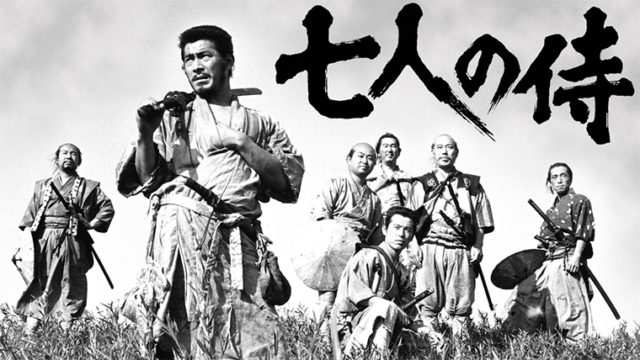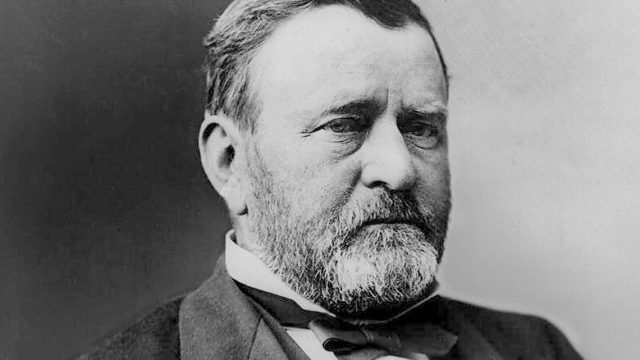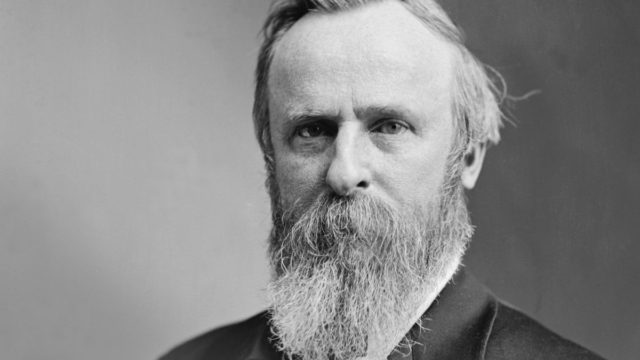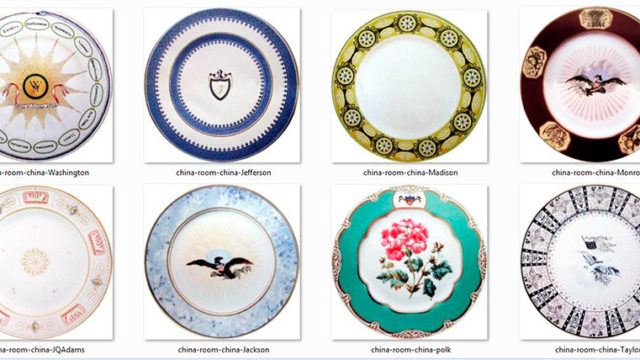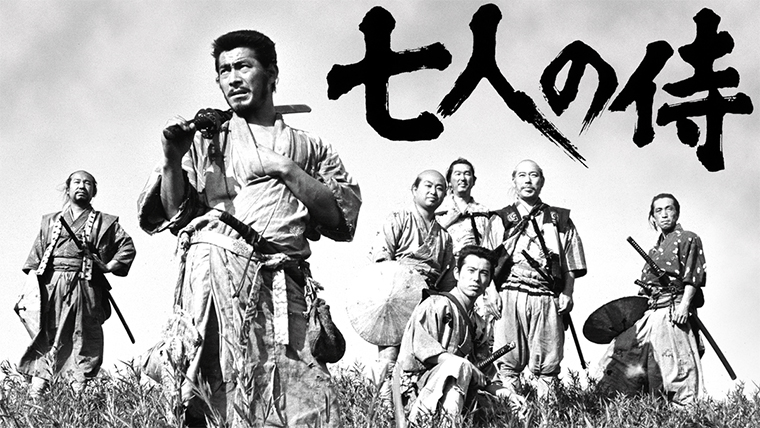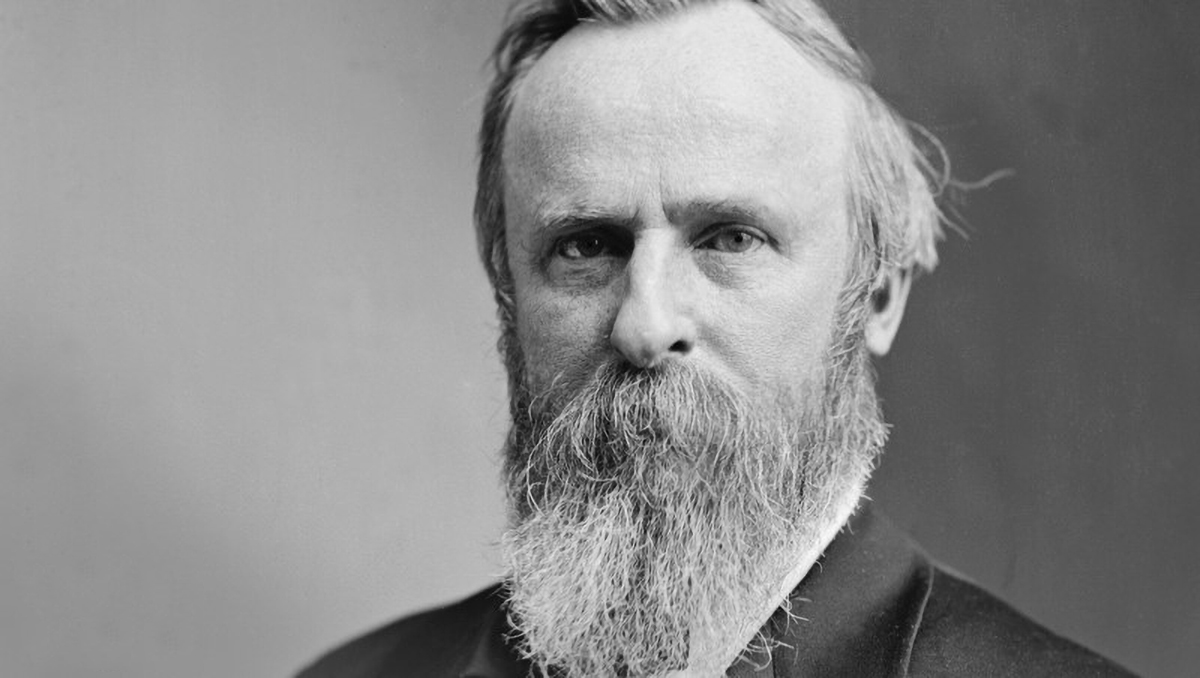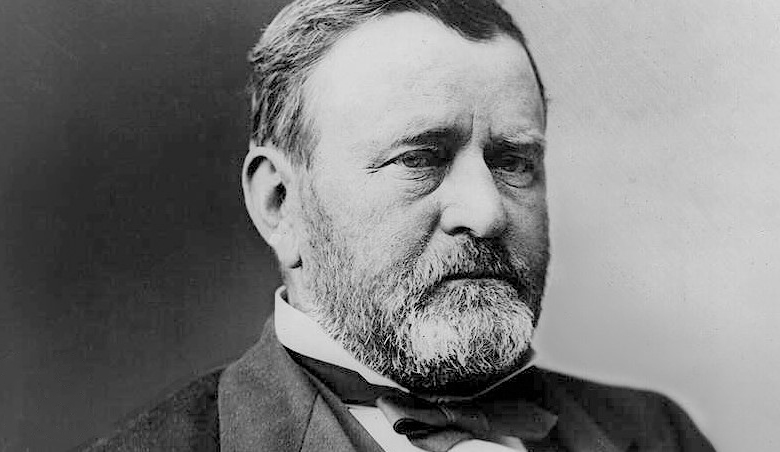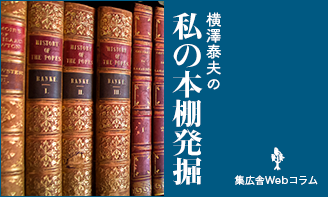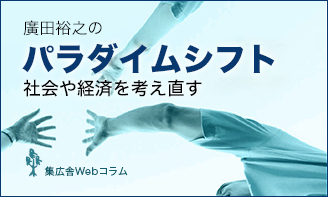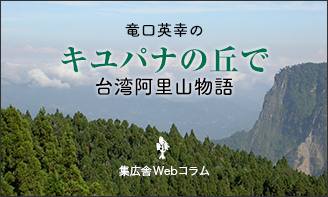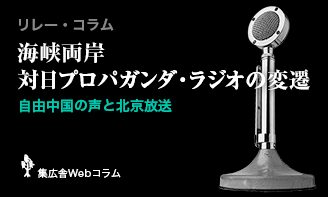アメリカがメキシコとの戦争に勝利してカリフォルニアを手に入れ、大西洋と太平洋の両洋に面する巨大国家としての道を歩み始めたころ、国を揺るがす「市民戦争(南北戦争=1861年~1865年)」が起きた。合衆国から離脱した南部11州は「コンフェデラシー・オブ・アメリカ(南部同盟)」を結成し、大統領と副大統領を選び、合衆国と同様の政治体制を敷いて宣戦した。第16代合衆国大統領エイブラハム・リンカーン率いる「ユニオン(北部連合)」にとって、南部は“反乱国家”だった。 南部ジョージア州を舞台にこの時代を描いた1939年の映画『風と共に去りぬ』の冒頭、女声合唱が緩やかにハミングで歌う南部同盟の国歌「ディキシーズ・ランド(南部の大地)」は葬礼の野辺送りを思わせる。夕暮れ時、牧童や牛飼いたちが家に戻る姿を背景に、映画の脚本陣に加わったベン・ヘクトの手になる文言が映し出され「かつて綿花栽培で栄え古き良き南部と呼ばれたこの土地の繁栄と貴族さながらの文化は、今では夢でしかなく、風と共に去ってしまった(要約)」と全編を暗示する。
ご購入手続きは「codoc株式会社」によって代行されます
コラムニスト