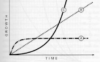芸術区で触れる民族文化
昨年の秋、特に目的もなく訪れた雲南省昆明の芸術区「創庫」。実はこの知る人ぞ知る「創庫」は、北京の有名な芸術区、「798」よりさらに早い時期に形成された、ロフト型としては中国で最初の現代アートの集積地だ。画廊や芸術家のアトリエ、個性的なレストランなどが集まる敷地は、798と同じく国営工場の跡地を再利用したもので、798と時期こそ異なれ、やはり一時期は取り壊しの危機に直面した。だが、その後何とか一命をとりとめ、これまた798と同じく、現在は商業化の波をかぶりつつある。
もっとも、今回の訪問での印象は、先回訪れた数年前と比べ、若干様変わりこそしているものの、それでもまだ798よりこじんまりとして、静かで親しみやすい空間だというものだった。

▲昆明市内にある芸術区「創庫」

▲「創庫」内にある「源生坊」の入り口
そののんびりとした空気に導かれるように、アートスペース、「源生坊」で開かれていた展覧会、「雲南郷音──源生坊民族民間芸人肖像主題展」を覗いてみた。民間芸人のさまざまな表情を捉えた肖像画が並んでいるが、描かれている芸人もさまざまなら、描いている作家もさまざまで実力派ぞろい。雲南のみならず現代中国を代表するアーティストの一人である毛旭輝氏の作品もある。

▲「雲南郷音」展の風景

▲作家の毛旭輝氏とその作品
その後、展覧会の背景を聞いてさらに驚いた。このスペースは雲南の少数民族の伝統音楽・舞踊文化の発掘、記録、伝承、公演に力を注いでいる非企業組織「雲南源生坊民族文化発展センター(以下、源生坊)」によって運営されており、肖像画に描かれているのはこのセンターが企画した公演に参加した民間芸人。同センターの活動の趣旨に共鳴した画家たちがセンターの経営を助けるために描いたという。

▲地元で活躍する若手作家、黎陽煕氏とその作品
きっかけは取材
「源生坊」のメンバーはいずれも雲南の僻地の少数民族の村に住んでいる。イ族、ワ族、ハニ族が含まれ、その数は創立当初は22人だったが、現在は50人余り。いずれも歌や踊りに長けており、1993年から2000年までは、田豊氏の創立した「雲南民族文化伝習館」のメンバーだった。同分野の先駆者として、田豊氏は十数年にわたって少数民族の伝統音楽や伝統舞踊をめぐる調査、発掘を実施。その保護と伝承のために奔走した。ちなみに、「伝習館」が当時収集した舞踊の動作の多くは、その後有名な舞踊家、楊麗萍氏の踊りの動作にも取り入れられたという。
だが、さまざまな理由によって「伝習館」は2000年に閉鎖。その事業は劉暁津氏によって受け継がれた。劉氏は、かつてテレビ局の記者として田豊氏をインタビューしたことをきっかけに田氏と知り合い、その活動に深く共鳴。田氏と伝習館をめぐるドキュメンタリー番組まで撮影したのだった。劉氏はやがて「伝習館」の偉業を継ぐべく「源生坊」を設立。少数民族の文化を発掘、伝承し、発展させるための新たな模索を始めた。
雲南は山が多く、交通が不便で、季節や気候によっては、僻地にある村との行き来は命がけだ。だが、源生坊のメンバーは、各地の農村を熱心にめぐり、伝統的な歌舞の伝承情況を調査。その保護にあたっても、現地での伝承にこだわるため、頻繁に昆明と農村部の間を行き来しているという。
幸い今回、筆者はその困難に満ちた活動をまとめている劉暁津氏と、女史を陰で支えている曹箏琪娜氏に詳しくインタビューする機会を得た。

▲源生坊の劉暁津氏(右)と曹箏琪娜氏(左)
学び終えれば600元
劉氏の話によれば、源生坊は、民族の音楽や舞踏を伝承させるため、「普及クラス」と「アドバンス・クラス」を設けているという。2005年にスタートした「普及クラス」では、「郷村計画」というプロジェクトを実施。源生坊のメンバーで、それぞれ異なる村に住んでいる芸人たちに、平日、現地の若い人々を対象として、民間の歌舞を教授させるというものだ。出資は香港のサポーターが個人で支えているという。
一方、2012年から設けられた「アドバンス・クラス」でも、経験ある芸人が若い世代に教える形をとっているが、対象はやや上級者。毎月一人、源生坊の責任者が農村に送られ、源生坊と芸人が共同で定めた伝承内容の修得の程度をテストする。例えば、歌い終えるのに30分かかる某伝統歌謡を3カ月で学び終え、テストの際に全部完璧に歌い終えることができた者に対しては、証書と奨励金600元が与えられるという。当然、教えた芸人にも生活費の補助や合格者数に応じた奨励金が支払われる。
この方法は、見方を変えれば「褒美で釣っている」とされかねず、「不純な動機で学ぶ者もいるのでは」と賛否両論であろう。だが劉氏によれば、現段階でもすでに、多くの歌や踊りが、断片的にしか残っておらず、何らかの応急措置をとらなければ、無数のすばらしい音楽や舞踊の伝統が途絶えてしまうのだという。そして実際のところ、貧しい農村であればあるほど、「時は金」であり、今の若い人たちのほとんどは、こういう報奨制度でもとらない限り、すぐには生活の糧にならない伝統芸能を苦労して学ぼうとはしない。
公演が励みに
現地での伝承は、舞踊や歌謡が土着性を失わないためにも、有効だ。だがそれにしても、源生坊のメンバーが毎月赴き、しかも奨励金まで払うのでは、あまりに源生坊側の負担が大きすぎるのではないだろうか。ではなぜ学校などの形態をとらないのか? この質問に対し、劉氏は「学校には場所が必要」、「中国の制度では、学位を与えられる学校を設立するのは難しい」、「学費を徴収しづらい」、「農村で学べば、農閑期や農作業等の合間を利用して学べ、仕事と両立できる」などの理由を挙げた。
一方で、源生坊では、学んだことを舞台のプログラムにまとめ、自らの擁する小劇場や国内外の各地で公演することで、伝統の担い手たちを励ますことにも熱心だ。2005年には、アメリカ東部で30日にわたる巡回公演を実現。中でも圧巻だったのは、「中国文化ウィーク」のイベントの一環として、アメリカの「ザ・J・Fケネディ・センター・フォア・ザ・パフォーミング・アーツ」で行われた公演だ。
そのフィルムを観ると、場所は舞台ながらも雰囲気はお祭りの賑わいで充満。歌い手たちの素朴で力強い声は広大な山野をイメージさせる。自由で時にユーモアに満ちた踊りの数々も、多彩な風習の存在や微妙な男女の感情のやりとりなどを生き生きと表していた。そして、観衆の盛大な拍手や喝采は、それらが呼び起こす、民族文化の豊かで多彩なイメージに呼応してのものであるのがひしひしと伝わってきた。
こういった海外での公演やテレビへの出演は、出演者たちを励ますとともに、若い学び手たちの夢と希望を育てる。劉氏は日本での公演もぜひ実現させたいと願っているという。
ショーと伝承を両立
だが、ここで疑問が生じる。ショー・ビジネスと伝統の継承は本当に両立できるのか、というものだ。例えば北京の京劇を例にとれば、ショーとしての観光客受けをねらう余り、演目が有名で分かりやすいもの、しかもその断片に集中し、多くの優れた演目が、ただマイナーであるがために演じ手を失うというアンバランスに陥っている。この問いに、劉氏はこう答えた。「確かに、似たフレーズが延々と続くものなど、聴衆が飽きやすい演目は、舞台にはのせません。でもそれらは、舞台とは関係のない稽古の場できちんと伝承させています」。
しかし、「踊る阿呆に、見る阿呆」の歌詞で知られる阿波踊りの歌にも「同じ阿呆なら、踊らなければ損」とあるように、民族の歌舞は往々にして「大衆参加型」であり、舞台で「鑑賞」する形をとること自体が、少数民族の民間歌謡や舞踊が本来もつ、インタラクティブな面を変容させることになりかねない。
だがこの問いを、急速な社会の変化の中で、存続自体が危うくなっている芸能について発するのは酷なのかもしれない。農村での稽古の過程のビデオを見ると、その雰囲気は日本の盆踊りにも似ていて、周囲も楽しみながらの、和気あいあいとしたものだった。
一方で、歌垣で歌われる歌謡などは、メロディだけは忠実に受け継がせるが、その歌詞は歌い手の気持ちに合わせて変えても構わないなど、芸人たちの創作の余地も十分に残しているという。
自覚を育てる
これ以外にも、源生坊では、各地での民族歌舞コンテストの開催を積極的に支持している。また、大学などの研究機関の研究者と民間芸人との橋渡しもし、芸人たちに学術的な国際的なフォーラムや学術会議の場で発言をさせたり、民間の歌や舞踊のパフォーマンスをさせたりし、民族芸能の重要性や具体的な内容を研究者らに伝えている。
劉氏によれば、源生坊の活動は政府からの資金的援助を一切受けていないという。経済的にはかなり苦しいが、ひとたび公的な援助を受けると、干渉も免れないからだ。だが救いは、その活動を通じ、源生坊の芸人たちの多くが、自らの民族文化の伝承者としての自覚を高めつつあることだ。
理想としては、いずれは、源生坊の助けを借りず、それぞれの民族が自発的に自力で、自民族の伝統の発掘、継承、発展に取り組めることが一番なのであろう。だが、経済や社会の急速な発展や変化のひずみによって、多くの伝統芸能が危機に晒されている今、源生坊の試みは、文化継承の一つの方法として、十分参考に値するように思う。