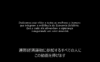日本の純伝統邦楽に於ける「流派」「流儀」の概念とは

◀地歌・箏曲の中でも異色な存在の「胡弓(写真右)」、左の沖縄の「胡弓(くーちょー)」も、共に「三弦(沖縄では三線とも言い、地歌では三絃とも書く)」に似せて作られる。が、いずれも胴の下に棹が突き出て居り、これを軸に楽器の面が変わり、空中の同じ位置を往復する弓に弦を選ばせる。この「ステッキフィドゥル式」は、西域弓奏楽器の基本である。
「端唄」と「小唄」に於ける呼称
次に「小唄」「端唄」であるが、そもそもが花柳界で発展した流儀(広義)であり、そのルーツを辿れば、江戸時代はおろか、平安時代にまで優に行き着いてしまう。勿論詳しい記述はほとんど存在しない。また、花柳界の芸子さんたちは、置屋馴染みの邦楽の師匠に稽古を授かった。当然、この系譜も、星の数ほど存在しそうなものであり、系図を見出すことは不可能だ。
一般に、「端唄が姉で、小唄が妹」と、「端唄」が歴史的に先行するように言われるが、それは「端唄」がかなり古い民間歌謡をも演目に持つからと、「小唄」が「小唄」の名称を確立し、「端唄」と一線を画し、流派的なものも現れたのが「端唄」の名称が流布した後である(らしい)こと、及び、有名曲の多くが近代に創作されたことなどに起因する。しかし、その源流は、極端な言い方をすれば、地歌・箏曲、浄瑠璃、長唄以外の全ての日本歌謡、一部、民謡の要素さえ含むのであるから、言ってしまえば、どちらが古いという話しはさして重要ではないし、系譜を探ることも無意味なのだ(筆者は試みたのだが)。ただ、近代の小唄には、後述のような明らかな流派が生じ、「端唄」と異なる個性を育てることに大きく貢献し、現代の姿に見られる多様な芸能に至らしめたことも事実である。
江戸末期には、浄瑠璃や長唄のような比較的組織化された流儀「うた沢」が生まれたが、ほどなく、有名な対立によって「寅派」と「芝派」に分裂した。「うた沢」は、既成の「端唄」「小唄」とは一線を画し、厳格な家元制度と厳しい審美眼によってその質を上げ、「俗謡」と大して違わない評価であった「端唄」「小唄」の世界から、地歌、長唄、と並ぶ地位を目指した。このことは「端唄」「小唄」の担い手たちに大きな刺激となり、後の手本になったことは大いにあるだろう。
幕末から明治にかけては、清元節から小唄にも情熱を注いだ有名な「清元お葉」が現れ、弟子の「横山さき」より後は、比較的確かな系譜が確認でき、流派も確立した。これを「江戸小唄」と呼ぶ(勿論以前から在ったのだが)。「横山さき」の門下からは、堀小多満の「堀派」、田村てるの「田村派」、小唄幸兵衛「小唄派」、蓼胡蝶の「蓼派」、吉村ゆうの「吉村派」、春日とよの「春日派」などが生まれ、いずれも「派」を名乗るとともに、家元制度とその徒弟制度が確立していった。
「端唄」も「小唄」も、近代の大教室の時代になると、次から次に「派」が現れ、現存するものだけでも合わせて百派は優に超えるとも言われる。中には、何らかの意図意匠を持って「会」を付けるところもあるが、基本的に「端唄」「小唄」の「分家・分派」の名称は「派」である。

◀中央:筆者の小唄の師匠・里園志津栄先生。右:娘さんの現家元・志津代先生。志津栄先生は筆者の大叔母のような存在。筆者実の祖父の晩年の相方さんだった。
「地歌・箏曲」に於ける呼称
「端唄」「小唄」の後になってしまったが、「地歌・箏曲」は、本来「唄もの」の筆頭に挙げるべき、最も古い歴史を持っている(実は、後に回した意図もあるのだが)。そして、恐らく、日本の純伝統邦楽中で、延べ人口は、長唄を上回り最多ではないかと思われる(※)。ならばそれなりに、お家騒動や分裂トラブルが耐えなかったはずなのだが。地歌の場合、ある決定的な理由(後述)で、この問題が基本的に解決されていて、後世、その箍(タガ)が緩くなった頃には、何らかの方法で、この問題を慎重かつ上手く処理しているように思える。
以下に述べる「ある決定的な理由」は、地歌・箏曲の根本的な事情によるもので、それによって、そもそも地歌・箏曲には、所謂流派の概念はなかったのではないか、という解釈さえ成り立つ。
※ 当道座が廃止され一般に門戸が開かれてから急増したに違いないが、それ以前から、当道座の全国展開によって、他流儀(広義)とは比べ物にならないほどの大組織であったに違いない。また、近代以降の感覚と比べ、医学水準、受診水準のみならず、栄養失調なども加わり、障害を持つ子供も多かったに違いない。
そもそも地歌は「三味線音楽(16世紀末)」が先行し、「箏曲(17世紀中期)」「三曲(17世紀末)」が追従したのだが、「三曲」に加わる胡弓を別格として、三味線とお琴はそれぞれの二派を形成せず、ある意味、曖昧に大きなまとまりを持ち続けていた。その結果、「地歌・箏曲」という一般には、その違いや内容が良く分からない音楽大系が生まれたのである。一方を「箏曲」と言うからには、「地歌=三味線音楽か」と言うと、必ずしもそうではない。
この「三味線とお琴を分家させない方針」は、誰かの案によるものではなく、明治四(1872)年に廃止されるまで、地歌・箏曲の担い手が属した当道座(簡単に言えば、盲人の為の、鍼灸、按摩、音楽の職業訓練・斡旋、管理組織)が存在したからに他ならない。
当道座に於ける楽師の職のそもそもは、有名な「平家琵琶」であり、それゆえ外来の三味線を琵琶撥で弾いた(筆者持論では、そうでない三味線の系譜も在る)。その結果、三味線は「世界で最も切れやすい弦を、世界で最も破けやすい表面の上に張るにもかかわらず、世界で最も大きく、最も重く、先端が最も鋭い撥で弾く」という驚嘆する技法の楽器となった。
この当道座の組織の堅固さは、平家琵琶の時代に組織から抜けた楽師や、それらが別な組織を作らんとしたことをことごとく鎮圧したことでも知られている(それでも抜けた楽師たちは、独自に「盲僧座」を構成した。九州で活動し、後の薩摩、筑前の琵琶に影響を与えた一派は有名)。
要するに、当道座の楽師たちが、組織の管理統制とは別に、勝手に「三味線専門流派」と「箏専門流派」を作ることは許されなかったに違いない。また、名だたる名検校のような作曲家であり名教育者である者を別として、現場の一介の楽師にとっては「どちらも演奏でき、演奏することが許されている」に越したことがない。このことは意外に誰も語っていないようだ(当たり前だからか)。当然、盲人楽師たちが、その音楽や音楽史を書き残す習慣も発想もなかっただろうし、当道座廃止後から今日の地歌・箏曲の担い手たちが当道座時代のことを詳しく書くこともなかった。
「能・狂言」
最後になってしまった「能・狂言」こそは、地歌・箏曲よりも遥かに古い芸能であり、地歌・箏曲、浄瑠璃から長唄に至るまで、この「能・狂言」に取材した演目が多くある。既に世の中に「能・狂言」で知られた演目をそれぞれの流儀(狭義)で演じることによって、その芸風が分かりやすくなるということだ。今で言う「カバー」である。
「能(能楽)(シテ方)」には、観世流、宝生流、金剛流、金春流、喜多流の五流があり、「狂言(方)」には、大蔵流、 和泉流の二流がある。すなわち,「能・狂言」は、全て「流」なのである。