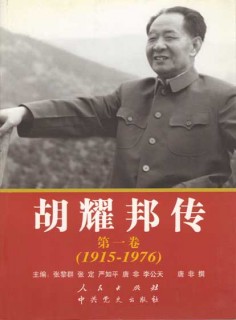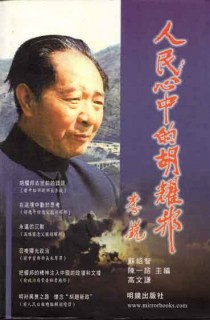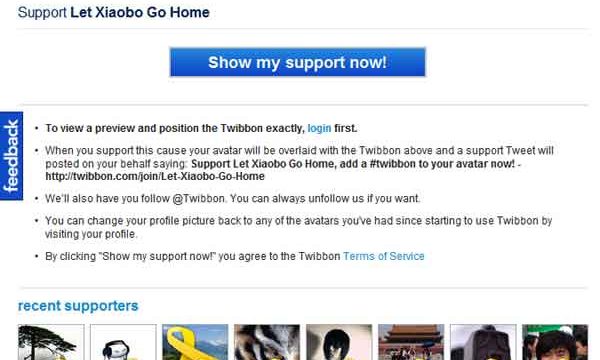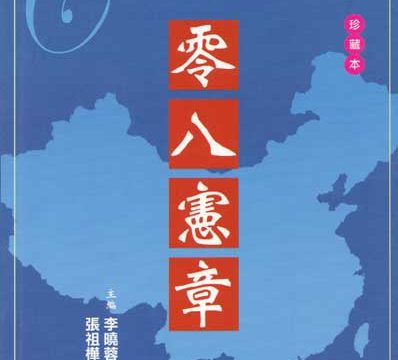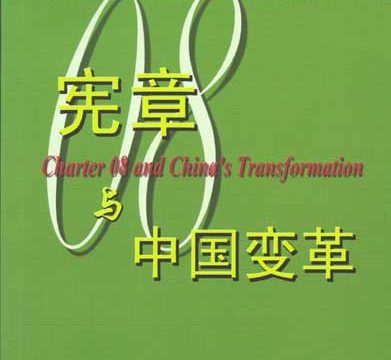山というよりは小高い丘というほどのなだらかな斜面を登りきったところに、胡耀邦の墓地はあった。生い茂る木々が切り拓かれ芝生の斜面が続くその先に、胡耀邦のレリーフが刻まれた巨大な墓碑がたたずんでいた。胡耀邦、1915ー1989。墓碑には、中国少年先鋒隊、中国共産主義青年団、そして中国共産党の徽章がそれぞれ刻まれている。
胡耀邦の墓地は、共青城の町はずれにある。訪ねたのは随分と前のことだが、案内してくれた共青城の担当者が誇らしげに町の歴史を語りながら、資料室に展示された共青城の立体パノラマを見せてくれたことを覚えている。共青城とは、文字通り中国共産党の青年の町だ。江西省の省都である南昌市と、廬山の麓で長江を臨む九江市のちょうど中間に位置する共青城は、中国共産党と深い関わりをもって誕生した。1955年に上海の青年有志98名が農地を切り拓いて共同生活を始め、「共青社」と名付けたという。1984年、当時総書記だった胡耀邦が2回目の視察に訪れて「共青城」と命名し揮毫したことから、胡耀邦ゆかりの地となった。
共産主義の志を頂いた青年たちによって開墾された町は、わずか50年余の歴史の中で、中国の歩みと共に変貌してきたのだろう。鄧小平の南巡講話で経済開放の大号令が発せられると、共青城は開発区に指定されて外資を導入し、服飾品の生産に力を入れるようになったという。巨大な「共青城」の看板が掲げられたダウンジャケットの模範工場を見学したことを思い出しながら共青城のホームページを調べてみると、服飾と観光産業を宣伝するウェブサイトの片隅に、特に説明もないままに江西共青城胡耀邦陵園の小さな写真が1枚掲載されていた。
生前、胡耀邦は李昭夫人に「亡き後は、青山緑水に埋葬してほしい、つまり共青城だ」と語っていたという。1990年12月5日、その遺言のとおり胡耀邦の遺骨は共青城の富華山に埋葬され、親族のほか当時共産党中央弁公庁主任だった温家宝も参列した。北京でもなく、故郷の湖南省でもない共青城に眠ることは、胡耀邦のささやかな願いだったのだろう。訪問した折、同行者たちと黙祷を捧げて振り返ると、眼下には緑が広がり、川とも湖とも知れないいくつも流れは、遥かに霞む鄱陽湖に繋がっているようだった。その景色を思い出すたびに、「魂の憩う処」とは、こういう風景なのかもしれないと思う。
「改革派の領袖」、「党内民主派の旗幟」と言われた胡耀邦は、1980年代に中国共産党党主席、党総書記を歴任し、趙紫陽とともに鄧小平時代を支えた人物だった。鄧小平のもとで改革・開放政策を推進した胡耀邦と趙紫陽は、旧ソ連の集団指導体制を例えた三頭立ての馬ぞりになぞらえて、「トロイカ体制」とも称された。文化大革命の終結後、社会の混乱と共産党内部の権力闘争が激しさを増した転換期の中国において、胡耀邦の存在は改革の象徴だった。特に、その晩年について語ることは、中国の改革・開放政策の明と暗を語ることでもある。共青城に眠る胡耀邦に思いを馳せながら、その軌跡を辿ってみたい。
胡耀邦は1915年に湖南省に生まれ、1933年に中国共産党に入党して翌年には長征に参加し、建国以前から党の要職を歴任した。建国後は中国新民主主義青年団とその後身の中国共産主義青年団で書記を務め、文革期は迫害されて労働に従事したが、名誉回復後は中国科学院の幹部として復活し、1977年には中央党校副校長、中央組織部部長に就任した。文革後の中国が、大きく舵を切ろうとしていた時期だ。
当時の中国では、1976年に毛沢東が亡くなり四人組が逮捕されたが、それらが文革との決別と新時代の到来を約束したわけではなく、党主席に就任した華国鋒は、「毛主席の決定したことはすべて断固として守らなければならず、毛主席の下した指示はすべて変わることなく守らなければならない」という「両個凡是(二つのすべて)」を強調し、亡き毛沢東の権威を借りた権力強化を図っていた。それに対し「三たび失脚し、三たび復活した」鄧小平は、「実事求是(事実に基づいて真理を求める)」を提唱して思想解放を推進した。脱文革を推進する立場から「凡是派(二つの全て派)」を批判する理論闘争の幕開けとなったのが、1978年5月11日付『光明日報』に掲載された「実践是検験真理的唯一標準(実践は真理を検証する唯一の基準である)」と題した特約評論員論文だ。『人民日報』、『解放軍報』にも次々と転載されたこの論文の起草と掲載に尽力したのが、中央党校副校長の胡耀邦だった。
当時、胡耀邦のもとで中央党校の理論工作に従事していた瀋宝祥の『胡耀邦與真理標準問題討論』(江西人民出版社、2005年)には、理論闘争の展開と胡耀邦が果たした重大な役割が詳述されている。1978年12月の11期三中全会において鄧小平路線が確立し、改革・開放政策がスタートした背景には、思想解放の基盤を固めた胡耀邦の存在があった。
脱文革を推進した胡耀邦は、文革期のみならず反右派闘争にも遡り、冤罪事件の解明と多くの失脚者たちの名誉回復に努めた。復権した党幹部はもとより、知識人や共青団人脈の登用は、胡耀邦の周辺に改革への期待にあふれた知的集団を形成したといえる。1980年代前半は改革・開放政策のさらなる推進に努め、対外開放の面では1983年11月に日本を訪問し、その後3000名の日本青年代表団訪中を実現させた功績が特に語り継がれている。
「真理の基準問題」によって一応の決着がついたかに思われた党内の権力闘争は、その後も保守派と改革派の対立が続き、影響力を振るい続ける老幹部たちの存在や政治改革に対する鄧小平自身のブレによってさらに複雑化した。1986年9月の12期六中全会で「ブルジョア自由化」に反対する「社会主義精神文明建設の指導方針に関する中共中央の決議」が採択されると、胡耀邦を支持して改革を求める知識人や学生たちの不満が噴出し、同年12月に安徽省の中国科学技術大学で発生した学生デモが全国に波及して、各地で大規模なデモが繰り広げられた。しかし、そうした学生運動は、皮肉にも胡耀邦の失脚を加速させる結果となった。保守派の激しい批判の矛先は、胡耀邦に向けられたのだ。
胡耀邦失脚の背景は、依然として明らかにされていないことが多い。自ら辞表を提出し、翌年1月16日の中央政治局拡大会議で総書記を辞任した胡耀邦には、「集団指導原則に対する違反」、「政治原則問題の誤り」という罪状が突きつけられた。だが、胡耀邦失脚の謎を解き明かす鍵は、中央政治局拡大会議の直前に中南海で開かれた「民主生活会」にある。
改革派論者として知られる李鋭は、胡耀邦の生前に数回にわたって懇談し、亡くなる10日前の談話を「胡耀邦の政治的遺言」として強調している。談話をまとめた「胡耀邦去世前的談話」(『李鋭近作――世紀之交留言』((香港)中華国際出版集団有限公司出版、2003年)に、その「民主生活会」の様子が記されている。「民主生活会」とは党の要人たちが意見交換する集まりで、「ブルジョア自由化」への対応について自己批判を行った胡耀邦に容赦ない批判が浴びせられ、胡耀邦批判は6日間も続けられたという。
新華社元高級記者の楊継縄は、李鋭の文章を引用しながらさらに関係者の証言を加え、『中国改革年代的政治闘争』((香港) Excellent culture press、2004)でその様子を伝えている。保守派だけでなく、親友や改革派の同志である趙紫陽までが批判的な発言をしたため、胡耀邦は会場の懐仁堂を離れると、思わず声を上げて泣いたという。総書記という国家指導者の人事が、正当な手続きによらずに「民主生活会」という名の不合理で非民主的な方法によって辞任に追い込まれたことが、胡耀邦の悲劇だった。
胡耀邦の慟哭は、その後に続く幾多の悲劇の序章にすぎなかった。1989年4月8日、胡耀邦は中央政治局常務会議の席上心臓発作を起こし、同月15日に帰らぬ人となった。各大学で胡耀邦の追悼活動を行っていた多くの学生たちは、天安門広場へ向けてデモ行進し、人民英雄記念碑に献花して座り込みを行った。胡耀邦追悼と民主化要求の運動は急速に拡大し、そして6月の天安門事件へとつながっていった。
2005年秋、当時北京で暮らしていた筆者の最大の関心事は、胡耀邦の生誕90周年がどのように記念されるかということだった。胡錦濤国家主席が提起したという記念行事は、当初11月20日の生誕記念当日に人民大会堂で2000人規模の記念大会が開催され、「事実上の名誉回復」が行われるだろうという情報も聞かれたが、真偽のほどは定かでなかった。いつ、どのような形で胡耀邦記念が行われるかということは、現代中国政治史の時計の針を1989年に巻き戻すだけでなく、2005年時点での党内政治力学でもあった。
記念行事は、結果的に生誕記念2日前の18日に非公開の座談会として開催され、300名余が出席した。温家宝総理が出席し、呉官正中央規律検査委員会書記による司会で執り行われ、曽慶紅国家副主席が記念講話を発表して次のように胡耀邦を讃えた。
「胡耀邦同志は、経験豊かにして忠実な共産主義の戦士であり、偉大なプロレタリア革命家・政治家であり、わが軍の傑出した政治工作者であり、長期にわたって党の重要な指導的職務を担当した卓越した指導者である」
記念講話では当然ながら胡耀邦の失脚に関する言及はなく、また「偉大なマルクス主義者」という言葉もなかったが、「我々は胡耀邦同志に学ばなければならない」という言葉が4回繰り返された。その人柄を偲び、在りし日の胡耀邦に学ぼうというメッセージが発せられたのだ。だが、当日、胡錦濤国家主席はAPEC非公式首脳会議出席のため韓国を訪問中だった。国家指導者の外遊中に開催された非公開の座談会は、皮肉にも胡耀邦記念が敏感な政治問題であることを印象付けることとなった。翌19日付『人民日報』1面には、APECでの外交活動がカラー写真付きで報じられ、座談会開催を伝える記事は紙面の一番下に写真もなく掲載された。新華社による配信記事以外には、他紙でも独自報道は見られなかった。
控え目な新聞報道とは対照的だったのが、記念行事に先立って11月初めに発売された雑誌『炎黄春秋』(2005年11期)の特集だ。『炎黄春秋』は1991年創刊の中国近現代史中心の月刊誌で、退職した老幹部たちに人気がある。「炎黄」は中華民族の祖といわれる伝説上の炎帝と黄帝のことで、『炎黄春秋』は「中華民族の歳月」という意味だ。「詳細で正確な資料に基づき、事実をありのままに記し、飾らず、世俗におもねらず、権勢に迎合せず、事実を重んじて真実を記録し、歴史を鑑とする」という編集方針で、独特の存在感がある。
特集号の表紙裏には「紀念偉大的革命家政治家 胡耀邦九十誕辰」と題して生前の胡耀邦を伝える写真があり、20ページわたる特集が掲載された。「我們心中的胡耀邦(我々の心の中の胡耀邦)」という表題で、14名の改革派老幹部たち――田紀雲、杜潤生、任仲夷、于光遠、李鋭、閻明復、朱厚澤、呉江、李普、曾彦修、何方、龔育之、鐘沛璋、杜導正――が、それぞれ回想文を寄せた。 しかし最も注目したのは、郝懐明の巻頭論文「耀邦指導我們起草中央文件――胡耀邦與“精神文明建設決議”」だ。1986年の「精神文明建設決議」の起草に携わった著者が、当時の「ブルジョア自由化」をめぐる党内の激しい論争の経緯を明らかにしたのだ。この特集号を筆者はいつもと同じように発売直後に北京市内の書店で購入したが、伝え聞いたところによれば、発売後に中共中央宣伝部から発行停止の指示があり回収処分されたという。中宣部の指示を確認する術はないが、胡耀邦に関する報道が極めて敏感な問題であることを象徴する出来事だった。
『炎黄春秋』は、その後も胡耀邦追悼の文章を掲載し続けた。胡啓立「我心中的耀邦」(2005年12期)、李昌「我與耀邦共事」(2006年1月)、張治宇「我聴胡耀邦談防止文革重演」(2006年2月)と、胡耀邦をよく知る人物たちの回想を掲載したのだ。いずれも胡耀邦の功績を主張した文章で、まるで『炎黄春秋』という雑誌が、じわりじわりと胡耀邦に関する言論空間を押し広げているかのようだった。
2005年には生誕90周年にあわせて出版された本があった。『胡耀邦伝 第一巻(1915‐1976)』(張黎群、張定、厳如平、唐非、李公天、人民出版社・中共党史出版社、2005年)と、胡耀邦の長女による回想録『思念依然無尽―― 回憶父親胡耀邦』(滿妹、北京出版社、2005年)だ。北京の書店では新刊コーナーに2冊並べて積み上げられ、多くの読者が手に取る姿があった。伝記の表紙には、にこやかに微笑む胡耀邦の写真があったが、伝記の続編が出版されるのはいつになるだろうかと思いながら購入したことを思い出す。
翌2006年1月に香港で出版された『人民心中的胡耀邦』(蘇紹智、陳一諮、高文謙、主編、明鏡出版社、2006年)は、生誕90周年を記念して約70名の文章がまとめられた記念文集だ。『炎黄春秋』の特集号に寄稿した老幹部たちの名前もあるが、1989年の天安門事件に深く関わった知識人たちの文章もあり、停滞する政治改革への主張も多く見られた。
非公開の座談会、管理された新聞報道と独自報道への圧力、大陸と香港で出版された本の相違に示されるように、生誕90周年は記念行事よりも胡耀邦に関する言論問題が露呈された形となった。胡耀邦の功罪は広く議論されるべきだが、全面的な再評価となれば「反革命暴乱」と定義された1989年の天安門事件にも言及せざるを得ない。功績を否定することはできないが、積極的に顕彰することも難しい。中国共産党にとって、胡耀邦という存在が放つ光が強ければ強いほど、その光によって生ずる影も色濃いのだろう。(文中敬称略)