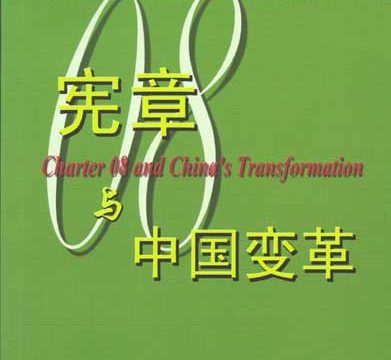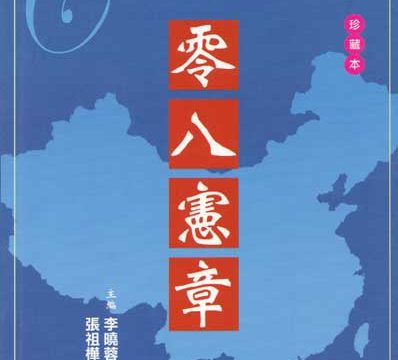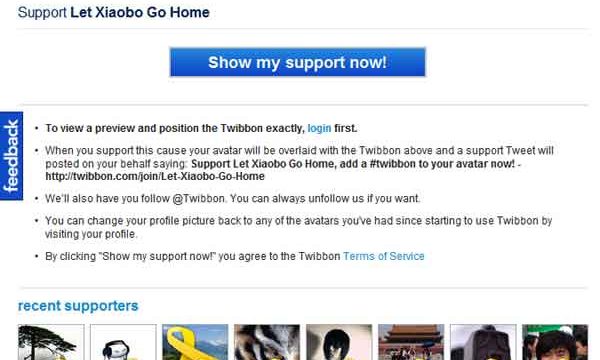『チャイナ・クライシス重要文献』
4月の中旬から読み始め、7月の後半になってようやく読み終えた本を、今あらためて手に取っている。勢いにまかせて読めば3カ月もかからなかったのだが、はやる気持ちを抑えながらかみしめるように読み進めたのには理由があった。
数年ぶりに書棚から取り出してこの数カ月間手元に置いたのは、矢吹晋編訳『チャイナ・クライシス重要文献』(蒼蒼社、1989年)の全3巻だ。ここでの「クライシス」(危機)とはつまり1989年の天安門事件のことで、当時の新聞や雑誌の記事、壁新聞、ビラ、自主出版物、公開書簡など数多くの資料が翻訳掲載されている。膨大な資料を蒐集・整理・編集・翻訳し、事件からわずか数カ月という驚くべき速さで出版された文献集は、編者の言葉にあるようにまさに「血で書かれた資料」だ。当時の民主化運動を知るためには、欠くことのできない重要史料だといえる。第1巻は1986年末の胡耀邦総書記失脚に関する資料から始まり、胡耀邦追悼が民主化要求運動へと発展した1989年4月中旬から、時間を追って運動の詳細と当局の対応を克明に描き出している。
天安門事件から20年が経った。今回あらためて読み始めたのは、天安門広場に座り込んでいた学生たちが政府に7カ条の要求を提出した4月18日で、それ以降1989年の「その日」に思いをはせながら、2009年の同じ日に該当する箇所を読み進めた。20年という時間を超えて、あの頃、あの場所で、いったい何があったのかをつぶさに知りたいと思ったのだ。もちろん、紙の上に記された文言をなぞるだけで追体験ができるとは到底思わないが、日を追うごとに緊張感を増し、悲壮感を漂わせながら衝撃的な結末に向かっていく時間の流れだけでも、せめて同じように感じることができないかと考えた。学生たちの希望と挫折、知識人たちの壮大な使命感、市民の情熱的な支持は、本来人民を護るべき人民解放軍に打ち砕かれて流血の惨事となり、「反革命暴乱」として鎮圧された。
文献集を読みながら、幾度となく天安門広場を思い浮かべた。世界最大の広場を初めて凝視したのは、事件当時のニュース映像だった。その年、本放送を開始したNHK衛星放送は連日広場の様子を報道していて、自宅の居間のテレビでニュースにくぎ付けになっていた筆者は中国語を学び始めたばかりの高校生だった。広場では自分よりも少し年上の大学生たちが悲痛な面持ちで何かを叫び、憧れの場所には戦車が行き交っていた。何が起こっているのか、なぜそうなったのか、学生たちはいったい何のためにそこにいるのか、それらを理解するだけの知識もなく、得体の知れない恐怖に戸惑いながら、未だ見ぬ中国に抱いていた漠然とした憧れや「悠久の中国」といったステレオタイプのイメージが砕け散ったことだけが確かだった。それでも、その後も中国にこだわり続けている理由のひとつは、あの学生たちの姿が、記憶の片隅で時折思いがけないほど鮮明に浮かび上がることがあるからだ。
断り書きをしておくが、筆者は当時の運動を無批判で美化するつもりはない。ハンストで倒れ運ばれていく学生たちやリーダーたちの感情的で扇動的な演説、激高し無秩序になっていく群衆たちの熱狂は、「民主化運動」のヒステリックな一面をさらけ出していた。当時、天安門広場にあったのは夢や理想だけではかったはずで、事件は単純な善悪二元論で整理できるようなものではないだろう。だからこそ、様ざまな事実をひとつずつ拾い集めるように読み解きながら理解していきたいのだ。
初めて天安門広場に立ったのは事件から5年後のことで、その広さに圧倒されながら歩いた。それからいったい幾たびあの広場を訪ね、天安門を背にしてはためく五星紅旗を見上げただろうか。広場の表情は実に多彩だ。春先の黄砂にかすむ広場、夏の強い日差しを照り返す地面、晴れ渡る秋空に舞い上がる凧、国慶節の華やかな飾り付けと行き交う人の波、凍りつくような寒風と一面の雪化粧、茜に染まる夕暮れ時に静かに国旗降納を見つめたことも何度かあった。
ある年の6月4日は日の出前から広場に出かけて、朝焼けの中で国旗掲揚を待つ観光客の晴れやかな笑顔を眺めた。またある年の6月4日には、文献集の図説を頼りに広場の端から端までを歩き、隊列を組んで行進する武装警察の草色の制服を目で追ったこともあった。その場所に自分の足で立ち、その場所で空を見上げて風に吹かれ、胸に吸い込む空気の匂いに気づいてこそ感じることのできる何かがあるのではないかと言ったら、いささか感情的すぎるだろうか。だが、所詮外国人に過ぎない者が、あの事件が中国の人びとにもたらしたものにわずかでも近づくことはできないかと思うとき、筆者にはまずそうした感覚的なものが必要だ。だからこそ、何度も広場を訪れては資料を読み、資料を読んでは広場を訪れている。
日付を確かめ、記述を読み、時には北京の地図や関連資料を広げながら、ようやく『チャイナ・クライシス重要文献』を読み終えた。事件の後、国外に脱出した民主化運動のリーダー数名が亡命先からパリに集い、「民主中国陣線」成立に向けて提案書を発表したのは7月20日のことで、文献集では第3巻の巻末近くに収められている。1989年の春から夏を辿るうちに、2009年の夏も本格的な暑さを迎えていた。
天安門事件を知るために、学ぶべきことはあまりにも多い。中国では事件に関する報道は厳しく制限され、あたかも歴史から消去されてしまったかのようだ。だが、この文献集をはじめ、現在では志ある人びとによって香港やアメリカなどで回想録などの資料が次々と出版されている。そうした資料を丹念に読みながら、民主化運動に関わった人びとの真意やしたたかさまでも真摯に読み解いていきたい。そして、書き手の「思い入れ」の強さには功罪があることを自戒しつつ、彼らの言葉を紡ぐようにして書いていきたいと思うのだ。
事件の背景となった当時の政治的、社会的、文化的な要因を探ることは、これからの中国を理解するためにも何らかの手がかりになるのではないだろうか。当コラムに「中国知識人群像」などという大仰なタイトルを掲げているのも、「天安門事件とは何だったのか?」という問いが、意識の底に澱のように溜まっているからにほかならない。そんなことを考えながら、2009年の日本から1989年の北京を想い、天安門事件20周年を迎えた6月4日前後を過ごした。
北京で暮らしていた頃に、まるで何かに引寄せられるかのようにして出会った友人たちがいる。民主化運動の熱狂と混乱の中で青春の一時期を過したいわゆる「八九一代(天安門世代)」と呼ばれる彼らとの出会いは、偶然であり、またどこか必然的でもあった。語り合った時間の分だけ互いを知るようになり、今でも時間を忘れて語り合う大切な友人たちだ。当時広場を埋め尽くした学生のひとりとして、あの時広場で目にしたこと、耳にしたこと、感じたことを話してくれる彼らは、事件当時有名だった学生リーダーではない。その後も北京で暮らしながら、遠ざかっていく1989年の記憶をそれぞれの方法で心に刻みつけている人たちだ。 ある年、そんな友人のひとりから「6月3日の夜に、天安門広場で」という誘いを受けた。1989年の天安門事件は、当初は「動乱」、その後に「反革命暴乱」、現在では「政治風波」と言われるが、一般的には6月4日の日付をとって「六四」と呼ばれている。だが、当時の関係者にとっては、戒厳部隊が長安街に現れて天安門広場周辺で学生や市民たちと正面衝突した6月3日の長い夜こそが、事件を記念し犠牲者を追悼するに相応しいのだろう。彼らは毎年ささやかな記念を続けているのだという。
「6月3日の夜に、天安門広場の記念碑の下に行って追悼するんだ。あれはまだ歴史なんかじゃなく、心の奥深くに根を張っているものだと、自分自身に対して言いたいだけだよ」、「気の置けない友人数名が天安門広場に集まる。特別なことは何もしない。ただ、その日に広場に集まるということに意味があるんだ。三々五々集まって、数人で立ち話でもして、それで終わりだよ」と聞いて、それが彼らの「記念の方法」であり、「追悼の作法」なのだと感じた。彼らが選んだ方法であると同時に、それが考え得る範囲で最も現実的な行動なのだろう。思いがけない誘いに、二つ返事で答えた。できることならばぜひ話を聞いてみたいと思ったからだ。もちろん、彼らの大切な集いを興味本位の外国人が邪魔をしてはならないが、友人のひとりとして受け入れてくれるならば許されるかもしれない。そして、ある年の6月3日夜、広場を目指した。
「8時に人民英雄記念碑の下で」という待ち合わせの約束は、広場に着くなり不可能だとわかった。いつもはライトアップされた天安門の夜景を見る観光客のために9時ごろまで開放されているはずの広場が、その日は7時に閉鎖されたらしい。広場の出入口に頑丈なゲートができたのはいつの頃からだったかと考えながら友人と歩いていくと、携帯電話で連絡を取り合いながらいつしか5、6名が集まっていた。まるで夕食の後に、ふらっと夕涼みの散歩に出かけたようないでたちで、たまたまばったり友人に会って立ち話でもしているかのようだ。地下鉄やバスで来た人がほとんどだが、中には自慢の高級車で登場した人もいた。二十歳前後だった学生たちはすでに不惑の歳に近く、ビジネスマンもいればジャーナリストもいて、中には会社経営者や研究者もいた。国家博物館の前で広場を眺めながら近況を報告しあう穏やかな語らいの様子は、ちょっとした同窓会のようでもあった。秘かな計画の発案者であった弁護士と大胆な言論で有名な作家のふたりからは、自由な外出ができなくなったことを知らせる携帯電話のショートメッセージが届いたようで、それもまた北京の現実だった。
重苦しい緊張感を打ち破るように、少し遅れてやってきた顔見知りのふたりが汗だくの笑顔で話し始めた。聞けば、北京大学の正門から数時間かけて徒歩で広場にやってきたのだという。あの頃、大学から広場を目指して歩き続けた道をたどり、あれこれ話しながら歩いてきたようだった。北京の町並みや行き交う人や車の流れは変わり、彼ら自身もずいぶん変わったのだろうが、それでも変わらないものがあればこそ、気の遠くなるほどの道程を排気ガスにまみれながら歩いてきたのだろう。それが、彼らのやり方なのだ。友人たちとのひとときの語らいの後、家に帰れば日常の生活があり、家族がいて、仕事もある。時間に追われるせわしない毎日の暮らしの中で、1989年は確かに遠い過去だ。だが、彼らにとって、事件は記憶の彼方に追いやって封印したものでもなければ、ただ懐かしいだけの思い出でもない。自分たちが信じた理想や希望が打ち砕かれ、やり場のない憤りややるせなさを抱えたまま歳を重ねた彼らは、現在それぞれの持ち場で直面している不正や理不尽と向き合いながら、それぞれの日常を懸命に生きているのだ。
 「あの時思ったのは……」と、編集者をしているという男性が話しかけてきた。銃声が響き戦車が近づいて来たときに、広場のどのあたりにいたかという話の続きだった。「あの時に思ったのは、カッコつけるわけじゃないが『愛と死』だった。初めて感じた死への恐怖、あぁ、これで死んでしまうのかという思い。それと、好きなあの子にまだ気持ちを伝えていなかったということ。死ぬ前に、思いきって告白しておけばよかったと、本気でそう思ったんだよ」と言って、少し照れくさそうに笑った。「そうだったのか!?」とからかう友人たちに、大真面目な表情で話し続ける彼の言葉を忘れまいと思ったとき、汗だくのひとりが「来年は一緒に歩くかい?歩きやすい靴でおいで」と声をかけてくれた。忘れることのできない、ある年の6月3日の夜のことだ。
「あの時思ったのは……」と、編集者をしているという男性が話しかけてきた。銃声が響き戦車が近づいて来たときに、広場のどのあたりにいたかという話の続きだった。「あの時に思ったのは、カッコつけるわけじゃないが『愛と死』だった。初めて感じた死への恐怖、あぁ、これで死んでしまうのかという思い。それと、好きなあの子にまだ気持ちを伝えていなかったということ。死ぬ前に、思いきって告白しておけばよかったと、本気でそう思ったんだよ」と言って、少し照れくさそうに笑った。「そうだったのか!?」とからかう友人たちに、大真面目な表情で話し続ける彼の言葉を忘れまいと思ったとき、汗だくのひとりが「来年は一緒に歩くかい?歩きやすい靴でおいで」と声をかけてくれた。忘れることのできない、ある年の6月3日の夜のことだ。
翌年、約束どおりスニーカーを履いて再び北京を訪れたが、前の年とは事情が一変していた。6月4日前後の緊張感は以前に増して高まっており、友人たちの中には「敏感な時期」に「強制的な里帰り」をすることになって北京を離れた人もいた。「無用な外出は控える」と不機嫌そうに言う友人からは「広場には近づかないほうがいい」と忠告があった。それでも、と思い出かけてみると、観光客でにぎわう昼下がりの天安門広場には異様な数の公安車両と武装警察が列をなしていて、それもまた、北京の現実だった。
天安門事件20周年にあたる今年の6月3日は、やはり北京で過ごそうと何年も前から考えていた。すでに北京を離れた友人もいれば、不当に身柄を拘束されて自由を奪われたままの知人もいる。それでも、この時期の北京を見ておきたいと準備をしていたのだが、出発の直前になって取りやめたのは、「いつものように家で原稿を書きながら、静かにその日を過ごすよ」という友人の作家の言葉が、重く響いたからだった。つまり、それが2009年の彼らのやり方だった。そうして、広場に集うことをやめた北京の友人たちを想いながら、20年目の6月3日の夜を、筆者もまたひとり静かに過ごした。
香山会議──2009・北京・六四民主運動研討会
天安門事件20周年を記念して大規模な追悼集会が開かれた香港のニュースや、関係者へのインタビューを報じる日本のニュースを見ながら、あらためて「香山会議」の資料を読み返さなくてはと考えた。5月中旬に北京から届いたメールには、いくつもの添付ファイルと、よく知る人たちの記念写真が添えられていた。集合写真の頭上には、真っ赤な横断幕に「2009・北京・六四民主運動研討会」と記されている。
 北京西郊にある香山は紅葉が美しい観光地で、この数年はマイカーブームに乗じた紅葉狩りの大渋滞がニュースで取り上げられる場所だ。その香山の麓で、5月10日に天安門事件と民主化運動20周年を記念する極秘討論会が開催された。中国語と英語で発表されたダイジェストには、「学者、公共知識人、弁護士、編集者及び六四によって投獄された人たち合計19名が会議に参加した。参加者は、1989年の六四事件の真相、その結果と意義、六四後の社会情勢、中国の民主化の前途、ならびに民族の和解を実現する可能性について発言し意見交換した」とあり、討論会の概要はその後インターネット上に公開された。
北京西郊にある香山は紅葉が美しい観光地で、この数年はマイカーブームに乗じた紅葉狩りの大渋滞がニュースで取り上げられる場所だ。その香山の麓で、5月10日に天安門事件と民主化運動20周年を記念する極秘討論会が開催された。中国語と英語で発表されたダイジェストには、「学者、公共知識人、弁護士、編集者及び六四によって投獄された人たち合計19名が会議に参加した。参加者は、1989年の六四事件の真相、その結果と意義、六四後の社会情勢、中国の民主化の前途、ならびに民族の和解を実現する可能性について発言し意見交換した」とあり、討論会の概要はその後インターネット上に公開された。
参加者は、徐友漁、莫之許、崔衛平、カク(赤+阝)建、徐暁、周舵、梁暁燕、秦暉、郭于華、李海、劉自立、銭理群、滕彪、田暁青、王俊秀、許医農、殷玉生、張博樹、張耀傑の19名だ。ほとんどが「08憲章」の第一次署名者303名のリストに名を連ねており、劉暁波が自由を奪われていなかったら、この記念写真に一緒に写っていたはずだ。氏名や写真をインターネット上に公開したことによるリスクをものともしないほどに、彼らには「自分たちが声を上げなければいけない」という壮絶な使命感があるのだろう。
写真には、劉暁波と「08憲章」の全署名者が2008 Homo Homini Awardを受賞した際にプラハで開催された授賞式に出席した徐友漁と崔衛平、自由主義の研究で知られる秦暉、「維権(合法的権利保護)」活動で有名な弁護士の滕彪、民主化について積極的な発言を続け『胡耀邦與中国政治改革――12位老共産党人的反思』((香港)晨鐘書局、2009年4月)を編集した中国社会科学院哲学研究所の張博樹、痛烈な社会批判で知られる中国芸術研究院の張耀傑、大学教員から環境保護のNGO活動に転じた梁暁燕らの姿がある。いずれも中国の民主をめぐる代表的な論客と社会活動家たちで、共通するのは当時デモに参加するなどして直接的に民主化運動に関わったということだ。
中でも周舵は劉暁波、侯徳健、高新らとともにハンストの決行や戒厳部隊との直接交渉で脚光を浴びた「四君子」の一人だった。彼らの「六・二ハンスト宣言」は政府と学生の双方に反省を呼びかけ、中国の歴史や文化までも批判的に論じて公民意識の重要性を説き、「民主政治の真の実現とは、運営の過程、手段、手順の民主化である。(中略)それはあらゆる具体的事柄から開始すべきである」と主張した。当時、「民主化運動」の現実と限界を自己批判的に訴えた精神は、その後20年という時間を費やして「08憲章」に結実したと言うことができるだろう。
天安門事件に関する発言が厳しく制限されている中国国内で、事件をめぐる討論会を企画し実現させたことはやはり特筆すべきことだ。香山会議の開催に様ざまな困難があったことは想像に難くない。計画が明らかになれば、開催が阻止されるだけでなく関係者への事情聴取や家宅捜索がなされるであろうことは容易に想像でき、重苦しい気分は拭いきれない。盗聴による情報漏えいを防ぐために、おそらく関係者は直接顔を合わせて話し合いながら準備をしてきたのだろう。19名という参加者は少人数ではあるが、参加したくても叶わない人、彼らと志を同じくしながらも参加を躊躇した人たちは、おそらく参加者よりも多いはずだ。
討論会は冒頭3分間の黙祷から始まった。最初に発言した銭理群は魯迅や周作人などの研究者として知られる元北京大学教授だ。当時、立ち見が出るほどの人気講義に影響を受けた多くの学生たちが運動に参加したという。銭理群は討論会への参加理由を次のように語った。
動機のひとつは教師としての良知によるものだ。20年前、多くの学生が中国の民主の事業のために命をささげたが、わたしは教師として彼らを護れず、ずっと後ろめたさを感じてきた。苦難にあった学生を護るのは教師として当然の責任であり、北京大学の伝統でもある。(中略)学生が犠牲になったのに護れなかったのだからすでに負債があり、学生が濡れ衣を着せられたまま今でも冤罪が晴らされないのにそれでもなお発言しないというのは、教師として恥ずべきことだ。そしてもうひとつは、学者としての良知による。政治家は六四を再評価せずともよいが、しかし学者は必ずや六四を歴史に書き込み、学問的な討論と研究を行わなければならない。
銭理群の言葉は重く、そして静かに響く。何年も前のことになるが、彼の書斎を訪ね「血の通った、体温のある歴史を学び、語ることが大切なのだ」という話を聞いたことがあった。銭理群が当時を振り返り、心の奥深くに残る傷跡から絞り出すようにして語った言葉は、歴史や社会に対する知識人の道義的責任として、多くの人の心に届くに違いない。
香山会議に関しては、その後主な参加者の報告要旨や論文がインターネット上で少しずつ公開されている。例えば、徐友漁は「六四事件は中国の政治体制を変えることはなかったが、しかし中国の政治体制改革が緊迫していることを明らかにし、かつ思想的な条件を整えた」と語った。また、張博樹は「現体制には活路がなく、最終的には真の憲政民主制度に取って代わられるとわたしたちは主張しているが、その一方で、わたしたちは為政者を“敵”とは見なしていない。人びとは歴史の大勢に従って改革の促進者となり、もはや阻害者ではない。これはより高度な道徳的基礎であり、全く異なる政治的思考と政治文化を体現したのだ」と主張した。香山会議は20年前の事件を記念するだけでなく、中国の現実を憂いながらも未来を思考する知識人たちの強い志が語られた集いだったといえよう。
最後に、崔衛平の発言を紹介したい。
こんなにも長い間、わたしたちは六四について集団的に沈黙を守ってきたが、実質的にはその犯罪行為の隠蔽に加担してきたのであり、そのことに対してわたしたちひとりひとりにすでに一定の責任がある。(中略)六四20周年にあたり、わたしは周りの全ての友人たちに問いかけたい。20年来の沈黙と隠蔽が、わたしたちの社会にもたらした影響とは何だろうか?わたしたちの民族の精神と道徳に、どのような損害をもたらしただろうか?そして、わたしたち自身の仕事や生活のなかで受けた損失とは何だろうか?わたしたちは、まだ沈黙しつづけるつもりなのだろうか?
彼らの訴えや問いかけに、「拒絶遺忘(忘却を拒絶する)」という銭理群の文章を思い出した。「強いられた忘却」を拒絶するのは、「歴史の悲劇を繰り返さないため」にほかならない。忘却の彼方に押し流されていくものを、彼らはその流れに抗いながら声を上げ、語り続けようとしている。(文中敬称略)
注:文中で取り上げた、矢吹晋編訳『チャイナ・クライシス重要文献』(全3巻、蒼蒼社、1989年)には、姉妹編である論文集『天安門事件の真相』(上下巻、矢吹晋編著、蒼蒼社、1990年)、『チャイナ・クライシス「動乱」日誌』(村田忠禧編著、蒼蒼社、1990年)がある。