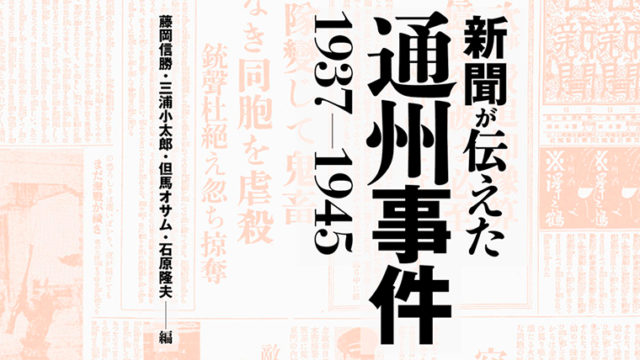文化財と共存 街づくり問う
文化財と共存 街づくり問う
歴史都市の景観は、文化遺産としてすっかり市民権を得たようだが、振り返ると、開発と発展の下に、その多くは失われてきた。 元、明、清歴代王朝の都市として威容を誇った北京は、今なお近代化の荒波に翻弄されている。半世紀以上前、ここで文化財との共存を模索した研究者がいた。
中国を代表する建築学者、梁思成。彼は北京の都市計画において古建築の救済に奔走する。城楼を壊し、れんがをはぐのは、自分の肉をえぐり、肌をはぐようなものだ、と。
50年、彼は都城を保存し、城壁の外に行政区の中心を建設するプランを作り上げる。しかし、複雑な社会情勢は、それを許さなかった。50〜60年代、城壁は壊され、多くの遺産が消えた。いまも北京は、膨張を続けている。
執筆者の王軍は新華社通信の記者。本書では、東京で生まれた梁が、太平洋戦争で京都、奈良の保護にかかわった可能性も示唆している。300を超える図表や写真、挿絵も貴重な史料だ。
本書は文化遺産と都市機能が共生した、これからの街づくりのあり方に貴重な指針を与えてくれる。
朝日新聞(西部本社版/夕刊)2009年1月23日
古都はいかに破壊されたか
高層ビルの建ち並ぶ中国の首都北京の中心部。60年前の建国当時は、明代の城壁をめぐらした城内に四合院(伝統様式の建築物)と胡同(路地)がひしめき、文化遺産の香りを放っていた。しかし建国当初の古都保存の声は圧殺され、城壁は撤去、四合院も胡同も次々に消滅していった。
本書(原題『城記』)は、清末の思想家、梁啓超の長男で、著名な建築家だった梁思成(1901〜72)らの保存論が、改造論に敗れていく過程を追う。北京の住民が大気汚染や交通渋滞に悩む今日、人間らしい都市とは何か考えさせられる労作だ。
梁思成は父の亡命先の東京で生まれ、辛亥革命後に帰国。その後、米国に留学して建築学を学び、30年代から中国建築界をリードした。伝統文化に愛着を持ち、太平洋戦争末期、京都、奈良を原爆投下目標から外すよう米国に訴えた逸話は教科書にも載った。
北京の都市改造計画は、新中国発足前から始まったが、消費都市から工業都市に改造するよう主張する共産党に対し、梁思成や英国で建築学を学んだ陳占祥は、西洋の都市建設の教訓に立ち、貴重な文化財の多い旧城内の保存を求めた。
2人は「梁陳プラン」と呼ばれる計画案を提起。行政機関を城外西部に移すほか、工業区や住宅区なども城外に設け、城内の建築物は3階以下に制限するといった内容だが、「天安門楼上から至る所に煙突が見える」のを望む毛沢東に受け入れられるはずはなかった。
建国当時、7階建ての北京飯店が城内唯一の高層ビルだったが、長安街周辺に政府ビルなどが次々に建てられ、近代化の障害とされた城壁の撤去が進む。梁思成が現実の前に後退を重ねつつ、文化遺産を守ろうとする姿が痛々しい。
新華社記者の著者は、北京改造をめぐる未知の歴史発掘に成功した。梁思成に共鳴しながら、梁への反対論や党が改造を急いだ背景も紹介、客観的に評価しようとする姿勢が好ましい。
原著は2003年の発刊後、大反響を呼んだ。08年五輪前の再開発で、由緒ある四合院も破壊を免れず、環境や文化財保護への関心が高まっていたからだ。建国以来の発展第一主義にその原点はあった。それを明かしたのも本書の功績である。(集広舎・4830円)
伊藤正(北京特派員)産経新聞2009年1月25日