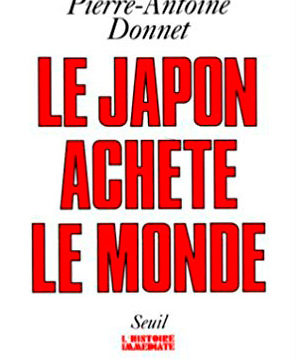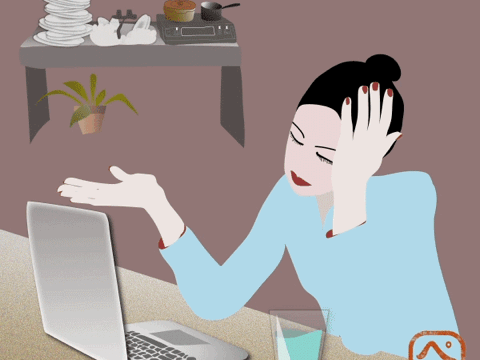1月に訪れたシンガポール。ビジネスと商業の中心街のエスプラナードで久しぶりに現地の女友達のケイト(中華系、仮名)とペナン料理バイキングを食べた。よもやま話のなかで、彼女の父親が長寿を全うして亡くなったという話になった。
ケイトは9人兄弟の末っ子だ。
ケイトの父親は相当な財産家だったらしい。ペナン風プローンミーを啜りながら、お葬式、そして9人の子供や20人を超える孫たちへの遺産分けについて語られる内容に興味深く聞きいった。
話が終わるとケイトに不謹慎にも聞いてしまった。
「で、相続税(Inheritance Tax)はどうした?」
「え、ソウゾクゼイ?」ケイトは不思議そうに首を小さく傾けた。
「……ごめん、何のこと? よくわからない」
シンガポールには相続税はないと聞いていたが、それは本当だった。投資銀行で長年働く金融のプロのケイトすらその概念を知らなかったのだ。
相続税がない…
ケイトがトイレに行っているあいだ、わたしは夜景を眺めながらつぶやいた——「相続税がない。だから節税対策がない。だから街も美しい」
実際、欧米やシンガポールの住宅地の景観は美しいのは相続関連の不動産税制に起因する部分が大きい。
わたしは昼間歩いたシンガポールの瀟洒な住宅街の景観を反芻し、東京のわが街と引き比べた。
一つ一つの家をみれば、東京の住宅にはシンガポールに負けないものもある。歴史ある文化財もあり、趣のある庭園もある、国際標準の商業コンプレックスもある。官公庁の建物も立派だ。都心の夜景は美しいし、海や山もいい。だが、こと一般住宅街の街並みの美しさという点に関してはシンガポールにとうてい適わない。
東京の残念な景観は無秩序な電柱や広告が連なるせいだけではない。
まとまった敷地の小綺麗なお屋敷や趣ある日本家屋はみるみるペンシルハウスと呼ばれる狭小住宅や安普請の収益用賃貸アパートに変わっていく。あるいは駐車場やコインランドリーに化ける。しばらくすると、区画全体が愛想のない金属の囲いで覆われてマンション建設用地になる。周囲住民の建設反対の旗がひらひらと舞う。
高度成長がとうに過ぎた今も街並みの変化は果てしがない。
人が死ぬと家は価値を失い、庭は潰される。駐車場への転用、自動販売機の設置など涙ぐましい庶民の経済合理性が景観をどんどん悪くしていく。
ペンシルハウスも安普請の収益用アパートも自販機も、これまで訪れたどんな国にもなかった。
元凶は税制だ。
子孫に美田を残さず──富は1代限りという特殊性
相続税は1世代が築いた富を次の世代にストレートに引き継がせないようにする仕組みだ。世界を見回せば、日本ほど過酷な相続税制がある国はない。シンガポール、ニュージーランド、カナダ、オーストラリア、中国、マレーシアなどにそもそも相続税が存在しない。欧米の大半の国でも課税対象は大金持ちだけである。
多くの移民国家に相続税がないのは国民の価値観のせいだ。異国の地に移り、そこで生業を営み、恒産を築いてきた人たちの子孫は、その血と汗の結果が国家に収奪されることを死力を尽くして防ごうとする。国家の制度は国民の価値観からかけ離れたところには作られない。作れば国家は転覆されるだからだ。
「子孫に美田を残さず」はグローバルスタンダードからかけ離れているのだ。
子孫に美田を残すため死力を尽くす人たち
海外華僑は人口過多の狭小な土地で戦乱や飢饉に苦しんできた中国の大地を父祖の地とする人たちの子孫だ。
彼らは万事につけ国家や大組織を信用しない。異国の生態系を巧みに把握し、それに適応し、計算力を行使して弱き異民族を利用し、時に搾取し、強い民族には恭順の意を示し、アメーバのように柔軟にたくましく生きてきた。
彼らを異郷の地の労働や商売の辛さに耐えさせる原動力は、子供たちにだけは同じ苦労させたくないという切ない思いである。
その理想郷は、汗水流す労働から解放され、世代を超えて永遠に一族の不労所得フローが滝のように流れ続ける世界だ。世界も労働も組織も事業も土地も、究極的には福徳(カネと子孫)のための手段に過ぎない。
 中国人にとって流れる水は生命力と冨貴の象徴
中国人にとって流れる水は生命力と冨貴の象徴そんな移民が作った国、シンガポールの未来主義的な都市のジャングルを注意深く分け入ってみれば、人々の本音の切れ端をあちこちに見ることができる。
レッドとゴールドの色が氾濫し、「恭喜发财(お金持ちになれるように)」、「万事如意(思い通りになりますように)」など、ストレートな欲望が刻まれた道教の祠。一方、シンガポールの団地の商店では線香や仏像に混じり、ダンボール製の張り子の札束やらヴィトンのバッグやらが売られている。葬式の副葬品だ。それらを死者と一緒に焼くことで、遺族は(必ずしも生前に成功しなかった)故人があの世で豊かに暮らしていると想像して安らぎを感じる。
華僑にとって黄泉の世界は現世と地続きで、子供は冨貴のアナロジーだ。
シンガポールの19世紀の歴史をみると、著名な華僑大商人はこぞって一夫多妻でたくさんの子供を遺している。
増殖する、という点で富と子供は似ている。カネの増殖に対する思いが信仰の域まで高まった世界では、自らの富が子供に継がれ、それがさらに増殖を続けると想像することで自己の「不死」が実現される。
運と偶然に左右される人の一生は成功を達成するにはあまりに短い。自己のアバターである子供は多ければ多いほど死=個体消滅への恐れは薄らぐ。より実用的な意味でも兄弟姉妹がたくさんいれば、それはビジネスネットワークの拡大と富の増殖可能性の広がりにつながる。
もちろん、今日の平均的シンガポリアンはもう子沢山でない。一夫多妻制はとうに滅び、今は金持ちも貧乏人も核家族のマンション暮らしだ。出生率は低く、サラリーマン、団体職員、公務員など、日本人と似たような職業と身なりの人ばかりだ。
それでも、華僑の家族主義やカネや投資に対する根本姿勢は今も昔も変わらない。
シンガポリアンにはマレーシア、インドネシア、香港など親戚が国境を超えて分散している人が多い。日本人なら「遠くの親戚より近くの他人」だが、シンガポリアンはどれだけ遠くに住んでいても家族ファーストだ。
年中行事、冠婚葬祭、家族のご機嫌伺いなど、親戚が集まる機会は多い。大家族──イトコやらハトコやらチンバイトコやら大叔父の遠縁の息子やら——が、さまざまな用事にかこつけ、絶えず国境を超えて行き来し、情報を交換し、有利な投資先の情報を共有し、金を融通しあい、リスクを互いに分散する。ホーカーの店主もサラリーマンも主婦も副業、投資、財テクに対するリテラシー、関心がきわめて旺盛で、そのことを隠そうともしない。有用な投資情報は知人や同僚よりまず親戚縁者同士で共有され、募集残があるときだけ、アウトサイダーに声を掛ける。
安全で自由な経済活動が保証された場所こそ彼らのの理想郷である(それはすでに東南アジアで実現している)。シンガポール、マレーシア、インドネシア、香港。いずれも相続税、贈与税、株式キャピタルゲイン税がない。
将来、どんな国家財政の逼迫があろうとも、貧富の格差がどれほど広がろうとも、シンガポールで相続税導入が議論されることはないだろう。
アジアのスイスになれない日本
逆にまた日本で税制の抜本改革が行われる兆しはない。「相続税をグローバルスタンダード並みに」などというような提言はネオリベ的金持ち優遇策として受けが悪い。
もちろん、相続税にメスが入らなければ、将来、日本が「アジアのスイス」となり、富裕な移民が移り住むことなどありえない。
かくして、人口が減少するなかでもわが国の国土は永遠に普請中の状態が続くだろう。複雑な都市景観改善や住空間の充実といった課題が真剣な政治アジェンダとなることはないだろう。むしろ、これから老人が増えれば増えるほど、社会全体の生産性が落ちれば落ちるほど、法をかいくぐる小手先の節税商品や節税ビジネスばかりが繁栄するだろう。
「そうやって日本はどんどん取り残されていく….」
わたしのとりとめのない憂鬱を吹き飛ばすように、レストランでの話題はケイトが最近観光で訪れた北海道の大自然や飛騨の古民家宿に移っていた。
「日本はキレイ。食事も美味しいし、人も親切、安全。何回でも行きたいわ」
「そう。ありがとう。今度は日本で会おうね。ウチで日本食をごちそうするよ」
「うん、東京行くとき連絡する」
とうに50を過ぎているのにケイトは活気に満ちて若々しく、ハイヒールの後ろ姿は軽やかで自由に見えた。帰りのタクシーの車窓に流れたマリナベイサンズのシルエットがまるで竜宮城のように見えた。