地球市民的な立場から新しい構造の経済を目指す社会的連帯経済の場合、当然ながら多文化主義もその中に含まれる一方、その意味合いについて深い考察が行われることは意外に少ないような気がします。今回と次回は多文化主義的かつ文化人類学的な観点から、社会的連帯経済における異文化間、特に大陸間での対話について考えてゆきたいと思います。
世界にはさまざまな文化があり、ある文化圏では当たり前のことが、別の文化圏では品のない仕草と批判されることも少なくありません。たとえば日本では味噌汁やラーメンなどの汁を飲むときに音を立てても問題ありませんが、西洋文化圏では下品だとみなされます。また、西洋文化圏ではファーストネームの呼び捨てで呼び合うことが多いですが、日本では基本的に苗字に「さん」、または「先生」や「課長」などの肩書をつけて呼ぶことが一般的で、下の名前を使うのは基本的に同じ苗字の人が複数いる場合のみであり、そして呼び捨ては大抵の場合、失礼とみなされます。このように文化は、世界各地で、そして場合によっては国内でも地域によってかなり違うものです。
しかし、ここで取り扱う文化は、上記のように目に見えやすい作法的なものではなく、むしろ私たちの行動規範として隠然とした影響を持っている価値観のことを指します。そして社会的連帯経済の分野でこの文化について話す場合、それぞれの事例が社会運動として持つ文化だけではなく、それぞれの運動が生まれた文化背景を理解することが欠かせません。
社会的連帯経済はラテン系諸国で活発に組織運営が行われていますが、その背景としてラテン系諸国特有の文化、具体的にはカトリックを基盤とする伝統的な助け合いの文化や、フランス革命により世界に広まった「自由・平等・博愛」という理想(詳細はこちらで)、そして各地独自の社会運動の歴史(カタルーニャについてはこちらで、ブラジルについては反軍政運動や、パウロ・フレイレの民衆教育の伝統など)があることを見逃してはなりません。海外の事例を目にする場合、私たちはどうしても目に見えやすい現地の事例のみに注目する傾向がありますが、その裏にはこれら実践例を支える価値観があり、そこまで理解しないと事例を本当に理解したことにはならないのです。
また、韓国や香港では社会的企業に対する関心が高く、行政も積極的に支援していますが(韓国社会的企業振興院、香港政府の社会的企業ポータルサイト)、個人的にはその背後に、儒教的な価値観があるような気がします。儒教の基礎である論語では、君主が仁徳をもって国を治めることの大切さが説かれていますが、韓国や香港の事例を見ていると、このような伝統的な価値観が、社会的企業の推進において大きな影響を与えているように思われます。
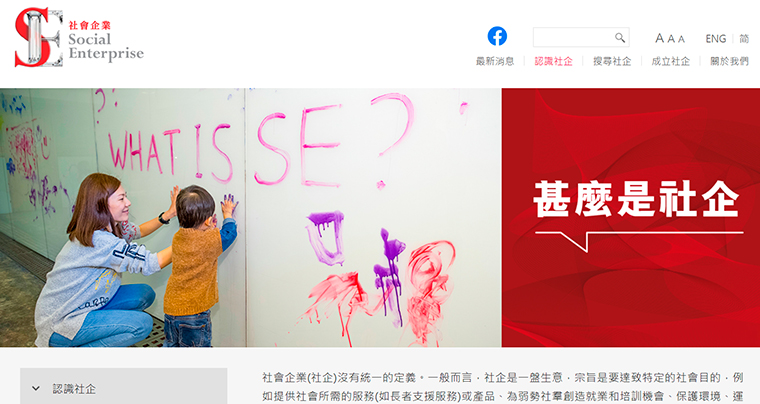 香港政府の社会的企業ポータルサイト
香港政府の社会的企業ポータルサイト当然ながらラテン的価値観と儒教的価値観では、その基盤が違うため、それにより最終的に目指す社会像も自ずと異なってきます。ラテン的、そして特に民衆教育的な価値観の場合、誰が特定の個人がリーダーとなって引っ張ってゆくのではなく、基本的に全員が平等な立場でそれぞれの役割を果たしながら社会全体を変えてゆくことを模索します。もちろん組織である以上、たとえば協同組合の理事長などの役職は必要ですが、基本的に特定の個人が長年その役職にしがみつくのではなく、半年なり2年なりといった短期で役職を入れ替えたり、または日頃から組織内で会議を開いて民主的な意思決定手続きを確保したりする努力が重要視されます。
その一方で儒教的な価値観では、あくまでも経営者と一般従業員という階層社会自体を肯定したうえで、企業における君主たる経営者が仁徳をもって経営を行うべきだという発想が強い感じがします。儒教自体は、民主主義という発想と無縁な当時の(紀元前6世紀から5世紀にかけての)中国の社会状況の下で孔子が編み出した哲学をまとめたものですが、君主制のみが社会統治において実践可能な形態であるという前提の下で、どのように君主が振る舞えば社会全体が反映し、平穏な社会になるかという帝王学が主に議論されており、この発想を社会的企業の経営に応用しようという傾向が、韓国や香港では強く見られます。前述のパウロ・フレイレであれば「偽の寛容さ」と批判するようなものかもしれませんが、私が今まで見聞きした限りでは、韓国や香港以外のアジア諸国でも(儒教文化圏以外を含めて)、このような価値観のほうがラテン的価値観より受け入れられやすい気がします。
この他特記すべき事項として社会的連帯経済では、さまざまな社会的弱者(先住民族や少数民族、女性や障碍者など)が活躍している事例も少なくありません。彼らはさまざまな理由から、資本主義企業の第一線で働けない事情を抱えていることが少なくありませんが、特に彼ら自身が設立した協同組合や、彼らに雇用を生み出すべく設立された社会的企業の場合、あくまでもこのような人たちへの福利提供を存在意義としており、前述の事情を鑑みたうえで、彼らに配慮する形で事業を運営することになります。
しかし、従来の支配的な文化が社会的連帯経済と親和性が悪いからといって、それ以外の文化が社会的連帯経済の価値観に100%調和しているわけではありません。先住民族や少数民族の伝統文化の中には、男女差別や家父長独裁など社会的連帯経済に合致しない価値観が残っているケースが少なくなく、むしろ社会的連帯経済の推進において障害となるケースも多々あります。また、社会的弱者の文化を大事にするのはいいのですが、だからといって社会的弱者とされている人たちの文化や価値観が絶対善であり、他者はそれを無条件に受け入れるべきだという意見には、私は賛同できません。あくまでも文化相対主義的な立場から、どの文化であれ社会的連帯経済と調和する価値観もあれば、そうではない価値観もあることを認識したうえで、内なる改革にも取り組み続ける姿勢を持つことが欠かせないのです。
社会的連帯経済の事例については私も長年数多くの事例を見てきましたが、社会運動の常として外部者への批判は得意でも、自己批判や自己改革には意外に消極的な人も少なくありません。ブラジルの連帯経済に大きな影響を残したパウロ・フレイレ(1921~1997)は、その代表作「被抑圧者の教育学」において「農民の中で現場監督に『出世』した者の中で、以前の仲間に対して雇用主以上に抑圧的にならない人は少ない」と書き残しています。例えば経営者が労働者を酷使している状況を見ると、経営者=絶対悪、労働者=絶対善のような印象を受けることが少なくないですが、実際にはこの労働者は、単に経営者になれなかっただけの人間で、何らかの理由でこの労働者が経営者やそれに近い立場になると、彼らと同じように部下に対して厳しく当たるケースは少なくありません。また、大企業の同期入社の社員で、新入社員当時は仲良かったものの、そのうち誰かが先に昇進すると、残りの同期の人たちに対して威張り散らかすケースも珍しくないものと思われます。社会的連帯経済においては、単に自分たちの外にいる抑圧者と戦うだけではなく、むしろ自分たちの中にある抑圧者性とも戦う必要があるのです。
次回は、このような状況を踏まえたうえで、社会的連帯経済の各種運動が盛んなラテン世界と、日本を含むアジア諸国における対話において、どのような点を理解することが大切なのかについて紹介してゆきたいと思います。




















